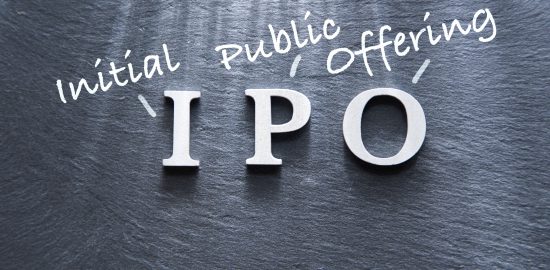証券アナリスト=三浦毅司(日本知財総合研究所)
5月7日に「知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言書」が発表された。大手企業20社の経営者や知財責任者が発起人となり、知的財産権を無償開放して新型コロナウイルスの早期終結を目指す趣旨だ。賛同者はその後も増え、6月11日時点で79の企業が参加している。
有効期限は新型コロナ終息宣言まで
この宣言書は画期的だ。新型コロナウイルス感染症のまん延終結を目的とした開発、製造、販売などの行為に対し、賛同する企業、研究機関、個人は国内外で保有する知財権を行使しない。目的と期間は限定するものの、原則として企業などが国内外に保有するすべての特許権、実用新案権、意匠権、著作権が対象となる。
有効期限は世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルス感染症の終息宣言を行う日までとしている。SARSウイルスでは、2002年11月に最初の患者が報告された。8000人を超える症例が報告され、WHOが2003年7月に終息宣言を発表するまで9か月を要した。今回の新型コロナでは感染者数がすでに660万人を超えており、終結宣言が出るまでにはるかに長い期間を要するだろう。
知財の無償解放の例としてはトヨタ自動車が2015年1月に発表した燃料電池関連の特許(審査継続中を含む)の実施権無償提供(約5680件)、2019年4月発表のモーター、パワー・コントロール・ユニット、システム制御等の車両電動化関連の技術の特許(審査継続中を含む)の実施権無償提供(約23740件)が有名だが、これらは市場の拡大を目指したもので、対象特許を当該技術分野に限定している。今回の新型コロナに関する無償解放は保有するすべての知財が対象となり、従来の事例とは大きく異なる。
今回、参加を表明した企業に製薬会社が含まれないのは象徴的だ。製薬会社にとっては新薬開発にかけた巨額の研究開発費の回収を担保する特許を無償解放することは困難であり、イニシアチブへの参加を見送ったと考えられる。米国でも同様の知財開放イニシアチブ(Open COVID Pledge)が稼働しているが、日本と同じく製薬会社の参加はない。
イニシアチブに参加した企業は電気機器、輸送用機器、情報・通信などが多い。研究開発の過程で医療への転用が可能だが事業化が不十分であった特許について、事業パートナーの範囲を広げて可能性を探ろうとするものと考えられる。こうした取り組みであれば研究開発の費用は本業ですでに回収されている場合が多いとみられ、イニシアチブ参加についてステークホルダーへの説明も可能と思われる。
■知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言書参加企業の業種

出所:知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言事務局のデータを基に日本知財総合研究所作成(非上場企業の業種は日本知財総合研究所が判断)
ライセンシーのリスクを軽減
通常、特許のライセンス契約は踏査・条件交渉に長期間かかることに加え、長期にわたるライセンス料の支払いを余儀なくされる。ライセンスを受ける側(ライセンシー)には事業化のリスクがあり、実現しないケースも多い。今回のようなイニシアチブでライセンシー側の負担が大幅に軽減され、比較的容易に提携が進む。
新型コロナ感染症対策を機に知財の「お試し利用」が進めば、従来の枠組みにとらわれない新しい組み合わせの事業展開につながる可能性もある。新型コロナから一歩進んで、事業化の入り口になる知財のライセンシー負担軽減の先駆けとなるか、注目される。(2020年6月8日)
日本知財総合研究所 (三浦毅司 [email protected] 電話080-1335-9189)
(免責事項)本レポートは、レポート作成者が信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、レポート作成者及びその所属する組織等は、本レポートの記載内容が真実かつ正確であること、重要な事項の記載が欠けていないこと、将来予想が含まれる場合はそれが実現すること及び本レポートに記載された企業が発行する有価証券の価値を保証するものではありません。本レポートは、その使用目的を問わず、投資者の判断と責任において使用されるべきものであり、その使用結果について、レポート作成者及びその所属組織は何ら責任を負いません。また、本レポートはその作成時点における状況を前提としているものであって、その後の状況が変化することがあり、予告なく変更される場合があります。