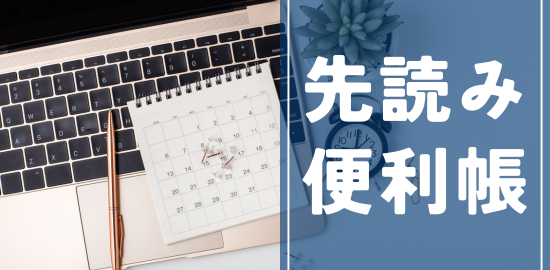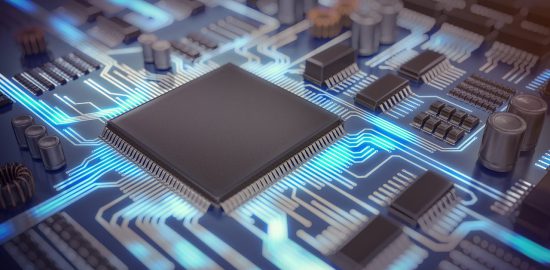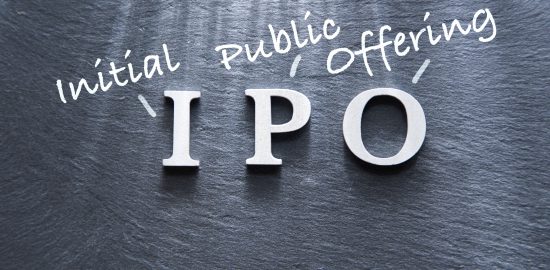今週は香港株式市場で飲食関連の新規株式公開(IPO)が相次ぐ。9月8日の中国ミネラルウオーター生産の農夫山泉に続き、10日には中国で「ケンタッキー・フライド・チキン(KFC)」などを展開する外食大手のヤム・チャイナ・ホールディングスが上場する。「食欲の秋」だが、投資家の人気はいまのところ明暗が分かれている。
■申込金額が過去最大
農夫山泉が7日に発表した一般投資家の購入申し込みは、応募倍率が割当枠の1148倍に達した。香港経済日報などの香港メディアによると、一般投資家の申込金額の合計は約6400億香港ドル(約8兆8000億円)に上り、香港市場の新規上場銘柄では過去最大となった。同社の飲料水は中国国内でのみ販売しているため、香港では商品を手にしたことがない投資家も多かったはず。それなのに、約180倍の応募があった京東集団(JDドットコム)など、今年上半期に上場が相次いだニューエコノミー株をしのぐ大人気となっている。
一方、香港紙の報道によると、ヤム・チャイナが4日に締め切った一般向け公募の応募倍率は50倍程度の人気にとどまった。同社は「KFC」のほか、「ピザハット」、メキシカンフードの「タコベル」などを運営し、6月末時点の店舗数は9954店に上る。知名度は抜群で、8月末に同社の上場計画が伝わるなり売買増の思惑から香港取引所株が急伸したほどだったが、実際の人気はいまひとつだ。
■公開価格、利益率、「内食」需要
明暗を分けた理由の1つは公開価格にある。農夫山泉は1株21.5香港ドルだが、ヤムは412香港ドル。ヤムの単元株数は50株なので最低2万600香港ドル(約28万2400円)を必要とする。農夫山泉(単元株数は200株)の5倍近くの軍資金を準備しなければならず、個人投資家にとってはやや「入場料が高い」銘柄になった。
農夫山泉は「水の貴州茅台酒」「中国のコカ・コーラ」とも呼ばれる利益率の高い飲料大手。なにしろ原料は湧き水なので、穀物などが原料の白酒やジュースよりも原価率が低い。開示資料によると、同社の2020年1~5月の売上高総利益率は59.1%。60%超の利益率を誇るコカ・コーラと並ぶ水準だ。
さらに新型コロナウイルスの影響が続くなかで、「内食」需要を取り込みやすいという点もある。コロナ禍で「外食」が減り、日清食品ホールディングスの子会社、香港日清など中国本土で事業を展開する「内食」株に投資家の関心が向きやすくなっている。

一方、「外食」のヤム・チャイナはコロナで打撃を受け、20年1~6月期の既存店売上高は前年同期比13%の減収だった。持ち帰りなどに力を入れているが、消費減退や営業制限などの影響は当面続くとみられる。市場では「KFCなど既に確立されたブランドを運営しているだけで、先行きの事業発展が期待しにくい」(金利豊証券の研究部執行董事の黄徳几氏)との厳しい指摘も聞かれる。
香港では今後も中国企業を中心にIPOが活況を呈するだろう。ただ、主役はアリババ集団傘下の金融会社アント・グループなどニューエコノミー銘柄。飲料や飲食などオールドエコノミー株がきらりと輝くには知名度だけでなく、農夫山泉のような高い収益力が欠かせない。(NQN香港 桶本典子)
<金融用語>
公開価格とは
特定の株主のみが保有していた会社の株式を、不特定多数の投資家が自由に売買できるよう新たに公開する会社の株の公募・売り出し価格(=発行価格)のこと。価格を決める方法には、一般競争入札方式とブックビルディング方式があるが、現在はブックビルディング方式が主流となっている。