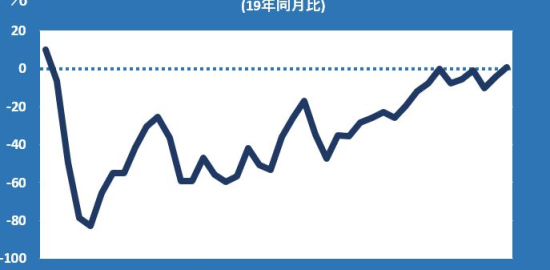新型コロナウイルス感染症対策として支給が始まっている、国民一律10万円の特別定額給付金。それを一部の個人投資家が資産運用に回している――。最近市場で話題となっている動きについて、麻生太郎財務相は2日の記者会見で特に言及しなかった。生活支援という本来の政策意図とはかけ離れているが、市場では政府としても貯蓄でなく投資に回るのならそれも許容、もしくは歓迎なのではといった見方も広がっている。
■政府にとって個人マネーの流入は歓迎すべき流れ?
麻生財務相は、一律給付が決まる前の3月24日の会見で「現金(給付)でやった場合、それが貯金に回らず消費に回るという保証は(あるのか)」と、一律の現金給付そのものに難色を示していた。自身が首相を務めていたリーマン・ショック後、2009年に配られた「定額給付金」は多くが貯蓄に回ってしまった経緯があり、同じ轍(てつ)は踏みたくないとの思いがあったのかもしれない。
ところが、現金給付の開始と「コロナバブル」とも呼ばれる歴史的な株価急伸のタイミングが重なったことも幸いし、個人の投資余力の拡大がクローズアップされている。「貯蓄から投資」の音頭を取り、少額投資非課税制度(NISA)や個人型確定拠出年金(イデコ)などの制度活用を促してきた政府にとって、株価底割れの回避にもつながる個人マネーの流入は歓迎すべき流れとも読める。
それゆえか、麻生財務相は2日の会見で、財政維持の観点から株式などの譲渡益への課税強化を検討する考えはないかとの質問に「現預金の比率が日本の場合は高すぎる」と否定的な考えを示した。
■現金給付は投資開始の「良いきっかけ」
第一生命経済研究所の熊野英生首席エコノミストは「経済活動の再開に歩調をあわせるように給付金の一部が市場に流れれば、株価の上昇要因になる」と話す。一律10万円という多額の現金給付だからこそ「生活に余裕のある個人が投資へと資金を振り向けるかどうかを考える良いきっかけになっている」(熊野氏)というわけだ。今回の現金給付は、景気や消費の下支えだけでなく、投資への流れの加速という思わぬ「副産物」を生む可能性もありそうだ。〔日経QUICKニュース(NQN)大貫瞬治〕