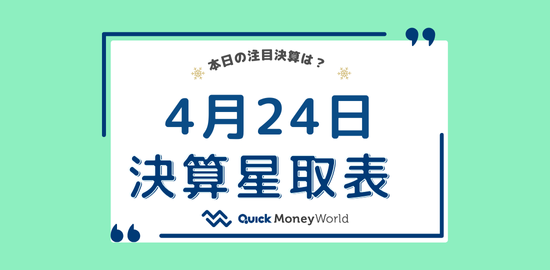【QUICK解説委員長 木村貴】米トランプ政権が打ち出した異例の関税引き上げ政策をきっかけに、経済ニュースで「スタグフレーション」という言葉を目にすることが増えてきた。「米中貿易戦争が激化すれば、スタグフレーションが現実味を帯びる」といった具合だ。
スタグフレーションとは、物価高と不況が同時に続く現象を指す。不況を示す「スタグネーション」と物価高を意味する「インフレーション」を組み合わせた言葉だ。
経済の混乱がこのまま続けば、スタグフレーションが現実になってもおかしくない。日本はここ数年、物価上昇率が2%を超える一方で、実質経済成長率はほぼ横ばいが続いている。インフレと不況の同時進行に陥る恐れは小さくない。
もしそうなった場合、厄介だ。理由は2つある。1つは、スタグフレーション自体、特異な経済現象であり、金融緩和や財政出動といった通常の経済対策では克服できない。思い切った発想の転換が必要になる。もう1つは、日本の場合、その発想の転換ができるかどうか心もとない。下手をすると、いつまでも適切に対処できず、世界の中で日本だけがスタグフレーションから抜け出せなくなる恐れもある。
この2点について、説明しよう。
ボルカー・ショック
スタグフレーションという言葉が生まれたのは1970年代初めのことで、それまでは存在しなかった。それには理由がある。
戦後、大きな影響力を誇ったケインズ経済学の理論によれば、不況とインフレは両立しないトレードオフの関係にあり、同時に起こるはずはなかったからだ。政策当局は不況(および不況による失業)から脱するには財政・金融政策でインフレを起こせばよく、不況になればインフレは収まる。もし不況とインフレが同時に起これば、理論が大きく覆されるだけでなく、政策当局はどうしたらいいか、途方に暮れることになる。
その途方に暮れるような事態が実際に起こったのは、1970年代に入る頃からだ。その後、2度の石油危機で物価高が加速する。米国内ではガソリン不足で給油所に長い列ができ、配給制が敷かれ、ニュースで大々的に取り上げられた。結局、スタグフレーションは80年代初めまで、およそ10年間続くことになる。

ボルカー元FRB議長(Wikipedia)
米国がスタグフレーションから脱するうえでは、経済政策の転換が重要な役割を果たした。米連邦準備理事会(FRB)のポール・ボルカー議長(当時)による徹底した金融引き締め政策である。
ボルカー議長は1979年に就任すると、金融政策の操作対象を短期金利から資金量に切り替え、市中に出回るお金を絞って、10%を超えていた物価上昇を抑え込もうとした。短期金利は20%にはね上がった。
物価高は終息に向かったものの、急激な金融引き締めは、米経済・金融市場に一時、深刻な副作用を引き起こす。厳しい景気後退を招き、株式相場は大幅安となった。「ボルカー・ショック」と呼ばれる。
FRBは世間の非難の的となった。ワシントンの本部ビルを農場主たちのトラクターが取り囲み、廃業を余儀なくされた住宅建設業者たちがツーバイフォーの建材を切断し、「金利を下げよ」などとメッセージを書いて送りつけてきた。住民グループが抗議活動を展開し、議長に面会を要求したこともあった。ボルカー氏は執務室で面会し、インフレを封じ込める必要性を説いたという。
ボルカー氏は回顧録で、「ほかに有効な選択肢がなかったため、最終的に強力な金融政策によってインフレの炎を消し止めた。景気への甚大な影響は避けられなかった」と振り返っている。
すきあらばバラマキ
さて、日本が近い将来、スタグフレーションに陥ったなら、ボルカー氏のように大胆な政策転換に踏み切れるだろうか。
同じ中央銀行トップである植田和男日銀総裁は昨年、長年続いたマイナス金利を解除した。政策転換にかじを切る「資質」はある。ボルカー議長によるスタグフレーション克服の手法も当然熟知しているだろう。激しい抗議にもたじろがなかったボルカー氏のような胆力があるかどうかは未知数だが、少なくとも何をすべきかは十分承知しているはずだ。
問題は、植田氏を取り巻く政治環境だ。ボルカー氏をFRB議長に指名したジミー・カーター米大統領は皮肉にも、ボルカー氏の金融政策が一因となり、1980年の大統領選でロナルド・レーガン氏に敗れたといわれる。それでもカーター大統領が任期中、FRBの金融引き締めに懸念を表明したのは一度きりだったという。
与党から現金給付圧力強まる 米関税を口実にhttps://t.co/t17bqxje3J
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) April 10, 2025
今の日本の政府・与党に、そのように腹のすわった、インフレ退治への協力が期待できるとはとても思えない。それどころか、すきあらばインフレをあおるようなバラマキばかりしている。政府は電気・ガス料金への補助を繰り返しているし、与党は米国による関税引き上げを口実に、経済対策として現金給付を求める声を強めている。夏の参院選に向け、なりふり構わぬとはこのことだ。
野党も負けてはいない。日本維新の会や国民民主党などは消費税の減税を求めている。減税は個人の財産権の尊重であり、補助金や現金給付のような単純なバラマキとは違う。けれども野党は、減税の財源として社会保障費などに切り込むつもりはなく、赤字国債を発行し、それを日銀に実質買い取らせる考えだ。結局、形を変えたバラマキであり、インフレで国民をさらに苦しめることになる。
その国民自身、インフレがなぜ起こるのか、インフレを止めるためにはどうすればいいのかを理解している人は、少ない。国民の多くは、無邪気に補助金や給付金を喜び、さらなるインフレを招こうが、目に見える税金さえ当面安くなればそれでいいと浅はかにも信じている。これでは政治家になめられ、バラマキに走られても仕方ない。
発展か衰退か
スタグフレーションはたとえるなら、インフレと不況という2つの頭をもつ怪物のようなものだ。頭が1つだけでも手強いのに、双頭となれば、政府、中央銀行、国民が心を合わせ、正しい知識と戦法で立ち向かわなければ、とても太刀打ちできない。
米国はスタグフレーションを退治するのに10年かかった。けれども、それによって1980年代以降、経済が再び発展に向かう素地を整えた。日本はこれまで染みついたインフレ頼みのだらしない姿勢を根本から改めない限り、スタグフレーションという禍(わざわい)を転じて福となすことはできず、南米型の慢性インフレの中で衰退に向かうしかないだろう。