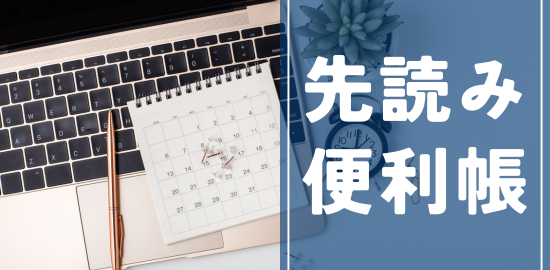8月25日、東証と経済産業省は「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2020」を選定、公表した。
■DX銘柄2020のパフォーマンス
企業価値の向上につながるデジタルトランスフォーメーション(DX )を推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を「DX銘柄」として35社を選定した。選定基準としては①アンケート調査回答・ROEのスコアが一定基準以上であること②評価委員会による取組評価が一定基準以上であること③重大な法令違反等がないこと、としている。従来、「攻めのIT経営銘柄」として選定・公表していたが、今年からDX銘柄と変わった事が示すように、足元でDXが用語として浸透しつつあり、期待が高まっている。
DX2020銘柄の昨年末比のパフォーマンスを比較した。
採用銘柄の昨年末比の平均リターンは日経平均株価と同水準であった。ただ、それぞれの企業の属する東証業種別株価指数との比較では、35銘柄中20銘柄が業種別指数のリターンを上回るという結果となった。
■DXの定義
総務省はDXに関して、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義している。しばしば混同されるが単なるデジタイズ(IT化)とDXは明確な違いがある。
単なるデジタイズは既存のアナログ技術をデジタルに置き換えただけのもので例えば会議であれば、会議室の予約をスマホやPCで行ったり、音声データをスマホで録音したりすることを指す。これがDXになると 先ほどの会議では、録音された音声を人工知能(AI)が解析して話者を特定し議事録が自動的に作成されるようになる。さらに会議で決定した内容をもとに業務上の指示や工程管理をAIが自動的に作成し、提案を行うようになると考えられる。
■DXが進まない背景
しかし日本においてDXによる企業の競争力向上はなかなか進んでいないのが実情だ。スイスのIMD(国際経営開発研究所)が毎年発表している世界各国の競争力ランキングで日本は34位と前年の30位からさらにランクダウンした。ちなみに1位はシンガポール、2位はデンマークとなっている。5位の香港、11位の台湾、20位の中国と比べてもアジア圏の中でも見劣りする結果となっている。
日本でDXがなかなか進まない背景についてよく指摘される理由には、以下のようなものがある。1つには、掛け声としてのDXは増えているが、デジタル化が目的化してしまっていることがある。また、企業の経営層に本当の意味でITに詳しい人材がおらず、システム部門に丸投げする形となり、必要な資源や権限が足りないという意見も多い。
その他にも企業が自前の仕様で構築し、アップデートを続けてきたいわゆるレガシーシステムが足かせになり、システムの保守管理に人員や予算を取られてしまい、攻めのDXまで手が回らないといった構造も背景の一つだろう。
■コロナ後にDXは進むか
こうした背景の中、コロナ後に広がりつつある社会のリモート化を契機に 、DXが加速するとの見方が多い。UBS証券の8月26日付の「Japan Economic Perspectives~日本企業・経済はコロナ危機を契機に生産性を引き 上げられるか?」と題したリポートでは、「日本の先行きの生産性上昇とそのための改革に対して楽観的になるのは難しい」としつつ、コロナ危機により①リモート化・オンライン化②行政手続きの効率化③地域分散の変化によって、経済・社会のデジタル化の促進が加速すると述べている。
また、SaaS(ソフトウエア・アズ・ア・サービス)の導入の広がりも追い風となる。日本の大企業は中小企業よりもSaaSの導入が遅れてきた。しかしアフターコロナ、ウィズコロナの世界ではテレワークの広がりや仕事のデジタル化、コストの見直しなどの動きがSaaSの導入を後押ししている。
今後はさらにDX化の進んだ企業とそうでない企業の差が広がると予想され、株主からの圧力や競争環境などの市場メカニズムがDXの促進をサポートするとみられる。日本株の出遅れの是正には、企業の低生産性の改善が不可欠であることから引き続きDXを取り巻く動きに注視したい。(QUICK Market Eyes 阿部哲太郎)
<金融用語>
ROEとは
Return On Equityの略称で和訳は自己資本利益率。企業の自己資本(株主資本)に対する当期純利益の割合。 計算式はROE=当期純利益÷自己資本またはROE=EPS(一株当たり利益)÷BPS(一株当たり純資産)。 米国では株主構成に機関投資家が増加し、これらの投資家が「投下した資本に対し、企業がどれだけの利潤を上げられるのか」という点を重視したことも背景となって、最も重要視される財務指標となった。 企業は、株主資本(自己資本)と他人資本(負債)を投下して事業を行い、そこから得られた収益の中から、他人資本には利子を支払い、税金を差し引いて最後に残った税引利益が株主に帰属する。したがって、自己資本利益率は、株主の持分に対する投資収益率を表すことになる。 そのため、経営者が株主に対して果たすべき責務を表した指標と見ることができる。また、それは株主に帰属する配当可能利益の源泉となるものであり、配当能力を測定する指標として使われる。自己資本収益率は株式の投資尺度としても重要である。