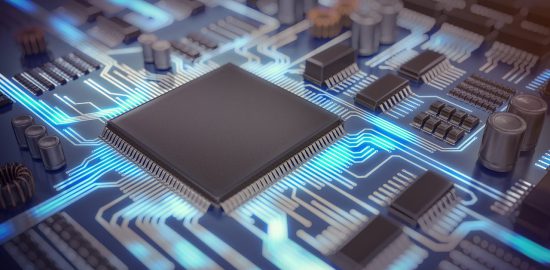【日経QUICKニュース(NQN) 尾崎也弥】ヤクルト本社(2267)株の出遅れ感が鮮明だ。24日は日経平均株価が歴史的な水準に上昇し、他の飲料大手株がそろって年初来高値を更新するなか、ヤクルト株は小動き。4月に付けた年初来高値からなお3割も低い水準だ。さえない株価には中国市場のある「異変」が関係しているという指摘がある。
■牛乳に飲まれる中国事業
ヤクルト株は朝方に2%高となったが、その後失速し、前週末の終値近辺で推移。人気アニメ「鬼滅の刃」とコラボした缶コーヒーが好調なダイドーグループホールディングス(2590)と、野菜飲料の需要が伸びているカゴメ(2811)はそれぞれ年初来高値を更新しており、ヤクルト株の元気のなさが目立つ。
背景にあるのが中国市場の変化。ヤクルトにとって中国は日本に次ぐ巨大市場。1日平均で700万本程度を売り上げる。その中国ではヤクルトの1日平均の乳製品の売上本数が1~6月期に前年同期比3%減、1~9月期の販売実績(速報値)ベースでも5.3%減となっている。1~3月期は1%増と売り上げは安定していたが、4月以降は苦戦しているようだ。
中国政府が5月ごろから、免疫力強化のために牛乳を積極的に飲むよう国民に奨励した面が大きい。「中国はコロナの感染拡大が落ち着いてきたとはいえ、国民の健康意識は高い。政府の奨励をきっかけに牛乳ブームが起きているようだ」と、浜銀総合研究所の白鳳翔主任研究員は話す。最近ではお土産としてお酒やたばこの代わりに牛乳を選ぶ傾向もあり、「ヤクルトの代替品」として牛乳需要が拡大しているという。中国の牛乳生産大手、蒙牛乳業の株価は春以降、上昇基調をたどり、11月に上場来高値を記録した。
※ヤクルト株(緑)の出遅れ感が強まるばかり。赤は日経平均株価、黄は蒙牛乳業
かたやヤクルトの株価は低空飛行で2021年3月期の業績予想をみても、純利益は前期比1%増の400億円と最高益を見込む一方、売上高は4%減とさえない。
■開拓余地あり
ただ、「ヤクルトは中国での知名度やブランド力が高く、人口対比で考えても中長期的な伸びしろは大きい」とも、浜銀総研の白氏はみている。ヤクルトの資料によると、中国の約14億人のうち販売対象となる人口は約半分の7億7000万人。この対象人口に対する1日あたり販売本数は約1%にとどまっている。市場を開拓する余地はまだまだ大きい。
※ヤクルトの業績推移
香港でも駅の売店などにはヤクルトが並び、朝の通勤時に「パック買い」する人の姿を目にすることもある。シンガポールやインドネシアも比較的、ヤクルトは身近な存在だ。中国では「牛乳ブーム」が一巡した後の需要の戻りに期待がかかる。日本国内でも健康意識の高まりは共通で、高付加価値商品「ヤクルト1000」などの伸びにつながっている。
今シーズンの観客制限の影響を大きく受けたプロ野球事業では国内フリーエージェント(FA)権を取得した山田哲人選手と石山泰稚投手がFA権を行使せず残留するなど、明るい話題もある。仏食品大手のダノンとの資本関係の解消で経営の自由度が増すともいわれる。中国市場の回復機運が高まれば、株価の見直しにつながりそうだ。