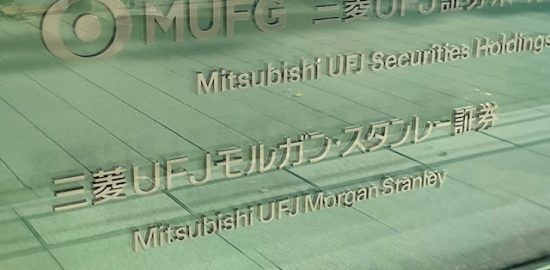無知の知:パウエル議長は「自分が『知らない』ということを知っている」と言う
今月中旬に米連邦公開市場委員会(FOMC)が開かれ、0.5%の利上げが決定されました。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は、FOMC後の記者会見で、重要なことをいくつも述べています。そのうちのいくつかを、発言の順番に拾ってみます。
「インフレが持続的な低下方向にあることに自信を持つためにはさらにかなり多くの証拠が必要である」(⇒インフレがどうなるかはまだわからない)
「確かに、家計や企業、エコノミストなどによる長期の予想インフレは落ち着いている。しかし、それは自己満足に浸る根拠にはならない。高いインフレとの戦いが長く続けば、高いインフレ期待が長く続く可能性も大きくなる」(⇒インフレを甘く見てはいけない)
「いうまでもなく、我々の(四半期)見通しは委員会の意見でも行動計画でもない。経済が今から1年先にどうなっているかについて、確信を持ってわかる者などいない」(⇒人間の予想などあてにはならない)
「経済見通しではふたたび、圧倒的多数のFOMC参加者がインフレリスクは上向きと見ていることが示されている。したがって、私は確信を持って『次回の経済見通しではターミナルレートが引き上げられることはない』などと言うことなどできない。今後、我々はどうするかはわからないし、それは、今後のデータに依存している」
「そのとき(=ターミナルレートに到達したとき)の問題は、そこ(=ターミナルレート)にどのくらい留まるかであるが、委員会の強い見方は、我々は、インフレが持続的な形で低下していることに本当に自信を持つまで、そこにいる必要があるだろうということだ。そして、それにはしばらく時間がかかると考えている」(⇒引き締めは長く続く可能性があると見ている)
「コア物価指数の55%を占める、非住宅関連のコアサービスセクターはまさに労働市場の関数といってよい部分だが、その部分が落ち着くためにはかなりの期間を要すると見られる」(⇒この部分のインフレは長く続く可能性があると見ている)
「この先、景気後退に向かうか向かわないか、あるいは、もし景気後退に向かうなら、それは深いものになるかそうでないのかは、誰にもわからないと、私は考えている。それは、まさに、知りようのないものなのである」
2023年の考え方の基本スタンス:我々も「わからない」でよい。
実に「わからない」だらけです。FRBは、おそらく世界のどの機関よりも経済や物価に関する情報を集めており、かつ優秀な経済学者を抱えていますが、そのFRBが「わからない」と言っています。
ですから、我々も「わからない」でよいのです。
FRBは昨年「インフレは一時的」と言って外し続けました。欧米の投資銀行で働くエコノミストたちは、FRBの人たちに負けず劣らず優秀ですが、彼らの多くはFRBが宗旨替えをした後も外し続けてきました。彼らの仕事は予測ですが、これまで外し続けてきた彼らの予測を信じるべき根拠があるとすれば、「「インフレは下がる」と言い続ければ、いつかは当たる」というくらいしか見当たりません。筆者を含め、誰かの予測を聞くときには「話半分」が適切でしょう。
2023年の資産運用の基本スタンス:わからないなら「両端」「逆境」に備える。
予想する人たちを信用しないならどうすればよいでしょうか。答えはシンプルで、「極端なできごとが起きたときのために備えを持っておく」ことです。
我々は何が起きたときに困るでしょうか。
インフレと景気後退です。この2つが「景気の勢いがとても強い」「景気の勢いがとても悪い」という両端の、極端な事象です。これら2つに挟まれた「真ん中」は「ふつうのできごと」と捉えられるでしょう。
言い換えれば、FRBさえも「この先のインフレや景気後退がどうなるかわからない」と言っている現在、この2つの極端な事象に耐えられるようにしておけば、これら2つの「真ん中」は、ふつうの状態であるため、対応可能です。
インフレ時には、先進国の割安株式や米国リートのパフォーマンスが相対的に良好です。
景気後退時には、(ディフェンシブと言われて販売されている)先進国の公益株式や高配当株式に比べ、米国ハイ・イールド債券のほうが下値抵抗力・ディフェンシブ性を発揮します。
日本の個人投資家の多くは、米国の成長株式やインデックスファンドを多く保有しているようですから、「真ん中」にはそれらで対応できるでしょう。
2023年もシンプルに、幅広い資産で分散投資を進められてください。
年末年始にお勧めしたい本
今年読んだ本の中でのベストは、門間一夫さんの書かれた『日本経済の見えない真実』(日経BP)です。日本経済の現状や課題の背景を考えるには、この本1冊で十分だと思います。
著者は日銀出身ですが、いわゆる「日銀理論」にも懐疑的な目を向けます。読み始めは「また、あの話か」と思われるかもしれませんが、そこを越えれば得られるものは多いと思います。
ウクライナ戦争については、(「今さら」と思われるのかもしれませんが)豊島晋作さんの『ウクライナ戦争は世界をどう変えたか』をつい2週間ほど前に読みました。(ほかにもいくつか目を通しましたが、この本は)わかりやすく、新たに得られるものも多いと感じました。参考文献に挙げられている本に興味を持たれるかもしれません。
また、ウクライナ戦争や米中対立のみならず、あらためて、国際政治学や地政学について知ってみられたい方は、『大学4年間の国際政治学が10時間でざっと学べる』(小原雅博著、KADOKAWA)あたりが便利に思えます。その途上で、世界史を学び直したくなるかもしれません。世界史の教科書である『詳説世界史B』(山川出版社)や『もういちど読む 山川世界史』(同)を読まれるのもよいかもしれません。
国防に関しては、『国難に立ち向かう新国防論』(ビジネス社)と『自衛隊最高幹部が語る台湾有事』(新潮新書)を挙げたいと思います。前者は俯瞰的な内容で、後者は個別事象に焦点を当てたものです。有事においてはどういったことが起こるのかを知ることができます。
中国について、岩波新書の『中国近現代史シリーズ』の中から興味のある時期のものを読まれるのがよいように思われます。別途、共産党の歴史について深堀りされたい方は『中国共産党、その百年』(石川禎浩著、筑摩書房)がよいと思います。
半導体市場の状況に関しては、『2030 半導体の地政学 戦略物資を支配するのは誰か』(太田泰彦著、日本経済新聞出版)がよいと思います。
働き方については、デヴィッド・グレーバーの『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』(岩波書店)が挙げられますが、なにぶん高価で分厚いので図書館で借りられるか(←私は多用しています;この本は待ちが多いかもしれません)、あるいは『ブルシット・ジョブの謎 クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか』(酒井隆史著、講談社現代新書)でもよいと思います。
それでは、みなさま、良い年をお迎えください。
(補論:読まなくても大丈夫です)防衛増税とアコード見直し
国内では、防衛増税がほぼほぼ確実となった上に、政府と日銀の物価安定目標に関する共同声明が改定されるとの報道もありました。現政権はやはり「緊縮」の方向に動いているように見えます。
増税をせずとも、当面は、最近の予算での繰り越しや特別会計の剰余金を充当することが検討できるはずです。また、現状では、予算の繰り越し(使い残し)があるために新たな予算措置も赤字国債の発行も不要にも関わらず、(さらに使い残しを増やすだけの)新たな予算を組み、(発行してもその資金が使われない)赤字国債をあえて発行した上で、政府の「負債サイド」だけに注目して「また、政府の借金が〇〇兆円増えた」という報道に接するのはなぜなのか、と疑問に思います。
加えて、日銀の2%の物価目標に触る必要はまったくありません。以前にも述べたように、先進各国では①「独立した金融政策」と②「資本移動の自由」が得られている現状において、各国が2%の物価目標を採用すると「為替相場の安定性」が期待されます。各国による2%のインフレ目標採用は、『国際金融のトリレンマ』を回避できる政策協調であり、経済活動がしやすくなる国際協調の枠組みです。現在の金融政策になんらかの問題があるとは思えませんが(有権者が問題を感じているようにも思えませんが)、もし、問題があるなら、その政策ツールを変更すればよいでしょう*。
ちなみに、現政権は「資産所得倍増計画」というものを出しています。これはおそらく、銀行金利が「0.001%」から「0.002%」になるということではなく、多くの家計がリスク資産への投資を進めるということでしょう。すると、今よりも多くの家計が預金を引き出して、投資信託口座などに資金を移しますが、より多くの家計が預金を引き出すと、国債には売りが出ます。このときに日本国債を買うのは誰でしょうか。『資産所得倍増計画』という政策をうたうためには、国債の引き受け手を決めておく必要があります。それは、日銀でしかありません。日銀は、いつでも家計が預金を引き出し、市中銀行が国債を売却してもよいように準備しておかなければなりません。万が一にでも、現政権が日銀や次期総裁に、金融緩和からの脱却を求めているなら、政策が互いに矛盾するように思えます。
(実は、今回のFOMCでも「2%のインフレ目標を再評価するか」という質問が出たのですが、パウエル議長は「どんな状況でもそれは考えないだろう」と全否定しています)
*(日銀は実際に、12月20日に10年金利の変動幅を拡大する変更を行いました。黒田総裁は「利上げではない」と述べましたが、もちろんそのとおりです。現在の日本経済には需給のゆるみ(スラック)があり、「引き締めるべきもの」は見当たりません。また、筆者は引き続き、2%の物価目標を取り下げる理由はないと考えています)
フィデリティ投信ではマーケット情報の収集に役立つたくさんの情報を提供しています。くわしくは、こちらのリンクからご確認ください。
https://www.fidelity.co.jp/
- 当資料は、情報提供を目的としたものであり、ファンドの推奨(有価証券の勧誘)を目的としたものではありません。
- 当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、その正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
- 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。
- 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き作成者に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。
QUICK Money Worldは金融市場の関係者が読んでいるニュースが充実。マーケット情報はもちろん、金融政策、経済を情報を幅広く掲載しています。会員登録して、プロが見ているニュースをあなたも!詳しくはこちら ⇒ 無料で受けられる会員限定特典とは