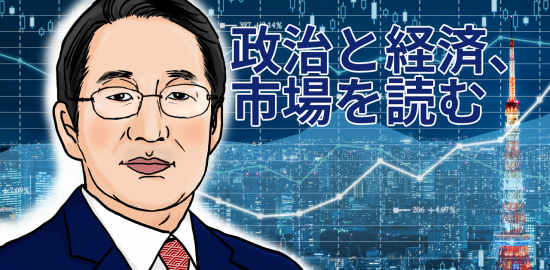高等学校の家庭科の授業で金融教育が必修になってからおよそ1年が経過し、教育現場の課題が浮き彫りになってきた。QUICKが金融教育に携わる高校教員を対象にアンケート調査を実施したところ、教員と学校側の積極性にギャップが生じていることがわかった。また、教員の金融教育に対する意欲の有無で、生徒の関心・興味に大きな差が生まれることがわかった。
金融教育に積極的な学校は4割弱にとどまる
QUICKは「高校での金融教育実態調査2022」を22年12月7〜12日に実施した。全国の中等教育学校、高等学校で公民・家庭科を担当する教員471名(公民384名、家庭96名、公民と家庭科を重複回答した9名を含む)が回答した。金融教育分野を「家計管理」「生涯の生活設計(ライフプラン)」「資産形成・運用」「金融トラブル」「金融や経済、市場の仕組み」の6テーマに分類し、授業の状況や教員が抱えている課題を聞いた。
金融経済教育を授業で取り扱うことは重要だと思うかを聞いたところ、「重要だと思っている」、または「意欲的に取り組んでいる」と答えた教員がそれぞれ全体の7割を超えた。それに対し、実際に金融教育の実施に対して積極的に取り組んでいる学校は4割弱にとどまった。

金融教育への積極性が生徒の興味・関心を左右
学校側が金融教育に積極的であるほど、教員は金融教育に意欲的であり、生徒の興味・関心も高い。勤務校が金融経済教育の実施に「積極的」だと思うと答えた教員は、その理由として「カリキュラムがある」、「教えられる人材が多い」、「外部講師を招いた授業を実施している」など、金融経済教育を実施できる体制が整っている点を挙げた。
金融経済教育の実施にあまり積極的ではない学校では、「教科の教育目標に入っていない」、「教員自身が何を教えるべきか分かっていない」などの声があがった。学校の運営方針として受験科目を優先する向きがあるほか、一部の教員は金融経済教育を受けた経験がなく、金融リテラシーを身につける機会が少ないことが課題となっている。
※調査結果の詳細資料をお求めの方は、こちらのフォームからお問合せください。
=②に続く
QUICKは現在、金融教育領域において、カードゲーム「資産形成王」と資産運用に関する講演をセットで、学校等に提供しております。資産形成・運用で好ましい授業形式である「ゲーム形式の生徒同士のグループワーク」を実現すると同時に、日本経済新聞社グループとして中立的な立場であるQUICKが、公的機関に求められている「ゲーム感覚教材」「講師派遣」を提供することにより、教員のニーズに応えられるものと考えています。ご興味・ご関心のある学校・教育関係者の方は、QUICK Money Worldのお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
<関連記事> |