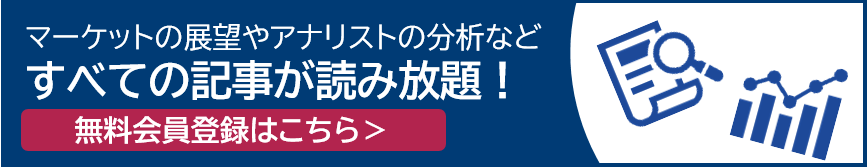日銀は金融政策決定会合を開き、イールドカーブ・コントロール(YCC)を柔軟化しました。
その背景について、筆者は、声明文で言及されたとおり、現行の「金融緩和の持続性を高める」ための措置と考えています。他方で、「正常化に向けたさらなる一歩」と強調する向きもあります。
現在、筆者がもっとも容易に想像できることは、「今後、正常化に向けた圧力は一段と強まる」ということです。「大合唱」です。
植田総裁におかれては、あくまで日本経済にとってもっとも望ましい金融政策を取っていただきたいと、筆者は願っています。
日銀が利上げしても預金金利は上がらない⇒資産運用がやはり重要
金融政策が正常化され、短期金利の引き上げが実施されれば、貯蓄する主体に恩恵があると考える方がいらっしゃるかもしれません。
はっきりと予言しておくと、「日銀が利上げを開始しても預金金利が上がることはない」でしょう。米国の実例がそれを示しています。
【次の図】に示すとおり、現在の米国の政策金利は5%を超えますが、米国の預金金利は2%程度です。

この関係に従えば、日本の政策金利がたとえば2%まで引き上げられても、預金金利はほとんど上がりません。
なぜかと言えば、銀行による有価証券投資や貸出が「大規模金融緩和の低金利時代」に実行されているために、利回りの「持ち値」が低く、政策金利にそって預金金利を引き上げると、銀行は逆ザヤになってしまうためです。
今後、「預金者は長年、低金利に苦しんできた。そろそろゼロ金利政策は止めるべき」といった言説を耳にするなら、ほかの意図に基づいてそう述べていると考えたほうがよいでしょう。
大増税時代、しかも引き締め、どちらも景気と「ふところ」を冷やします。われわれには、資産と時間の分散が効いた資産運用こそが頼りです。
米国債の格下げ:米国債にとっての頼り①:債務上限
さて、8月1日に大手格付け会社のフィッチ・レーティングス(以下、フィッチ)は、米国債の長期格付けを「トリプルA」から「ダブルAプラス」に引き下げました。
フィッチは「ガバナンスの崩壊」(Erosion of Governance)を根拠のひとつとし、その一例として「債務上限をめぐる瀬戸際のやりとり」を挙げています。
しかし、債務上限あるからこそ、議会少数派・野党がギリギリまで自分たちの主張をもとにホワイトハウスとの交渉を深め、議会多数派・与党から譲歩を引き出すことで財政赤字の拡大が緩やかになったり、「公平性」がいくぶん確保・回復された財政支出や減税が実施されたりします。
言い換えれば、合意までの「途上」で主張の対立は先鋭化してみえても、「結論」=政策自体は穏健になる・中道に寄ることが期待されます。実際、毎度そうなっています。
逆に、債務上限がなく、どちらか一方の政党に財政に関する裁量があり、結果として、フィッチが望む「ガバナンス」が取れている状態は「少数派によるけん制が効かない」ことを意味し、一部の有権者に偏った恩恵を与える財政支出や減税が実行される恐れがあります。
とくに国民の意見が二分される現下の状況において、予算や債務上限に関する「ガバナンス」が望ましいとは言い難いでしょう。「企業価値の(サステナブルな)最大化」というひとつの目標に向かう一般企業のガバナンスと、有権者が異なる目標や目的、欲求を持っている国家のガバナンスは異なるように思えます。決められない政治だからこそ、「内戦」が起きていないのかもしれません。
米国債にとっての頼り②:世界的な貯蓄意欲(Global Savings Glut)
フィッチはもうひとつの根拠として、政府債務の増加を挙げています。しかし、(世界)経済の規模と貯蓄意欲が高まれば、(米国の)政府債務は増えていくものです。これは、政府の選択というよりも、われわれの選択次第です。
われわれの口座には毎月貯蓄がいくらか残ります。預金通帳の金額をみるとき「毎月毎月自分が倹約をしてきたためだ」と思うかもしれません。
しかし、「貯蓄が生じる」ということは、「生産したもの(=所得)のすべてを自分では消費しなかったという事実」と、「残りを誰かが消費してくれたという事実」の両方が成立している場合のみです。後者が成立しないと、生産額=所得は減り、貯蓄はできません(→それでも、少なくなった所得からさらに貯蓄しようと思えば可能ですが、経済が収縮し、デフレスパイラルに陥っていくことが予見できます)。
「残りを消費している」のは、現在の世界ではおもに政府です。このとき、家計は政府に対して国債という債権を持ちますが、その債権の支払い・返済はわれわれ自身の税金(やインフレ)によってのみ可能となります。言い換えれば、「親の所得の一部を子供が消費するのですが、そのときに子供に借用書を書いてもらっている状況であり、それこそが親にとっての貯蓄」です(→「貯蓄がよいことである」とか、「政府債務が問題である」とかいうことは、しっかりと考えられるべきことでもあり、主観的なことでもあり、仮想的なことでもあるかもしれません)。
話を戻すと、もし、政府による国債の発行や(われわれの代わりに行う)政府消費を拒否するなら、われわれは生産の全量を消費することになり、もちろん消費金額は増えますが、貯蓄は不可能になります。
逆に言えば、われわれが「今後とも貯蓄を増やしたい」と願うならば、政府の国債は増えていきます。そして、このこと(貯蓄)は世界規模で起きていて、米国以外のわれわれが貯蓄できるために消費をしているのは米国政府(および米国の企業や家計)です。
言い換えれば、米国以外の世界にいるわれわれが「今後とも貯蓄や貿易黒字、準備通貨を得たい」と願うならば、米国債は増えていく=米国債を買うはずです。政府債務の残高や増加ペースは、貯蓄の欲求とその強弱を示すものです。現在の米国債の利回り水準をみれば、貯蓄意欲は旺盛に思えます。
では、足元と今後の米国債を支えるものは、なにでしょうか。
米国債にとっての頼り③:実質金利の高さ
現下では、【次の図】に示すとおり、主要国の中では米国の実質金利のみがプラスであり、他の主要国ではマイナスであることも、米国債やドルへの投資を促していると思われます。

米国は、(世界的な財や労働の供給不足に加えて)パンデミック後の巨額の金融緩和と財政出動で大幅なインフレを起こしました。たしかに、それは「失策」だったかもしれませんが、その後の(実質金利がマイナスの状態を続けるという)「財政従属」の誘惑にも負けることなく、実質金利をプラスにまで一気に引き上げました。それこそが、米国の経済成長や政府債務に対するFRBの自信の表れでしょう。また、投資家にとっては、単に「米国は実質金利が高い」ということのみならず、米国に対する信頼感を回復させるものとなったでしょう。
米国債にとっての頼り④:米中対立
最後に、米中対立も、ドルや米国債への資金フローを「長持ち」させる可能性があるでしょう。
国際政治におけるリベラリズムの「カントの三角形」は、民主主義であること、経済の相互依存が強まること、国際機関を設立しこれに加わることで、戦争は防がれると考えます。
これと同様に、米国のリベラル派はとくに1980年代以降、中国との経済依存を深めることで(=関与政策)、中国がやがては(自由貿易や資本移動の自由、財産権の保護などの)資本主義と親和性の高い民主主義体制に移行することで、中国を米国の側に取り込み、ロシアを「封じ込める」ことを企図していたかもしれません。
他方で、(国際政治はアナーキー・無政府状態であり、常にパワーが対立していると考える)リアリズムの観点からは、上記のリベラリズムの考えに基づいて自由貿易が拡大していけば、世界経済や貿易に占める中国の規模が大きくなり、貿易による富の増大は中国の国際政治的・軍事的な地位を高めることで、準備通貨がドルから人民元に徐々に移行し、準備通貨としてのドルの地位が落ちていくことが予見されました。そして、実際に、中国は米国の地位を脅かすほどに台頭しました。
現在の米国は(表面的には)いくぶんリアリズムに転じているようにみえ、中国の台頭を「封じ込め」ようとしているようにみえます。米国以外の西側諸国にとってみると、米国の軍事支出をファンディングし、中国への軍事転用可能な技術や製品の提供を抑制することによって、安全保障を保とうとしている状況でしょう。逆に、中国の側も資本主義(≒改革開放)から社会主義(≒共同富裕)への回帰を指向しているようにみえます。
中国の経済的・軍事的なプレゼンスの拡大が内外から抑制されることで、米国やドルの地位が保たれる可能性があります。
フィデリティ投信ではマーケット情報の収集に役立つたくさんの情報を提供しています。くわしくは、こちらのリンクからご確認ください。
https://www.fidelity.co.jp/
当資料は、情報提供を目的としたものであり、ファンドの推奨(有価証券の勧誘)を目的としたものではありません。
当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、その正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。
当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き作成者に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。
QUICK Money Worldは金融市場の関係者が読んでいるニュースが充実。マーケット情報はもちろん、金融政策、経済情報を幅広く掲載しています。会員登録して、プロが見ているニュースをあなたも!詳しくはこちら ⇒ 無料で受けられる会員限定特典とは