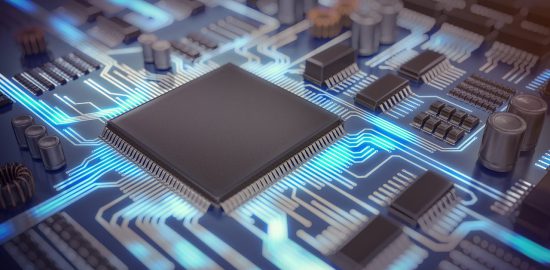※この記事はフィデリティ投信のWebサイトで4月8日に公開されたコラムの転載です
【今週のベスト・ベッセント語録】:「関税がそんなにひどいのなら、なぜ、世界には今日も関税が存在しているのでしょうか。なぜ、彼らは他国の製品に関税を課しているのですか。あるいは、米国の消費者が全ての関税を負担するなら、なぜ彼らは関税を気にするのでしょうか。そうです。彼らは関税を負担するつもりだから(トランプ政権を非難するの)です。」
ベッセント財務長官が米国市民に伝える大切なこと(前編:後編は付録③に)
本稿のためにもみなさんのためにもとても重要なベッセント語録を付します。
【1982年と現在との対比】「1980年にロナルド・レーガンが大統領に当選したとき、私は大学の新入生であり、米国では新しい日々を迎えつつありました。いま、人々と話すと、彼らはレーガン政権の時代をとても懐かしく見つめます。(レーガンが大統領に就任した前後には、米国経済には)大きな曲折がありました。しかし、レーガン大統領は決して揺らぎませんでした。(中略)80年代初頭のあるとき、1人の農民が連邦準備制度理事会(FRB)にショットガンを持って現れました。(インフレを退治するために大規模な引き締めを行い)金利を引き上げたポール・ボルカー議長を(憎み、彼を)撃とうとしたのです。(中略)当時は(それほど米国民にとっても、レーガン政権にとっても)厳しい時期でした。しかし1984年の大統領選挙ではレーガン大統領は49州で勝利したのです。」(⇒【訳注】いま行っている政策は、1982年当時のボルカー議長による強烈な引き締めのように、米国市民には苦しみを強いることかもしれないが、われわれはそれが米国の一般市民を債務のワナから救い出すために必要だと思っている。米国の有権者が1982年には高い金利と失業率に苦しみながらも1984年にレーガン大統領を圧倒的に支持・再選させたように、今回もそうした結果に米国の一般市民を導きたいと思っている)
【格差について】「米国人の上位10%は、株式市場の88%を所有しています。次の40%は、株式市場の12%を所有しています。下位50%は借金があります。クレジットカードの請求書があります。彼らは家を借ります。彼らは自動車ローンを持っています。われわれは彼らにいくらかの安心感を与えなければなりません。」
【格差について】「2024年の夏、歴史上最も多くの米国人が欧州での休暇を取りました。同じ2024年の夏、歴史上かつてないほど多くの米国人がフードバンク(企業や家庭から寄贈された食品を、必要としている人や団体に無償で提供する活動)を利用しました。私は故郷の近くにある2つのフードバンクに行って、話を聞きました。フードバンクの主催者たちは、多くの人にとってフードバンクに入ることは尊厳を失うことだと言いました。もちろんです。彼らは新しい事態に直面していました。その事態とは、フードバンクの典型的な利用者である家を失った人々や通りに出ている人々でもなく、食料品店で働いて100ドルを稼ぎ、しかしそれだけでは必要な食料品を買うことができなくなった働く家族がフードバンクを利用している、ということでした。彼らは5つ、6つ、7つの必要な食料品を買えず、それらを補充するためにフードバンクに来ていました。それは素晴らしい米国ではありません。かたや欧州で休暇を過ごしている人がいて、かたやフードバンクを利用している(それがいまの米国です)。」
トランプ氏は保護主義か。
相互関税(reciprocal tariffs)」は、言い換えれば「報復関税」です。
すなわち、トランプ氏は「あなたたちが、あなたたちの関税や非関税障壁を通じて不公正な貿易をしてきたから(→トランプ氏の考え)、この不公正な貿易を公正にするために、あなたたちにこの相互関税を課します」とおっしゃっています。
トランプ氏の考え方によれば、米国の相互関税そのものが、貿易を公正にするための「報復」ですから、他国がこれに対して報復をすれば、再び不公正になってしまいますので、米国は追加の「相互関税」を課す(と考える)のが合理的に思えます。
すなわち、カナダや独仏、中国が検討したり、実施したりしている報復措置は真逆の対応であり、むしろ米国以外の国々は、関税や非関税障壁を取り除いたほうがよいのかもしれません。
その結果、世界で実現するものは何でしょうか。
保護主義とは真逆の自由貿易です。
誰も、相互関税の真のメッセージを理解していない①
トランプ氏の相互関税のメッセージは次のようなものです。すなわち、
- 「相互関税を課すことで米国ではあなたたちの国のモノが高くなるよね。それは覚悟しているんだ。そうなれば、これまでほど、あなたたちのモノを買えなくなるよね。つまり、米国はもうこれ以上、あなたたちから借り入れをしてまで、あなたたちの国のものは買わないということなんだ。もう、過去50年にわたる借金生活は止めにしたいんだ。」
- 「これ以上、借り入れはできないから、もしも米国にモノを売りたいなら、米国のモノを買ってくれよ。だったら、米国はあなたたちのモノを買うことができるからさ。」
といったものです。重要な点を補足しておくと、後者のケースでも、米国は借り入れに依存する必要がないので、米国の借り入れは減少します。
これと同じメッセージは、本欄でこれまで数回にわたり議論してきたマールアラーゴ合意が目指す「ドル安」からも伝えられています。すなわち、
- 「ドル安になれば、米国にとってはあなたたちの国のモノが高くなるよね。そうなれば、これまでほど、あなたたちのモノを買えなくなる。いままでの借金漬けの生活は止めにしたいんだ。」
といった感じです。
ここが重要ですが、言い換えると次のようになります。すなわち、
- 「あなたたちは、これまで米国に借金させることで、自分たちのモノを買わせてきたよね。われわれはただ、関税やドル安によって、いままでの借金生活を止めようとしているだけだよ。言い換えれば、これは『自分たち米国自身への緊縮宣言』なんだ。自分たちの生活のことだから、あなたたちがとやかく言うことではないよね。確認だけど、もしあなたたちが米国のモノを買ってくれるなら、われわれにも元手が入るから、それであなたたちのモノを買えるからね。じゃあまたね」
といったふうです。
誰も、相互関税の真のメッセージを理解していない②
米国経済は、1971年に第2次世界大戦終戦以降、初めて、貿易収支の赤字を計上します(→貿易・サービス収支でも同年)。そして、同年にはニクソン・ショック(ドルの切り下げ、輸入課徴金、価格政策)を行います。その後、1973年と75年は小幅な黒字に転じますが、それ以降、これまでは継続して貿易収支の赤字を計上しています。
米国の貿易赤字が意味するところは、「世界経済は、米国の借り入れによる消費で成り立ってきた」ということです。
ごく簡単に言えば、第2次大戦後の世界経済は、
- 米国以外の国々が104を生産して、100を消費し、残った4は米国に消費させる(=米国に輸出する)。反対側の米国は100を生産して、米国以外の国々から4を輸入し、104を消費する、
- ところが、米国の所得は生産と等価の100なので、米国には、米国以外の国々から4を買うお金はない、
- そこで、米国以外の国々は、米国に4を「掛け売り」する。すなわち、米国以外の国々は米国に4を売るにあたり、お金は受け取らず(→なぜなら米国に4を買うお金はないので)、そのかわりに米国に金額4だけの借用書を書かせる、
というかたちで成り立ってきました。
その米国が「もう借りませんよ」、実際には「借り入れは減らしますよ」と言っています。
すなわち、
- 世界最大の債務市場である米国が借り入れを減らす、
- 特に米国政府は財政赤字を削減しようとしている、
ことの帰結は、
- 米国の借り入れに依存した世界経済の規模縮小
です。よって、もし、トランプ氏がこれを貫徹するなら、
- 株価は大きく下落する、
- 米国債の利回りは低下する、
ことになります。
「トランプ・ショック」は(もし、トランプ氏がこれを貫徹するなら)、「米国に貸し付けて消費をさせる」という第2次世界大戦以降の世界経済の構造の「天と地をひっくり返す」ような一大変革です。
トランプ・ショック>リーマン・ショック+ニクソン・ショック
おそらく、最近の株式市場の下落と国債利回りの低下は、
- 「トランプ政権がめちゃくちゃなことをしようとしている。将来が不安。将来がわからない。だから、株式を売って、債券を買おう」、
といった「パニック売り」でしょう。
しかし、
- 世界経済史上、最大規模のクレジット・サイクル(与信サイクル)が終焉する、
と考えれば、「まっとうな説明」ができます。
多くの人は、相互関税や(マールアラーゴ合意の)ドル安が発するメッセージに気付いていないように見えます。
しかし、もしトランプ氏がこれを貫徹するなら、これは、第2次大戦後初めてのことであり、
- 巨大クレジット・サイクル(与信サイクル)の終焉たるリーマン・ショック、
- 米国による経済のレジーム・チェンジとしてのニクソン・ショック、
を合わせたものを上回ると言ってよいのではないでしょうか。
(もちろん、決して、これからリーマン・ショックが起きると言っているわけではありません。これについては次節に書きます。)
他国が米国に仕掛けてきた「追い貸し」という経済戦争の形勢を一気に逆転させるもの、という意味では
上記が「煽りすぎ」というなら、(冒頭に挙げたベッセント財務長官の発言に沿えば)少なくとも「痛みに耐える」緊縮策という点では、
- 「第2のボルカー・ショック」
と名付けてよいでしょう。
トランプ・ショックとリーマン・ショックなどの信用危機との違い
信用危機は通常、「借り手が返せなくなるのではないか、と貸し手が不安になる」ときに生じます。これについては例を挙げなくともよいでしょう。
他方のトランプ・ショックはこれとは異なり、「借り手が借りられなくなる前に、もう借りません」と訴えた状況です。
ですから、信用の根源である米国債が売られる状況(=信用収縮)は生じていません。いま起きているのは信用危機ではありません。
むしろ、米国は関税の引き上げや、ウクライナ戦争の停戦・政府効率化省(DOGE)による歳出削減などで、新たな借り入れをできるかぎり減らし、米国債の信用を高めようとしています。
(次節に挙げるベッセント財務長官の発言どおり)放っておけば、このスーパー・クレジット・サイクルはひどい形で終焉したかもしれません。
「スーパー・クレジット・サイクル終焉の前に借り手自身が降りた」ということ自体は英断です。しかし、もしかしたらこの英断こそが、トランプ氏の「第2次世界大戦終戦後以降の変革」を阻むかもしれません。
2つ問題があるでしょう。
-
- ひとつはもちろん、トランプ氏が「トランプ・ショック」を貫徹できるか、です。
- もうひとつは、「トランプ・ショック」というプランが抱える困難です。
後者について、マールアラーゴ合意が重要になる点を含め、次回に書きたいと思います。
(付録①)関税とその報復の一般論
関税とその報復による経済への影響は次のように整理されます。
- 【米国による他国製品への関税賦課】米国ではインフレ、輸入企業の売上・利益の減少、国内製造業の生産と雇用の増加が生じます。他国では、米国への輸出が減少するため、輸出企業の生産・雇用・売上・利益の減少が生じます。
- 【他国による米国製品への報復関税賦課】上記と同じことが、互いに反対サイドに生じます。
- ただし、現在、すでに米国は完全雇用に近く、不法移民の退去で労働力が減少する可能性もあり、他国企業による米国への生産移転には数年単位の時間を要するため、米国が生産を拡大できる余地は限られます。
- 【まとめ】関税と報復は、世界経済にスタグフレーションの圧力をもたらします。株価は大きな調整圧力を受けることになります。
(付録②)どうすれば、株価下落は終わるのか。
下落相場は「戻り」を伴いつつ、下落が続いていきます。小さなきっかけで株価が戻りかけると、「少し戻ったら売ろう」「一度ここで売っておこう」と思った人が優勢になり、株価は再び下落します。そうすると、次の戻りでは「今度こそ少し戻ったら売ろう」「一度売っておいたほうがよさそうだな」と思う人が優勢になり、株価は再び下落します。
株価下落が終わる条件として、一般的には、次の3つが挙げられます。
-
- 【株価下落の原因であるイベントそのものが終わる】 最近で言えば、2022年の弱気相場はインフレが契機でしたが、高インフレがピークを付けた2022年10月あたりが、株価の底になっています。2012年は欧州債務危機が深化していましたが、ドラギECB総裁の「なんでもする」という政策対応の姿勢(と政策の中身)で危機が収束しました。今回で言えば、トランプ氏が「相互関税」を早晩、取り下げることがそれに当たります。もうひとつ、他国による関税や非関税障壁の撤廃も考えられますが、それには数ヵ月を要するため、間に合わない恐れがあると筆者は感じます。
- 【FRBが金融緩和を行う。引き締めを止める】2020年のパンデミック、2018年のクリスマスまでの下落、2009年3月にかけてのリーマン・ショック、1998年のLTCM危機、1987年のブラックマンデー、1974年と1970年のニフティ・フィフティ相場の調整局面では、利下げが始まるか、十分な利下げが起きるか、あるいは引き締めが終わることが株価を反転上昇させています。今回FRBは早晩大幅な利下げを行うかどうかがもうひとつのポイントです。(もしも株価の下落を止めたい場合には)筆者は5月のFOMCよりも先に利下げすべきだと思いますし、0.75%や1%の利下げでは足りないと感じます。往々にして「利下げの余地があるうちはマーケットは納得せず、さらなる利下げを求めるため」です。ただし1974年がそうですが、いま利下げをしてしまうと、さらに高いインフレを招くリスクがあります。「利下げは効果ない」という主張も理解できます。スタグフレーションの1970年や1974年を含め、金融緩和が一端の反発につながっていますので、そうしたデータに沿ってお伝えさせていただきました。
- 【これ以上、下がらないところまで下げる=自立反発】 2002年のITバブル崩壊後がそうかもしれません。利下げがなかなかワークせずとも、株価が50%ほど下落すれば、自立的に戻ってくることがあります。当然、そこまでは待っていられないと思います。
まとめれば、今後は、トランプ氏が相互関税を取り下げるか、FRBが大幅な利下げするかどちらかが必要だと筆者は感じています。
(付録③)ベッセント財務長官が米国市民に伝える大切なこと(後編)
ベッセント語録の後半です。今後、ほかの発言も拾っていきたいと思います。
【相互関税について】「トランプ大統領はもう40年間も、このこと(=貿易不均衡の関税による是正)について話してきました。これは米国経済、米国の労働者、そして共和党支持者たちとの新たな連携にとって革新的なものです。」
【グローバル化と格差について】「(中国が米国への輸出を拡大させた)チャイナショック以来、少なくとも過去20年間、あるいは過去30年間にわれわれが見てきたのは大規模な所得や資産配分の問題です。すなわち、米国の西海岸や東海岸の人たちはグローバル化の恩恵を大いに得ました。他方で、米国の真ん中の地域に住む人たちは生活の質や平均余命が下がり、自分たちの子供たちが自分たちよりもうまくいくとは思っていません。(グローバル化の恩恵を得た)多くの人々はこのことを気にしていません。しかし、トランプ大統領と政権のメンバーはこれを重要な課題だと思っています。」
【グローバル化と格差について】「安価な財へのアクセスは、アメリカン・ドリームの本質ではありません。アメリカン・ドリームは、どの市民も繁栄、上昇志向、経済的安定を達成できるという概念に根ざしています。国際貿易システムの設計者はあまりにも長い間、このことを見失ってきました。」(⇒【訳注】中国から安価な財を買えるようになったことで、一般市民の生活は本当に楽になったのでしょうか。中国の企業や米国の一部企業がグローバリゼーションで利益を得た分、一般市民は代償を払ってきたのではないでしょうか)
【グローバル化と格差について】「アメリカン・ドリームは、いかに薄い薄型テレビを持てるかではありません。いま米国の家計が自分の家を持てない現実に照らせば、彼らの子供世代の暮らし向きが親世代の暮らし向きよりもよくなるとは想像しがたいでしょう。アメリカン・ドリームは中国製の安物を買えることではありません。アメリカン・ドリームはそんなことよりももっと大きなものです。われわれの焦点は購買力です。住宅であり、自動車であり、実質賃金の上昇です。」
【トランプ政権の政策について】「われわれは、高度に金融化された経済を、再び工業化された経済にするつもりです。(中略)再分配とは言いたくないのですが、(トランプ政権の一連の政策は)働く米国の人たちに実質賃金の上昇をもたらし、彼らの生活を向上させるためのものです。ウォール・ストリート(米国の金融業界)は成功しました。その繁栄はまだ続くと思います。しかし、今度はメイン・ストリート(米国の実業界)の番です。それこそが昨日われわれが見たこと(=相互関税)です。」
【トランプ政権の政策について】「一方では、大統領は世界の貿易を再構築しています。他方では、連邦政府の過剰な労働力を削減し、連邦政府の借り入れを減らしています。そして、新しい製造業に必要な労働力を確保し、民間部門を再び活用するつもりです。(中略)これは連邦政府を適正化し、民間部門を再び解き放つ機会です。なぜなら、民間部門は過剰な規制によって締め出され、政府によって締め出されてきたからです。」
【米国債の危機について】「(財務長官を引き受ける前)私は申し分のない暮らしを送っていました。しかし、高水準の政府支出が高水準の政府債務につながることで金融危機が差し迫っていることを心配していましたし、そのことを人々に伝えたいと思っていました。」
【米国債の危機について】「古いシステムが機能していませんでした。機能していないシステムを見たら、それを変える勇気を持たなければなりません。では、何がうまくいかなかったのでしょうか。私が財務長官になって、さらに多額の米国債を発行し続けていたとすれば、それは私にとって楽しいことだったのでしょうか(そんなことはありません)。それは、まるでボディビルダーがステロイドを飲んでいるようなものです。外見は素晴らしく、筋肉質ですが、内面では重要な臓器を殺している、それが米国で起きていることです。たしかに(借り入れをさらに増やし続ければ)経済は刺激を受け続け、多額の借金をし、多くの政府の雇用を創出することは容易だったでしょう。こうしたことにはいままで誰も異論を唱えませんでした。しかし、あなたは災難に見舞われることになっていました(≒これを放っていれば、米国債の暴落という金融危機が米国市民を襲っていたことでしょう)。」
【米国債の危機について】「私がトランプ政権に入った頃、10年物金利は5%近くに急上昇していました。5%の金利水準は、米国経済にとって、また多くの債券を発行しなければならない財務省にとって不快な領域になる可能性があると思います。そして、金利が低下したいまは、少し心配は減りました。しかし、それでも心配です。われわれは莫大な借金を抱えています。われわれは無駄な歳出、詐欺的な歳出、歳出の乱用を削減しようとしていますが、それがうまくいかない場合を心配しています。それが脇に追いやられるのではないかと心配しています。他方で、税制法案がどういうわけか行き詰まり、史上最大の増税が行われるのではないかと心配しています。また、イランであろうと台湾であろうと、地政学的な事態が心配です。」
【米国債の危機について】「現在、われわれはかなりの関税収入を得られる予定であり、DOGE(政府効率化省)は大幅な経費削減を行っています。まだはいまはそうした取り組みに対する信用を得ていませんが、市場はそれを理解し始めていると思います。つまり、10年債利回りはほぼ5%でピークに達していたのが、いまでは4%に低下しているのです。0.01%ごとに約10億ドルの節約です。つまり、われわれは1,000億ドルを節約したのです。」
【FRBについて】「彼らは金融政策に焦点を当て、米国経済と米国国民のために最善を尽くし、インフレ率を低く抑えるべきだと思います。」
【中国について】「中国のビジネスモデル、そして経済は現代世界の歴史の中で最も不均衡です。GDPに対する輸出金額の水準、人口に対する輸出金額の水準という点で、現在の中国のような国家は見たことがありません。ですから、彼らがモデルを変えようとするのは非常に難しいと思います。(中略)彼らはいま、デフレ不況に陥り、不況を深刻化させています。彼らはそこから抜け出すために輸出を試みていますが、(それは米国市民をさらに傷つけるため)われわれはそれを許すことはできません。」
【中国について】「(中国との間では)われわれは製造業を増やす、逆に言えば、経済に占める消費の割合が小さくなるというディール(取引)が成立することが理想でしょう。中国は不均衡な経済を持っています。(中略)中国の家庭はいわゆる中所得国の罠に捕らわれており、われわれが一緒に何かをして、リバランスする必要があるでしょう。彼らはより多く消費し、より少なく製造する、他方のわれわれはより少なく消費し、より多く製造する、といった姿ではないでしょうか。(中略)それは明日には起こりません。それは1ヶ月で起こることではありません。しかし、今後数年間で、彼らのビジネスモデルは壊れていると思います。彼らは立ち直らなければならないかもしれません。トランプ大統領は、関税で彼らのビジネスモデルを壊したと思います。」
フィデリティ投信ではマーケット情報の収集に役立つたくさんの情報を提供しています。くわしくは、こちらのリンクからご確認ください。
https://www.fidelity.co.jp/
- 当資料は、情報提供を目的としたものであり、ファンドの推奨(有価証券の勧誘)を目的としたものではありません。
- 当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、その正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
- 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。
- 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き作成者に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。
QUICK Money Worldは金融市場の関係者が読んでいるニュースが充実。マーケット情報はもちろん、金融政策、経済情報を幅広く掲載しています。会員登録して、プロが見ているニュースをあなたも!詳しくはこちら ⇒ 無料で受けられる会員限定特典とは