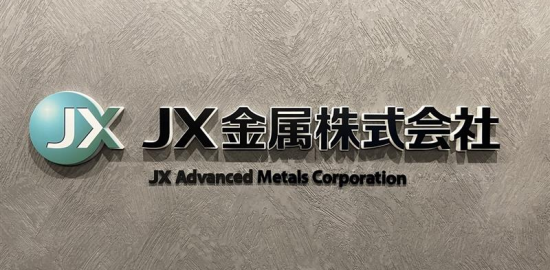財政も将来も不安、ソブリンリスクに目向く
「有事の金」。その存在感が増したのは実はここ20年ほどの話にすぎない。1980年代に東西冷戦が終わった後、政治リスクが薄れたと判断した各国の政府・中央銀行はいざというときのために取っておいた金を売り続け、「金は石ころになる」とまで言われた。転機は99(平成11)年のワシントン協定だった。商品市場の生き字引で「ブルース」の異名を持つディーラーの池水雄一氏は「中銀による金の売却基準を厳しくしたこの協定がなければ金の復権はなかった」と振り返る。

池水雄一氏
いけみず・ゆういち 1986年上智大学外国語学部卒業、住友商事入社。90年からクレディ・スイス銀行、92年から三井物産の貴金属チームリーダーを務める。2006年に南アフリカのスタンダードバンク(現ICBCスタンダードバンク)東京支店副支店長に転じ、09年から支店長。元三和銀行(現三菱UFJ銀行)の外国為替ディーラーで現在は衆議院議員を務める今井雅人氏(本シリーズ➌に登場)は大学の同級生
◆ワシントン協定で中銀の売却を制限
1989(平成元)年に1トロイオンス=400ドル程度だった金価格はワシントン協定を境に復活し、足元では1300ドル近辺で推移している。協定ができた99年といえば97~98年のアジアやロシア危機の余韻さめやらぬころだ。新興国を中心に財政赤字への懸念がくすぶっていた。
それまで長らく、中銀は金の最大の売り手だった。運用担当者が第2次世界大戦を知らない若い世代に代わり、「冷戦は終わったし金を持っていてもしかたない」との雰囲気がまん延していた。だがアジア危機などをへて、1970年代からの財政拡張で高まってきた国家のリスク(ソブリンリスク)に目が向かいやすかったのかもしれない。
協定では欧州各国の中銀が年間の売却量を計400トンに制限することになった。欧州系の中銀は保有している金の貸し出しもしていて、借り入れた鉱山会社などは先物の売りで価格下落のリスクを回避(ヘッジ)してきたがそれにも制約をかけた。協定締結まで緩やかな右肩下がりで、300~400ドル程度を行ったり来たりしていた金相場はにわかに底堅くなった。
世界に存在する金の総量はよく「オリンピックプール3杯半ほど」と表現される。一辺21.3メートルの立方体程度なのだという。限られたパイの中で最大のプレーヤーである中銀の売りを抑えれば、需給はおのずと引き締まる。
その後、2001年に起きた米同時多発テロは国際情勢の緊張感を再び高めた。世界は思ったほど平和ではない――。世界大戦や冷戦構造から局地的なテロが新たな脅威として意識されるようになり、「セーフヘイブン(安全資産)」として金のニーズが高まった。
◆鉱山会社のヘッジ売りも止まる
ワシントン協定は金鉱山会社の手足も縛った。金の先安観が強かった80~90年代の相場環境で、オーストラリアや南アフリカなど主要産金国の鉱山会社は中銀から安く借り入れた金を主な担保に数年先までの生産分相当額の先物を売ってきたが、中銀がなかなか金を貸してくれなくなったので市場から調達せざるを得ない。コストは上がる。ヘッジが機能しづらくなっていた。
ヘッジ戦略は相場の下落時に鉱山会社を守ってくれるが、先物売りが現物の売りに波及し値段をさらに下げる負の側面もあった。ワシントン協定はその悪循環を止める役割も果たしたわけだ。
しかも01年以降は「有事の金」復権で価格が上昇傾向に転じ、数年前に安い価格で積みあげた先物の売り持ち高には含み損が膨らむ。金価格の下落がこれ以上は見込めないとなると、各社は先物の買い戻しを急ぎ始めた。先物売りが減るだけでなく買い戻しが入る。買いが「倍々ゲーム」で広がるようなものだ。
ただディーラーの視点では「有事の金買い」にあまり踊らされないことが重要だ。紛争などが起きて投資家が我先にと金を買うと、必ず相場のオーバーシュート(行きすぎ)が起こる。短期的にはひとまず調整が入る「有事の金売り」を意識し、落ち着いたところで改めて買うスタンスが良いだろう。
平成の話ではないが例えば、1979年に発生したソ連のアフガニスタン侵攻。ニューヨークの金相場は200ドル台から850ドルまで急騰した後、すぐに押し戻されてきた。目端の利く投機筋は誰よりも早く持ち高を作ろうとし、イベントが人々の間で認知されれば利益確定を進める。そんなときは相場はいったん下がる。
◆米中ロ、国際政治の不透明感を反映
2006~07年ごろから金の世界は変わってきたと感じる。08年のリーマン・ショックに続き、足元では英国の欧州連合(EU)からの離脱(ブレクジット)問題やトランプ米政権の登場などいままでの常識では考えられない事態が起き、資本主義の前提が崩れてきた。漠然とした将来の不安は解消しそうにない。「有事の金」の価格が200~300ドル台に戻る可能性はもうないだろう。
米国が金本位制を放棄した1971年の「ニクソン・ショック」からしばらくは金の大口保有者は米国とドイツなど先進国の中銀で、ワシントン協定まで金の売り手だったのは欧州勢だった。だが2010年ごろから中銀は金の買い手に転じている。中国やロシアなどが外貨準備として保有していた米ドルを売り、金の買いに傾いているためだ。米国との微妙な関係と国際政治の不透明感を映していると考えられる。
基軸通貨のドルを持つ米国は別の通貨を多く保有していてもしょうがないので外準に占める金の割合は現在も75%と突出している。その他の欧州各国の間に中国やロシアなどの「新参者」が割り込んでいく展開になってきた。
中国は世界1位の、ロシアは世界3位の金産出国でもあるため、市場で買わなくても金の保有割合を増やせる。近年はロシアが世界6位、中国は7位の金保有国に浮上した。ロシアが数年前にルーブル下落に苦しんだ際にどうにか持ちこたえられたのは、金の保有を多くしていたからとの指摘が聞こえてくる。
リーマン・ショック以降の米金融緩和政策の影響は大きかった。低金利の資金が行き先を求めて市中にあふれる構図は金に限らず商品相場全体に追い風だった。2012年に量的緩和第3弾(QE3)が始まったころ1600ドル台で推移していた金相場は、米連邦準備理事会(FRB)の出口政策が意識されると1200ドル台まで下げたが、19年に入ると今度は「緩和の終わりの終わり」が意識されている。金は再び上昇トレンドに戻ると予想している。
=聞き手は日経QUICKニュース(NQN)片岡奈美
=随時掲載