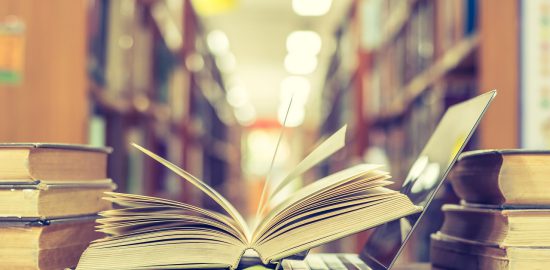SBI証券が取り扱う投資信託の積み立ては、月間の設定額が今年に入って100億円を突破した。QUICK資産運用研究所の調べでは、ネット専業証券の中で最大規模となる。
月間の投信積み立て設定額は今年2月に初めて100億円を上回り、3月も増加傾向が続いた。2年前の50億円程度と比べ倍増した。長期的な視点で取り組んできた投資家層の拡大戦略が実を結んだ格好だ。
同社の投信ビジネスを先導してきたキーパーソンの橋本隆吾執行役員(投信・債券部長)に話を聞いた。

橋本隆吾氏(執行役員 投信・債券部長)
――100億円突破までの道のりは。
「月間100億円になるまでに10年以上の年月を要しました。2008年の米リーマン・ショック直後あたりが黎明期です。有名な投信ブロガーの方々の影響もあって、三菱UFJ国際投信の『eMAXISシリーズ』など指数連動型で低コストのインデックスシリーズが注目を集めました」
「2012年には少額投資を推進するために最低投資額を500円に引き下げたこともあり、積み立て投資の手法が脚光を浴び始めました。14年に始まった少額投資非課税制度(NISA)をきっかけに積み立て口座数が飛躍的に伸び、当社ビジネスの中核として成長する勢いを感じました」
「16年12月頃からはトランプ・ラリーによる相場上昇が追い風となり、成功体験を積んだ投資家も少なくなかったようです。17年10月には積み立て機能を拡充し、新しく始めた『毎日積み立て』などが投資家に支持されています。18年1月からスタートした『つみたてNISA』も浸透してきました」
――SBI証券の投信積み立ての特徴や強みは。
「商品数の多さが特徴の一つです。2500本を超える豊富な投信のラインアップがあり、その中で当社の課税口座や一般NISA口座で積み立て設定ができるのはだいたい1900本から2000本くらいあります。幅広い投資家層のニーズに対応するために品ぞろえの充実は常に意識しています」
「もう一つは、総合ネット証券として投信以外にも多様な投資商品を取り扱っていることです。国内外の株式やIPO(新規株式公開)、PO(公募増資・売り出し)、個人向け社債、外債などを幅広く取りそろえているので、投信以外の金融商品と組み合わせて投資することができます。こうした規模の大きさや総合力が集客につながっている面があります」
――どのような顧客が多いですか。
「株式や一般の投信保有者に比べると、投信積み立ては20歳代から40歳代の資産形成層と呼ばれる年代の投資家が多いです。また、株式投資と比べ女性の比率がわずかに高くなっています」
「金融リテラシーの高い顧客も多いと感じています。ドル・コスト平均法や長期・分散などといった資産運用の基本を理解している印象で、小口の100円から気軽に始められる当社の投信積み立てを活用しながら、独創的な投資手法でトータルリターン(総合収益)を高めている投資家もいるようです」

1982年住友信託銀行(現:三井住友信託銀行)入社。年金運用、債券トレ-ディング業務等を経て、2005年住信アセットマネジメント(現:三井住友トラスト・アセットマネジメント)に出向。投資信託の運用、商品企画、営業を担当し、2013年11月SBI証券入社、現在に至る。
――投信積み立て機能拡充の反響は。
「2017年10月に実施した投信積み立て機能の拡充で、毎日、毎週、毎月、複数日、隔月の5コースの中から積み立てコースを選べるようにしました。その後も従来からの毎月積み立ては安定して伸びています。さらに究極の時間分散といえる『毎日積み立て』も大きく増えており、月間設定額100億円突破のドライバーの一つになったと言っても過言ではありません」
――どのような開発体制で機能拡充に臨んだのですか。
「全社でプロジェクトチームを立ち上げるような大規模な取り組みではありません。当社のシステム担当者とサービス企画推進(フロント)担当者、SBIグループ内のシステム開発担当者のメンバー数名で議論を繰り返し、納得のいくサービスに仕立てていきました」
「少ない要員でも比較的短期間で開発が実現できた背景には、フロント担当者がシステムや画面設計に詳しく、要件定義を主導しながら全体開発を進めていけたことがあります。コールセンターに寄せられた顧客の要望なども吟味し、操作性を高める工夫をしていきました」
「投信積み立ての独自機能である『NISA枠ぎりぎり注文』などは、その過程で生まれた発想です。『NISA枠ぎりぎり注文』はNISAで投資できる残り枠に応じて自動で注文金額を調整し、枠を超える金額は発注されない仕組みです。株式など他の商品のシステム開発を掛け持ちしている担当者も多いのでスピードを要する開発には苦難を伴いますが、グループ独自の開発でシステム設計できる体制は当社の強みといえます」
――今後の戦略を教えてください。
「総合ネット証券として全方位で取り組む姿勢に変わりありません。主戦場であるネット画面の操作性を高めるべく、シミュレーターやスクリーニング機能などを拡充していきたいです。投資家が自ら投信を選びやすくなるような啓蒙コンテンツの提供にも力を入れていきます」
「また、四半期に1回程度のペースで長年続けてきた投信積み立てのキャンペーンを地道に続けていくつもりです。会場型セミナーなども積極的に取り組みながら、投資家とともにレベルアップを図っていきたいと思います」
(QUICK資産運用研究所 大沢崇)