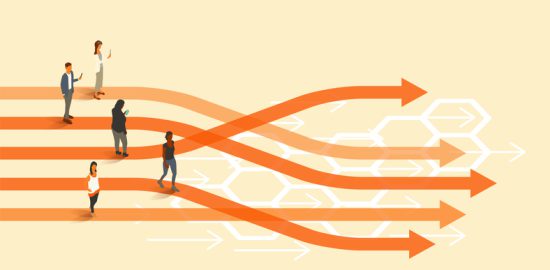QUICK Market Eyes=丹下智博、池谷信久
依然として新型コロナウイルスの感染拡大が沈静化する兆しが見えない。一方でグローバルの金融市場は変動幅が大きいものの「底割れ」を回避した小康状態を続けている。投資家に一定の安心感を与えているのが世界の中央銀行の危機対応とも言える金融緩和政策。米国ではひとまず引き締め度合いが強まっていた金融環境に一服感も出始めている。
■リスク圧縮は継続の可能性
米シカゴ連邦準備銀行が22日に公表した4月17日までの週の金融環境指数(NFCI)はマイナス0.15と前週(10日まで)のマイナス0.11(改定値)から低下した(灰色棒)。同指数は数値が低ければ金融環境が緩和的、高ければ引き締め的であることを示し、2011年の欧州債務危機の時以来のプラス転換が懸念されていた。マクロ経済条件で調整した指数(ANFCI)は3月20日までの週で先行してプラスに転じていたが(橙棒)、NFCIはゼロ直前で踏み止まることになりそうだ。米連邦準備理事会(FRB)が「無制限」の緩和を示したことが有効だった。構成する3項目のうち、「リスク」(ボラティリティ:赤線)には頭打ちの兆し、「クレジット」(信用リスク:青線)にも鈍化傾向が見られる。一方、「レバレッジ」(緑線)は高水準を維持しており、市場参加者によるリスク圧縮の動きは継続する可能性が高そうだ。
■日銀の次の一手は・・・
欧州中央銀行(ECB)は新型コロナと戦う姿勢を改めて示した。22日に銀行ローンの担保に「ジャンク債」と呼ばれる低格付け債を受け入れると発表した。ただ、野村証券の松沢中氏は日銀が同様の決定をしたとしても、「スプレッド縮小にはつながっても、企業金融全体に与える効果は乏しい」と指摘した。日本では同等の社債市場の規模がかなり小さいためであり、焦点は「市場性のない銀行貸出債権へ働きかける策」であると述べている。
米連邦準備理事会(FRB)の様な債権買い取りの影響力は大きい。貸出債権を売却した銀行はその資金をクレジットや国債に振り向けるため、結果的に「市場金利の低下、スプレッド縮小」の効果もあると指摘。また、「貸出支援オペの担保基準緩和や、金利引き下げ(マイナス金利貸出)も意義があろう」とも述べている。
その日銀は23日、27~28日の2日間にわたって開く予定だった金融政策決定会合の日程を1日に短縮し、27日のみの開催にすると発表した。
展望レポート発表月の会合を1日で行うという異例の措置に関し、SMBC日興証券の森田長太郎氏はレポートで「議論の紛糾がないことを前提にしたもので、金融政策の緊張感が先月からはやや後退していることの表れ」と指摘した。日銀が今回の決定会合で検討する措置は社債・CPの買入れ強化と銀行の企業向け融資サポート策の2つに絞られる見込みだ。
ただ、ロイター通信は、コロナ対応で経済の停滞が長期化した場合には「年後半にも大規模緩和を打ち出す必要が出てくるかもしれない」との議論が日銀内で出ていると伝えている。森田氏は追加緩和の具体策は不明としながらも、財政ファイナンスを半ば容認するような形での「国債買入れを中心とした量的政策の再強化」、「ETF購入の更なる増額」を組み合わせたパッケージという形を、「現時点でできるイメージ」として挙げていた。
一方、実質的な経済効果をより求めるのであれば、「企業ファイナンスのより直接的なサポートに踏み込むかどうかに尽きる」とも指摘。低格付社債の購入の他、ノンリコースでのローン担保資金供給ないし直接のローン買取りが「最後の手段」としては残るという。しかし、「この政策を米国のような政府からのエクイティ供与なしに実施することが可能なのかどうかも、やはり現時点では不明だ」とも述べていた。
<関連記事>
■米ザイリンクスが時間外で6%安 コロナ問題で4~6月期業績見通しが予想下回る
■J.フロント リテイリング(3086) 新型コロナ収束後の消費行動変容リスク回避に向け、変革加速を期待
■原油の上場投資商品に資金流入、運用対象はWTI 6~7月限で関心集める