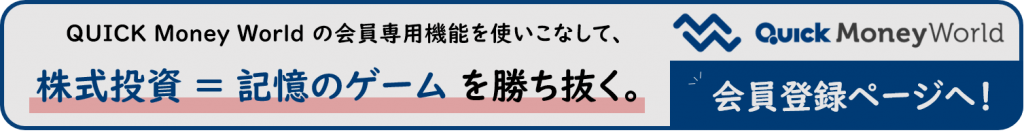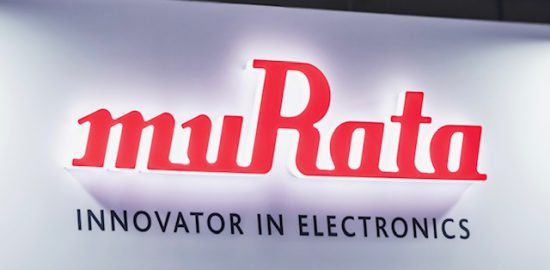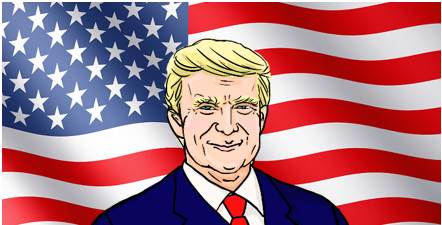9月30日、日本電信電話(9432、NTT)は子会社のNTTドコモ(9437)の完全子会社化を発表した。NTTの技術・サービスの競争力への懸念などやドコモの5G(次世代通信規格)の普及の遅れが背景となっている。
■スマホ出荷台数の減少
新型コロナウイルスの影響が本格化する前、2020年は5G(次世代通信規格)本格化の年と目されていた。すでに5Gサービスをスタートしていた米国や中国、韓国などに加えて、日本でも5Gの商用サービスがスタートするなど期待感が高まっていた。ただ、国内では、中国などに比べて5G端末の普及は進んでいない。新型コロナウイルスの影響による消費の押し下げも世界のスマートフォン販売に影を落としている。
米調査会社IDCが7月末に発表した2020年4~6月期の世界のスマートフォン出荷台数の予想は、前年同期比16.0%減の2億7840万台だった。日本、中国除くアジア、欧米などの幅広い地域で落ち込みが続き、1~3月期の同11.7%減から減少幅は悪化した。一方、中国の4~6月期は、同10.3%減と相対的に落ち込みが小さく、回復の傾向が見られると指摘した。
SMBC日興証券の9月29日付の電子部品セクターリポートによると、20年の5Gスマートフォンは、中国だけで約1.6億台に達する勢いとみているようだ。10月以降に発売が期待されている新型のiPhone12の5G対応により、21年には、グローバル で普及が本格化する見込みで期待先行から、実需を確認するフェー ズにようやく移行するとの見通しを示している。
■5Gの関連銘柄の騰落率
5Gの関連銘柄の騰落率を比較するため、 国内の追加型株式投信の純資産総額ランキングの上位の中から三井住友アセットマネジメントの「次世代通信関連 世界株式戦略ファンド〈愛称:THE 5G〉」の組み入れ上位銘柄の20年の騰落率を調べてみた。まず19年末から10月2日までの分配金再投資換算基準価額の騰落率は、14.8%と米国S&P500指数の3.8%を上回った。公開されている最新の8月末のファンドレポートによると組み入れ上位銘柄で最も2020年に上昇したのは、中国の電子商取引(EC)サイトのJDドットコムで116%の上昇だった。コロナ後のEC化の加速と中国の景気回復の2つが追い風となった。
欧州の通信インフラ事業者の セルネックステレコムや米国の通信キャリアのTモバイルUSもそれぞれ4割を超える上昇となった。TモバイルUSは、4月にソフトバンクグループ(9984)よりスプリントの買収を完了し、両社のシナジー効果を期待する向きもあり、株価は堅調に推移している。
通信半導体大手のクォルボの業績見通しも好調さが伺える。クォルボは、5Gで活用される高周波向けの通信半導体に強みを持っている。9月10日に足元の5Gスマートフォン向けなどの需要の強さを受け、20年7~9月期の売上高と1株利益の見通しを上方修正し、好感された。
日本株では、積層セラミックコンデンサ大手の太陽誘電(6976)が唯一組み入れ上位銘柄としてランクインした。コロナ禍による産業向けや自動車業界向けなどの落ち込みもあり、19年末からの騰落率ではほぼ変わらずの水準となっている。ただ、足元は積層セラミックコンデンサーなど電子部品の復調への期待感は、高まりそうだ。
クレディスイス証券は、5日付のリポートで9月後半に日 本、香港、シンガポールの投資家を中心に行った投資家向けのミーティングでは、10-12月期に向け ては電子部品セクター全体に対して強気な投資家が多い印象との見方を明らかにした。短期的には、車載向けの需要増やiPhone12の発売への期待が多かったとした。足元で iPhone 関連の部材の需要ひっ迫から株式市場の想定を上回る生産が進んでいるとみているようだ。米国による輸出規制などで苦境の続く中国ファーウェイ(華為技術) からのシェア奪取に動いているとの 観測から11月~12月の中国市場でのiPhoneのシェア上昇度合いに注目が集まるとみているようだ。(QUICK Market Eyes 阿部哲太郎)
<金融用語>
シナジー効果とは
シナジーは共力作用の意味を持つ英語で、シナジー効果とはM&A(企業の合併・買収)などを通じて複数の企業や事業を統合した場合、それぞれの価値を単純に足し合わせた合計よりも大きな価値を生み出す相乗効果のことを指す。 統合する相手企業の公正な価値評価にはシナジー効果を含めるのが妥当とされる。シナジー効果の例として、商品サービスの拡充や販売チャネルの拡大による売上げ増加、製造・販売拠点や物流など重複する機能の統廃合によるコスト削減、技術・ノウハウの共有や財務統合による節税効果などがあげられる。