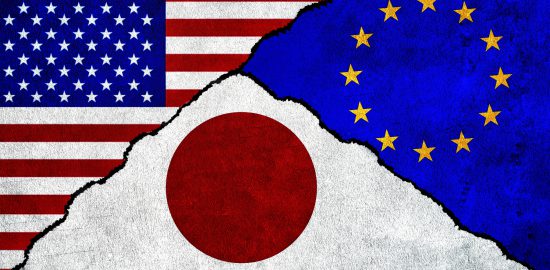10月20日の米債券市場で長期債相場は小幅に4日続落し、米長期金利の指標となる10年物国債利回りは前日比0.01%高い(価格は安い)0.78%で終えた。追加の米経済対策の与野党協議が合意に至るとの楽観から米国債が売られた。最近は小売売上高など一部指標の堅調さも目立つが、コロナ禍の景気回復のいびつさに着目し先行きの不透明感を意識する市場関係者は多く、債券の下値は堅い。

■高所得者の雇用状態が景気を左右
「2020年の失業は08年の金融危機後の景気後退と全く違う」。FHNファイナンシャルのクリス・ロウ氏は最近発表したリポートでこう指摘した。失業者の多くが低所得者だったコロナ禍では、失業が比較的少なかった高所得者が急ピッチの景気回復をけん引している。一方、金融危機後は高所得者の失業の割合が高かったうえ、その後の累進課税が景気回復を遅らせたと分析する。
雇用面を詳しくみると、金融危機後の景気後退が始まってから2年たつ10年序盤時点で所得上位40%の層で500万人強が失業していた。一方、現状では所得上位40%の失業者は約270万人にとどまる。米国では個人消費が実質国内総生産(GDP)の約7割を占め、所得の上位20%が全体の約4割を消費する。下位20%の3倍超となる。高所得者の雇用状態が景気を大きく左右する構造だ。
9月の失業者数はコロナ前の2倍以上だが、同月の小売売上高はコロナ前をすでに回復しているのはこうした状況を映す。宝飾品やヨットなど高級品の売れ行きが好調だ。夏までの失業給付の上乗せが低所得者の所得を底上げしているが、格差は拡大しながら高所得者が経済を引っ張る、ややいびつな状態が鮮明になっている。
■大企業の強さが雇用減に?
ゴールドマン・サックスのジョン・ウォルドロン社長兼最高執行責任者(COO)がブルームバーグ通信に対して、大企業の強さが先行きの雇用減につながるリスクを指摘したのも市場の話題になった。同氏は力強い大企業が弱い中小企業を買収する形で大型のM&A(合併・買収)が増えるとの見通しを示した。緩和的な金融政策を背景とした低金利がこうした動きを促す。ウォルドロン氏はM&Aの活発化は好ましいとしつつ「政治家は大企業が好業績を達成し、買収により失業を生み出すという気まずい現実に今後向き合うことになる」と予想した。
エバコアISIのスタン・シプレー氏は州政府などが発行する地方債の動きを注視する。米連邦準備理事会(FRB)のコロナ対策の緊急資金供給策の一環による地方債買い取りは一定の効果はあったが、地方債の利回り低下は限定的で、米国債との利回り差(スプレッド)はコロナ前の水準には戻っていない。連邦政府による州政府などへの支援が途絶えれば、今後の州政府の財政は悪化する。州や地方自治体の雇用は米雇用全体の約13%を占める。シプレー氏は「州政府が雇用減に踏み切れば景気を下押ししそう」と警戒する。
米経済の回復はこれまでのところ順調にみえるが、偏りのある回復が思わぬところで均衡を崩し、債券買いを促すリスクを想定しておいた方がよさそうだ。(NQNニューヨーク 川内資子)
<金融用語>
実質国内総生産とは
GDPは、名目GDPと実質GDPで構成される。 実質GDPは物価の変動による影響を取り除き、その年に生産された財の本当の価値を算出したものである。 たとえば、財の値段が一気に2倍になったとする。この場合名目GDPは2倍となるが、経済の規模も2倍になったとはいいきれない。それは、個人の所得も2倍になったとすると、個人の購入できる財の量は変わらないからである。このように、財の値段が変化することでGDPの数値が変化してしまうことを避けるため、経済の実状を知るうえでより重視されている。