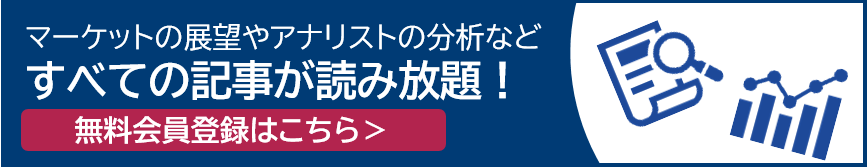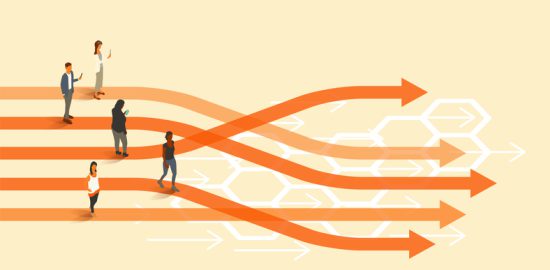金融市場の目下のテーマのひとつは、米国の長期金利上昇でしょう。
筆者は、今年3月のエントリーで「米10年金利は4.5%~5.0%程度まで上昇する」とお伝えしており、(直後に銀行危機が起きたものの)いまもこの見方は変わりません。
目下の米国の長期金利上昇は、ファンダメンタルズ? 需給?
目下の米国の長期金利上昇は、ファンダメンタルズというよりも、需給の観点から生じているようにみえます。
先にファンダメンタルズを考えると、たとえば、【次の図】に示すとおり、①インフレ期待は落ち着いたままであり、
ほかにも、【次の図】に示すとおり、②来年の利下げ期待も「健在」です。
そして、もうひとつ、③(経済の貯蓄と投資を均衡させる実質)均衡利子率・自然利子率の上昇によって、(観察可能な)実質金利に上昇圧力が生じている可能性も考えられます。
しかし、その場合には、まずはインフレ率の上昇が先立ち、これによって「実質金利が均衡利子率よりも低い」(=緩和的である)ことが認知され、実質金利が上方調整する(もしくは実質政策金利が引き上げられる)といったふうに、インフレ圧力が先立つと考えられます。
実際には、上述のとおり、インフレ圧力はこのところ顕在化しておらず、金融市場は、(実体経済の貯蓄と投資を均衡させる)均衡利子率の上昇を見ていないように思えます。
米国債の需給を決めるひとつの要因、財政赤字
そこで米国債の需給を考えると、ひとつには、米国債の発行増加に直結する財政赤字の拡大が挙げられます。
【次の図】に示すとおり、2023財政年度の財政収支【●点付きの赤ライン】は、(パンデミックによる財政出動がほとんど消失した)2022財政年度【ピンク】に比べ、大幅に悪化しています。
バイデン政権の財政政策に加えて、財政赤字の拡大に貢献していると考えられるのが、米連邦準備制度理事会(FRB)から財務省への送金金額の減少です。
【次の図】に示すとおり、FRBと連邦準備銀行は昨年7-9月期に財務省への送金を停止しています。その背景は、本欄でお伝えしてきたとおり、FRBの資金収支が赤字・逆ザヤに陥ったためです。中央銀行による赤字・逆ザヤは、①量的金融緩和によるバランスシートの拡大、②準備預金への付利開始、③急速なインフレに伴う大幅な利上げ、の3段階によって生じています。
【次の図】に示すとおり、FRBは世界金融危機以降、(ゼロ金利政策下でバランスシートを膨らませることで)年間800億ドル~1,000億ドル程度の利益送金を行ってきました。これに対し、2023年財政年度(今年7月時点)は、送金額がほぼゼロに近い水準となっています。
【次の図】に示すとおり、この送金額を毎年の財政赤字幅と単純比較すると、財政出動が増えた世界金融危機後やパンデミック後でも、FRBから財務省への利益送金は4-5%程度の財政赤字削減に貢献してきたと試算されます。
やはり単純比較ですが、仮に、今年7月までの送金額が昨年度と同じであったとすれば、今年度の財政赤字(7月まで)は6%程度、少なかったと試算されます。
上記のとおり、中央銀行が赤字・逆ザヤに陥って財務省への利益送金が停止されると、政府の収入が減ることで財政収支が悪化します。
合わせて、前々回に考えたとおり、仮に中央銀行の赤字や債務超過が貨幣の信用に対する懸念を生む場合には、徴税や国債の発行によって、中央銀行の増資が行われると考えられます。
以上をまとめると、足元では、「中央銀行の財務悪化により、(いざというときに中央銀行を支えるべき)政府の収入が減少する」という事態が生じています。政府の財政と中央銀行の財務が同時に悪化する事態は、準備預金への付利から生じています。
以下に述べるように、「付利のない世界」と「付利のある世界」では、全く異なる事態が生じます。たとえば、「付利のある世界」では、政府・有権者から市中銀行に利益を手渡すことになります。そして、市中銀行は必ずしも、受け取った利益を預金者への利息として還元していないようにみえます。
「付利のない世界」の政府と中央銀行
世界金融危機前、準備預金に付利をする中央銀行はほとんど存在しませんでした。あるいは、付利を行う中央銀行でも準備預金の発行金額はきわめて小規模でした。
「付利のない世界」の中央銀行は「ほとんど無敵の存在」です。
金融資産や実物資産の多くは利息や配当金が非負であるため、中央銀行が、利息ゼロ%で発行する負債(準備預金や紙幣)でこれらの資産を買えば、資金収支が赤字になることはありません。
以下では「付利のない世界」の中央銀行と政府について、具体例を考えます。
例として、中央銀行が利回り3%の国債を購入したとすれば、3%の利息はすべて中央銀行の利益です。そして、多くの中央銀行は(業務費用を差し引いた後の)利益を政府に送金します。
このときに重要なのは、政府と中央銀行を一体ととらえる「統合政府」の考え方です。
同じ例で政府は中央銀行が保有する国債に3%の利息を支払いますが、同行からは同額の利益送金を受けます*。
すなわち、「付利のない世界」において、政府は「中央銀行が保有する国債については利息ゼロ%で国債を発行する」ことができました。その分だけ、財政費用(支払利息)を削減できたわけです。
このように「付利のない世界」は、統合政府にとっても居心地のよい世界でした。ところが、上述のとおり、準備預金への付利は、政府と中央銀行を苦境に追い込むことになります。
*捕足すると、①国債購入の場合、中央銀行にとっての利益(受取利息)は、政府にとっての費用(支払利息)であり、バランスシートを連結すれば、互いに相殺されます。言い換えれば、中央銀行にとっての利益は、統合政府にとっての利益ではありません。
別途、②リートや株式の購入の場合には、中央銀行がその配当金を受け取って政府に送金すると、統合政府は民間部門から利益・資金を吸い上げることになりますから、「徴税」に似た性格を持ちます。中央銀行による受取配当金は、統合政府にとっての利益です。
「付利のある世界」の政府と中央銀行
次に、「付利のある世界」の中央銀行と政府についても具体例を考えます。
仮に政府がしばらくのあいだ、3%の利回りで国債を発行してきたとします。民間部門が保有する国債には3%の利息が満期まで支払われますし、中央銀行が保有する国債についても同様です。
そこで中央銀行が政策金利を2%に引き上げるとします。このとき政府は、①中央銀行が保有する国債に3%の利息を支払った上で、②中央銀行から同額を利益送金で返してもらいますが、他方で、③中央銀行は利上げに伴い、市中銀行が保有する準備預金に2%の利息を支払います。
したがって、統合政府にとってのキャッシュフロー(準備預金発行額部分)は、「マイナス3%+3%-2%」=「中央銀行保有国債への利払い+中央銀行からの利益送金+中央銀行による市中銀行への利払い」=「マイナス2%」です。
すなわち(「付利のない世界」では利息負担がゼロ%だった)中銀保有国債を介し、政府は市中銀行に2%の利息を支払っているのと同じで、財政負担が増しています(→ただ、まだコストは「2%」ですから「3%」で市場消化したときよりはコストをセーブできています)。
それどころか、現在のFRBのように中央銀行が5%まで利上げを行うと、統合政府のキャッシュフロー(同)は「マイナス3%+3%-5%=マイナス5%」です。
すなわち、政府は(中銀保有国債の存在によって)財政コストをセーブするどころか、中銀保有国債(準備預金発行額相当分)については、発行時(3%)よりも高い金利(5%)を(市中銀行に)支払うことになります。利率「3%」で発行し、中銀保有によってコスト「0%」で調達したつもりの国債の利率が「5%」に引き上げられたのと同じです。
言い換えれば、準備預金への付利は、発行済み国債の一部(準備預金発行額相当分)を変動利付国債として発行しているのと同じ効果をもたらします。
一般に、利上げが生じると、政府が新たに発行する新発債については市場金利の上昇で発行利率が高まり、政府の財政負担は高まります。これに加えて、「付利のある世界」では、政府が過去に発行した既発債の利率も短期金利に連動して事実上増加することで、財政負担をさらに高めます。
まとめると、「付利がない世界」では、中央銀行が保有する国債については利息ゼロで発行でき、財政コストが減りました。他方の「付利がある世界」では中央銀行が保有する国債が多ければ多いほど、財政負担が高まる潜在的なリスクを抱えます。
FRBは、超過準備をなくして「付利のない世界」に戻れたはずだが、「付利のある世界」に居続けることを決めた
準備預金に付利をした理由は「多額の準備預金・流動性がもたらす短期金利への低下圧力」と「利上げ」という矛盾を回避するためです。
しかし、FRBは2019年1月に、金融政策の正常化を終えた後でも(金融危機前のように超過準備をゼロにまで減らすことで)「付利のない世界」には戻ることはせず、準備預金を潤沢なままに保って「付利のある世界」を続けることを決定しています。FRBはこの世界を、「Ample Reserve Systemへのレジーム移行」と称しています。
その理由は明示されていません。たとえば「フェデラルファンド市場での日々の金利誘導という煩雑なオペレーションや無用な短期金利の変動をなくすため」が挙げられるかもしれません。しかし、現状のFRBの赤字や債務超過、政府の財政悪化に鑑みれば、筆者には費用対効果のバランスが取れているようには思えません。
いずれにせよ、上述のとおり、準備預金への付利で負担が増えるのは統合政府であり、利益が増えるのは市中銀行です。
「付利のない世界」の市中銀行は、短期調達・長期運用のデュレーションのミスマッチ(とクレジット)のリスクを取ることで収益を得てきました。利上げが続いて逆イールドになると、期間収支が逆ザヤになったり、保有有価証券に含み損が生じたりして、財務状況は悪化しました(→今回も一部の中小行はそうなりました)。
ところが、「付利のある世界」の市中銀行は、上記の従来業務に加え、準備預金を潤沢に保有することで、利上げ時には付利からの利益が増加し、上記の期間収支の逆ザヤや有価証券の含み損を一部補うことになります。保有する準備預金は、政府に変動金利で貸し付けているのと同じですから、顧客預金とのデュレーションのミスマッチがありません。
「付利のない世界」で逆ザヤになるのは市中銀行でした**が、「付利のある世界」で逆ザヤになるのは中央銀行です。中央銀行が逆ザヤに苦しむ分だけ、統合政府の財務が悪化する分だけ、市中銀行は楽になっています。
実際、米国の政策金利は5%を超え、FRBは逆ザヤですが、市中銀行はFRBから5%の利息を受け取りつつ、顧客預金金利は2%程度に留めています(→今年3月時点)。バランスシート全体の逆ザヤを回避し、利益を確保するためです。
FRBが2019年1月に、なぜ「Ample Reserve Systemへのレジーム移行」を決めたのか、筆者には謎のままです。
**たしかに今回も逆ザヤや含み損で苦しんだ中小行が出ましたが(→今後、さらに出るでしょう)、そうした銀行は大手行によって買収され、寡占化が進みました。
参考文献
Anderson, Alyssa, Dave Na, Bernd Schlusche, and Zeynep Senyuz (2022a) “An Analysis of the Interest Rate Risk of the Federal Reserve’s Balance Sheet, Part 1: Background and Historical Perspective”, FEDS Notes, Board of Governors of the Federal Reserve System, 15 July 2022
Anderson, Alyssa, Dave Na, Bernd Schlusche, and Zeynep Senyuz (2022b) “An Analysis of the Interest Rate Risk of the Federal Reserve’s Balance Sheet, Part 2: Projections under Alternative Interest Rate Paths”, FEDS Notes, Board of Governors of the Federal Reserve System, 15 July 2022
Archer, D and P Moser-Boehm (2013) “Central bank finances”, BIS Papers, No 71, April 2013
Bank of England (2023) “Asset Purchase Facility Quarterly Report – 2023 Q1”, 28 April 2023
Bell, Sarah, Michael Chui, Tamara Gomes, Paul Moser-Boehm and Albert Pierres Tejada (2023) “Why are central banks reporting losses? Does it matter?”, BIS Bulletin, No 68, 7 February 2023
Board of Governors of the Federal Reserve System (2022) “Federal Reserve Banks Combined Financial Statements As of and for the years ended December 31, 2022 and 2021 and Independent Auditors’ Report”
Board of Governors of the Federal Reserve System (2023) “Financial Accounting Manual for Federal Reserve Banks”, January 2023
Bonis, Brian, Lauren Fiesthumel, and Jamie Noonan (2018) “SOMA’s Unrealized Loss: What does it mean?”, FEDS Notes, Board of Governors of the Federal Reserve System, 13 August 2018
Bukhari, Meryam, Alyssa Cambron, Marco Del Negro, and Julie Remache (2013) “A History of SOMA Income”, Liberty Street Economics, Federal Reserve Bank of New York, 13 August 2013
Bullock, Michele (2022) “Review of the Bond Purchase Program”, Speech for Bloomberg, Reserve Bank of Australia, 21 September 2022
Bundesbank (1976, 1977, 1978, 1979, 1980) “Report of the Deutsche Bundesbank for the Year 19xx”, Annual Reports
Bundesbank (2023) “Annual Report 2022”, 1 March 2023
Cipriani, Marco, James Clouse, Lorie Logan, Antoine Martin, and Will Riordan (2022) “The Fed’s Balance Sheet Runoff and the ON RRP Facility”, Liberty Street Economics, Federal Reserve Bank of New York, 11 April 2022
English, William B. and Donald Kohn (2022) “What if the Federal Reserve books losses because of its quantitative easing?”, The Brookings Institution, 1 June 2022
European Central Bank (2023) “Annual Report 2022”, 25 May 2023
Federal Reserve Bank of New York (2023) “Annual Report on Open Market Operations During 2022”, April 2023
Nordström, Amanda and Anders Vredin (2022) “Does central bank equity matter for monetary policy?”, Staff Memo, Sveriges Riksbank
Sveriges Riksbank (2023) “Annual Report for Sveriges Riksbank”, 20 March 2023
Ueda, Kazuo (2003) “The Role of Capital for Central Banks” Speech at the Fall Meeting of the Japan Society of Monetary Economics on October 25, 2003
池尾和人 (2010) 『現代の金融入門【新版】』、ちくま新書831、筑摩書房
岩田一政、左三川郁子、日本経済研究センター (2016)『マイナス金利政策: 3次元金融緩和の効果と限界』、日本経済新聞出版社
岩田一政、左三川郁子、日本経済研究センター (2018)『金融正常化へのジレンマ』、日本経済新聞出版社
岩村充 (2018) 『金融政策に未来はあるか』、岩波新書1723、岩波書店
翁邦雄 (2017) 『金利と経済―高まるリスクと残された処方箋』、ダイヤモンド社
小林慶一郎(編著)(2018) 『財政破綻後: 危機のシナリオ分析』、日本経済新聞出版社
齊藤誠、岩本康志、太田聰一、柴田章久 (2010) 『マクロ経済学』、New Liberal Arts Selection、有斐閣
白川方明 (2008) 『現代の金融政策: 理論と実際』、日本経済新聞出版社
高田創(編著)(2017) 『シナリオ分析-異次元緩和脱出: 出口戦略のシミュレーション』、日本経済新聞出版社
門間一夫 (2022) 『日本経済の見えない真実 低成長・低金利の「出口」はあるか』、日経BP
フィデリティ投信ではマーケット情報の収集に役立つたくさんの情報を提供しています。くわしくは、こちらのリンクからご確認ください。
https://www.fidelity.co.jp/
- 当資料は、情報提供を目的としたものであり、ファンドの推奨(有価証券の勧誘)を目的としたものではありません。
- 当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、その正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。
- 当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の傾向、数値、運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。
- 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き作成者に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。
QUICK Money Worldは金融市場の関係者が読んでいるニュースが充実。マーケット情報はもちろん、金融政策、経済情報を幅広く掲載しています。会員登録して、プロが見ているニュースをあなたも!詳しくはこちら ⇒ 無料で受けられる会員限定特典とは