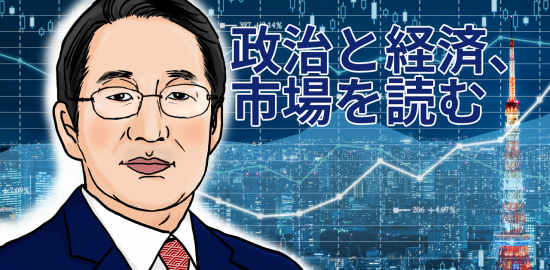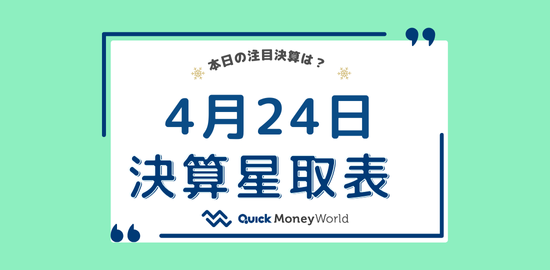【QUICK解説委員長 木村貴】トランプ米次期政権で政府の歳出削減を目指す「政府効率化省(DOGE)」が話題だ。米電気自動車(EV)大手テスラを率いるイーロン・マスク氏がトップに就く。マスク氏はビジネスで培った剛腕を振るって、政府の効率を大幅にアップできるだろうか。
権限を疑問視
マスク氏は「少なくとも2兆ドル(約310兆円)を削減する」と主張する。だが米政府の予算は削れない「聖域」が拡大している。
マスク氏登用も財政再建は難路 トランプ政権の弱点にhttps://t.co/qcnszpyiyV
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) November 13, 2024
日本経済新聞の記事によると、2024年度の歳出は6.8兆ドルで、そのうち4割近い計2.5兆ドルは、トランプ氏が削減しないと公約した社会保障費とメディケア(高齢者向け公的医療保険)が占める。
国防費は8500億ドルを占め、与党・共和党内には、中国などの軍備増強に対抗が必要として、予算増額を求める声が根強い。
最近の大きな変化は利払い費の増加だ。新型コロナウイルス対策の財政拡張で債務残高が急に増えたうえ、その後のインフレ対応で金利も上昇した。24年度は8900億ドルと国防費を上回る水準に増えた。
これらの「聖域」を除いた歳出額は2.5兆ドルしかない。もし「聖域」に手を付けないのであれば、この「削りしろ」をほぼすべて削らなければ、マスク氏の主張する2兆ドルの削減は実現できない。
政府効率化省の権限を疑問視する声も少なくない。政府効率化省は省と名乗っていても事実上はトランプ大統領への助言機関であって、直接の権限はない。
過去にも同様の組織はあった。日経の別の記事が指摘するように、1982年、レーガン大統領が諮問した行革組織「グレース委員会」は、150人を超えるビジネスリーダーらで構成し、2500を超える勧告を含む最終報告書を84年に提出した。レーガン政権は財政赤字に直面していたが、そのほとんどが実行されなかった。
米経済評論家ピーター・シフ氏は先月、X(旧ツイッター)への投稿で「DOGEは本当の省庁ではない。政府の外にあり、何もする権限はない。すでに存在する数多くの独立系シンクタンクと同様に、望む勧告を自由に行うことができるが、政府はそれをすべて無視する自由がある」と指摘したうえで、「トランプ政権が実際にDOGEの勧告のいくつかを提案したとしても、議会が可決しない限り、それは何の意味もないし、可決もされないだろう」と厳しい見通しを示した。
損益計算が存在しない
さらに根本的な問題がある。「政府効率化省」の名が示すように、政府をまるで企業のように「効率化」することは、そもそも可能なのだろうか。
効率化には何らかの基準が必要だ。企業の場合、それは損益によって判断できる。ある部門の採算が赤字で、将来も黒字に転じる見込みがないなら、リストラの対象になりうる。
しかし政府は違う。効率性を測る物差しがないのだ。
たとえば、トランプ氏は1期目在任中の手柄話として、大統領専用機「エアフォースワン」の値段が高いとして、製造元のボーイング社と交渉し、値引きさせたというエピソードを語る。そこだけ見ればたしかに税金の節約だ。しかし、そもそもボーイング製以外の選択肢はなかったのかという疑問があるし、小さな機種にして、もっと安くできなかったのかという問題もある。逆に、大きな機種にしたほうが仕事の能率が上がり、他の部分でコストを節約できるかもしれない。
様々な選択肢の中で、どのようなコストとリターンの組み合わせが最も効率的かは、企業なら損益によって判断できる。けれども政府は、このエアフォースワンの例でわかるように、効率性を客観的に判断できない。損益の計算が存在しないからだ。
実際、マスク氏は11月の大統領選投票日の直前、司会者ジョー・ローガン氏のポッドキャスト番組に出演した際、DOGEが官僚の業績を判断する方法について説明しなかった。客観的な基準がないのだから、説明できないのも無理はない。
一般市民は官僚組織の運営を自分になじみのある企業と比較し、官僚組織の無駄や非効率に気づき、「なぜ民間企業のやり方を採用しないのか」と批判する。だがそのような批判は的外れだと、経済学者ルートヴィヒ・フォン・ミーゼスは著書『官僚制』(1944年)で指摘する。「政府と営利企業の根本的な違いを認識していない」からだ。
ミーゼスはこう説明する。一般市民が行政機関の欠陥と呼ぶものは、必要な特性なのだ。官庁は営利企業ではない。いかなる損益計算も利用できない。「企業の運営と比較して政府の効率性を判断するのは誤りである」
だから「政府の部門の長に実業家を任命することで官僚制改革を主張しても、無駄なことである」とミーゼスは続ける。起業家としての資質は、市場社会の枠組みの中でこそ発揮される。「政府機関の責任者に任命された元起業家は、もはや実業家ではなく官僚である。彼の目的はもはや利益ではなく、規則や規制の順守になる」
ミーゼスはこのように、すでに80年前に、起業家が政府を効率化できるというマスク氏の考えを真っ向から批判している。官僚組織が例外なく非効率なお役所仕事になってしまうのは、消費者ではなく、選挙で選ばれた大臣に従属しているからだ。損益の基準ではなく、細かな規則、予算の制約、外部からの監視に従わなければならないからだ。たとえその結果生じる精神が、コスト削減や新技術の導入といった大胆な起業家精神とはまったく相容れないものになったとしてもである。
政府と企業はその行動原理がまったく異なる。極端な話、民間企業にとっては損失や倒産を招くような失敗でも、政府にとってはむしろ予算増につながる成功となる。米シンクタンク、ミーゼス研究所所長のトーマス・ディロレンゾ氏は「米航空宇宙局(NASA)がスペースシャトルを爆発させた(1986年の事故の)翌年度、予算は50%増えた」と指摘する。同氏がいうように、「政府では、失敗は成功」なのだ。
そうだとすれば、無駄でお粗末な仕事を作り続ける官僚を、無能呼ばわりするのは間違っている。官僚はそのような仕事を通じて、予算を増やし、政府の規模や権限を大きくすることに成功しているからだ。その意味において、政府は非常に効率的といえる。
「賢い支出」でなく歳出削減を
メディアではよく、政府に「賢い支出」を求める。日経は先月の社説で、政府が閣議決定した巨額の経済対策について「財源を国債の増発に頼る公算が大きい。どれだけの効果を期待できるかもみえない」と批判し、「次の成長につなげる「賢い支出」からほど遠いのは残念だ」と嘆いた。
[社説]これほど巨額の経済対策は必要なのかhttps://t.co/FU0d3GHM5w
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) November 22, 2024
批判は正しいものの、すでに述べたように、政府自身に無駄な支出を減らすインセンティブ(動機)はないのだから、「賢い支出」を期待しても無理だ。
求めるべきは、何が「賢い支出」なのかを政府に判断させるのではなく、有権者・納税者の圧力によって支出そのものを大胆に削減し、小さな政府にすることだ。その際、財政法を厳格に守らせるなどして、赤字国債という逃げ道をふさいでおく必要がある。そうしなければ、税負担がインフレに形を変えるだけになってしまう。
マスク氏の政府効率化省がどれだけ実績を上げることができるかは未知数だが、「無駄な支出ランキング」などの取り組みを通じて歳出の様々な無駄を白日の下にさらすことで、納税者の怒りに火をつけ、意識変革を促す効果はあるはずだ。それは小さな政府実現の原動力になる。
「ドージ(Doge)」は「犬(Dog)」を意味するスラングで、インターネットミーム(ネット上の面白ネタ)として話題になった柴犬を由来としている。ここから「ビットコイン」をまねてジョークとして作られた暗号資産(仮想通貨)がドージコインで、マスク氏が愛好することで知られる。同氏のトランプ政権入りにより、ついに政府効率化省の略称にまで出世したわけだ。
DOGEが優れた嗅覚を発揮して、米政府の無駄を暴くことを期待しよう。もともと柴犬だし、ぜひ日本にも登場してほしい。政府の支出を減らさない限り、その負担は必ず税やインフレなど何らかの形で市民の背中にのしかかる。