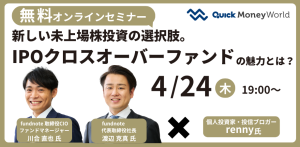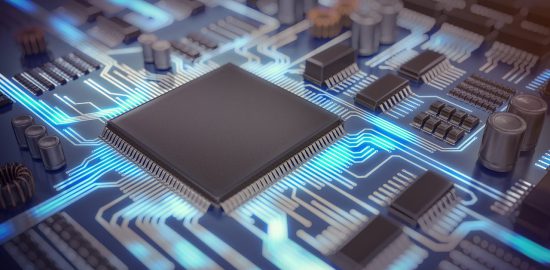【QUICK解説委員長 木村貴】先日放送されたNHKスペシャル「密着 “国債発行チーム”」は大きな話題になった。番組を見た人の多くは、日本の財政がいかに危うい状況にあるかを知って驚き、不安を抱いたことだろう。そう感じるのはもっともだ。けれども、そこから単純に「財政破綻を何としてでも防がなければ」と思い込んだとしたら、いったん立ち止まる必要がある。
#未完のバトン 第1回
— NHKスペシャル(日)夜9時 (@nhk_n_sp) April 13, 2025
密着 “国債発行チーム”
👇NHKプラス見逃しはこちらからhttps://t.co/FJUI4Ve5v7
👆配信 20(日)まで
再放送 17(木)午前0時35分(水曜深夜)[総合] #NHKスペシャル
なぜなら、財政破綻はたしかに深刻な事態だが、それでも経済や暮らしにとって、最悪の事態とは限らないからだ。もっと恐ろしいものはほかにある。番組を注意深く見ていけば、それが何であるか、わかるはずだ。
以下、ヒントとなる映像や発言をたどりながら、「財政破綻より怖いもの」を明らかにしていこう。
「公共サービス」の現実
番組の冒頭、教育や福祉、医療のイメージ映像に重ね、ナレーターがさりげなくこう語る。「私たちが享受するさまざまな公共サービス。税収と共にこれを支えているのが国債です」。このくだりは、視聴者に2つのことを印象づける。
1つは、政府の提供する教育、福祉、医療などの「公共サービス」はどれもすばらしいもので、私たち国民はその恩恵を心ゆくまで「享受」しているというイメージである。それは現実からはるかに遠い。
多くの人は、政府の統制する教育、福祉、医療といった、市場競争のない「公共サービス」の品質や使い勝手の悪さにうんざりしている。「それでも安いから」「無料だから」とありがたがる幸せな人もいるが、実際には税金や社会保険料などの形で、サービス内容に見合うとは思えない高いコストを社会で負担している。
財政が破綻しないということは、これらの劣悪な「公共サービス」が将来も続くことを意味する。恐ろしいことではないだろうか。
もう1つ印象づけられるのは、「公共サービス」を支えるために、国債は税収とともに、なくてはならない資金調達手段だというイメージである。たしかに、今の現実はそうだ。けれどもその姿は、番組自身が後半で説明する、財政本来のあり方を踏み外している。税収の穴を埋める赤字国債は、本来禁止されているのだ。
国債が税金とともに、まるで両輪のように支出を支える今の財政は異常かつ不健全であり、早く正さなければならない。それには財政破綻も辞さない覚悟が必要だろう。「財政破綻を何としてでも防がなければ」という思い込みにとらわれていては、根本的な改革はできない。
まるで債務奴隷
はるばる中東ドバイの機関投資家に日本国債を売り込みに訪ねた財務省の官僚は、投資家側から日本政府の多額の債務残高について問いただされる。これに対し官僚は、日本の債務の規模は他国に比べて非常に大きいと認めたうえで、「有利な要素もある」として、こう説明する。「企業や家計部門の資産規模が拡大しています。それに加えて債務残高の大部分は国内で保有されています」
この説明を聞いて、投資家側は一応納得したかのように見える。英語で懸命に説明する財務官僚が実直そうな青年だということもあり、思わず「よくがんばりましたね」と拍手を送りたくなるかもしれない。けれども発言の意味をよく考えてみると、怖いことに気づく。
投資家が気にしているのは、日本国債を購入して、無事に利息が支払われ、元本が戻ってくるかどうかだ。その原資は税金である。財務省の官僚が海外投資家に対して「日本国債は大丈夫」と太鼓判を押すとしたら、それは「日本の納税者から税金をきっちり取り立てます」と宣言するに等しい。青年官僚に拍手を送りかけた納税者のあなた、何だか不安な気持ちになってこないだろうか。
家計の資産規模に関する発言には、金融資産への課税を強化する可能性が含まれるかもしれない。債務残高の大部分は国内で保有という発言は、極端な話、いざとなったら終戦直後の財産税のような重い税を国内の富裕層・中間層に課して借金を実質踏み倒し、浮いたお金で海外投資家にはきちんと支払いをするという意味にも取れる。
今すぐそんなことにはならないにしても、納税者にとってあまりいいことはなさそうだ。そして財政が破綻しなければ、国債の利払いのために税金を召し上げられ続ける。まるで債務奴隷だ。しかもその額は、債務増加や金利上昇とともに増えていく。人々の財産がそのような不毛な用途に使われる度合いが高まるほど、日本の生産力は衰え、社会に貧困が広がっていく。恐ろしいことではないだろうか。
「赤字国債は万死に値する」
財務官僚も好んで課税を強化したいわけではないだろう。その背景には、巨額の借金の山を積み上げた、無責任な政治家たちの存在がある。
番組で紹介されるとおり、日本政府は1975年、石油ショック後の景気低迷で急激な税収不足に陥り、自民党政権で蔵相(現財務相)を務めていたのちの首相、大平正芳氏は、戦後禁止されてきた赤字国債の発行に追い込まれる。それでも大平氏は最後まで赤字国債の発行に抵抗した。その根源には戦時中、戦費調達のために大量の国債を発行し、急激なインフレを招いた経験があった。

大平正芳氏
日本経済新聞の記事によれば、大平氏は、借金漬けの国家に未来はないという信念を抱き、しばしば「赤字国債は万死に値する」と口にしたという。真の保守と呼ぶにふさわしい、健全な経済感覚だろう。
ところが今の政治家には、保守政党のはずの与党にも大平氏のような健全な考えは皆無に等しい。予算の大盤振る舞いを続け、赤字国債を本気で減らそうとする努力すら感じられない。一部の野党政治家は、消費減税の財源として「ちゅうちょなく赤字国債を発行したらいい」(国民民主党の玉木雄一郎代表)などと主張する始末だ。
減税は個人の財産権の尊重であり、本来はよいことだ。しかし、その財源が赤字国債ならば、インフレという別の形の税がのしかかる。減税の財源が増税ではシャレにならない。
失われた経済常識
東京・霞が関の財務省前で「財務省解体」を唱えるデモに加わった評論家が、「日本が財政破綻することなどない」と叫ぶ姿が、映し出された。彼もその主張に賛同する人々も、財政破綻しないのは良いことだと信じている。その発想は、自分たちが敵とみなす財務省と大差ない。
政府が放漫財政にもかかわらず破綻しないのは、そのツケを増税やインフレで市民に押しつけるからだ。喜ばしいことではまったくない。
日本の政治家も市民の多くも、健全な経済常識を失ってしまった。その一因は、良くも悪くもわかりやすい税金を避け、ごまかしのきく国債に長年頼ってきたことにある。国債頼みの財政が破綻しない限り、日本人の経済感覚は狂ったままだろう。それは未来の日本にとって、恐ろしいことではないだろうか。
日本の財政破綻は、現実味に乏しい夢物語ではない。やみくもに恐れるのではなく、経済政策上の選択肢の一つとして冷静に検証しておくべきだろう。破綻しない財政は、財政破綻よりも怖いかもしれないのだから。