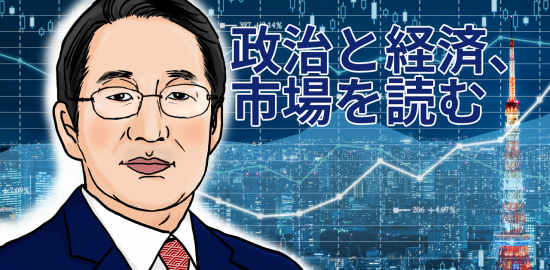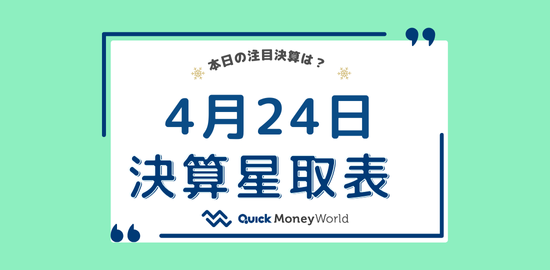【QUICK解説委員長 木村貴】年末、韓国ドラマ「イカゲーム」のシーズン2がネットフリックスで公開され、さっそく楽しんだ。続きが気になるところで終わってしまい、早くもシーズン3が待ち遠しい。
競争社会の縮図?
このドラマは、大金を賭けた命がけのゲーム大会が絶海の孤島でひそかに催され、参加した人々が生き残るために必死の戦いを繰り広げる。タイトルのイカゲームとは、韓国の子供の遊びだ。イカゲーム以外にも「だるまさんが転んだ」など、本来はのどかなはずの遊びが、血生臭い殺人ゲームと化すギャップが衝撃的で、見どころの1つとなっている。
12月26日より世界独占配信⚡️
— Netflix Japan | ネットフリックス (@NetflixJP) November 26, 2024
Netflixシリーズ『#イカゲーム』シーズン2
キービジュアルも公開!
メリーゴーラウンドのような新たなゲームにも注目🎠
全てが”イカしていて”、圧倒的に”イカれている”新シーズンのゲームスタートは間もなく👀#イカれたゲーム #イカゲーム2 #SquidGame pic.twitter.com/n0pwCHLHzQ
ところでこのドラマは、2022年にシーズン1が米エミー賞で6冠に輝くなど世界で高く評価されて以来、各種のレビューで、ちょっと気になるほめられ方をしてきた。「現代の資本主義社会を鋭く批判している」という称賛だ。
たとえば、シーズン2について最近書かれたGQ JAPANの記事は、ストーリーとキャラクターをていねいに紹介した後で、ドラマの解釈をこう述べている。
「我々が生きる資本主義社会は、全員に開かれた競争社会でもあるが、お金がお金を生む社会でもある。はじめから多くを手にするものはそれを元にさらに大きな資産を築くことが可能だが、持たざる者が富を得るためには、厳しく激しい競争を潜り抜け、さらに強運も味方にする必要がある。イカゲームはそんな現代の競争社会の縮図だ」
イカゲームを資本主義に結びつけて論じた、典型的なレビューの1つといえる。この記事はまだ抑制が利いているけれども、ネットで検索すれば、もっと大仰な表現が多く見つかる。「資本主義社会における格差と搾取を鋭く描き出した」「競争と独占の悪循環の資本主義的世界観」「世界全体が資本主義のゲームにのみ込まれ、もはや逃げ場がないことを常に突き付けてくる」といった調子だ。
たしかに、このドラマには、そうした感想を抱きたくなる要素はある。ゲームにしろ、競争にしろ、一部の勝者がお金を独り占めする様子にしろ、そしてその争いをガラス越しに見て楽しむ金持ちたちにしろ、資本主義のよくあるイメージに結びつきやすい。
けれども、ドラマで描かれた恐ろしいゲーム大会は、本当に資本主義の縮図になっているだろうか。よく考えてみると、まったく違う。
やめられる自由
イカゲームのゲーム大会が実際の資本主義社会と異なる点は、少なくとも2つある(以下、ドラマの内容に触れた部分があります)。
まず、やめる自由がない。たしかに、ゲームへの参加は、それぞれの参加者の自由意志に基づく。とくにシーズン2では、勝ち残った参加者が次のゲームに進むかどうかは、その都度自分たちの投票によって決定される。不参加が過半数となったら、その時点での賞金を分配してゲームを終了し、家に帰ることができる。
けれども、もっとお金を得ようとゲーム続行を希望する人が過半数となったら、参加したくない人もゲームを続けなければならない。逃げれば射殺される。個人にやめる自由はないのだ。
経済が自由な資本主義社会では、ある会社の労働環境がきつすぎたり、報酬が働きに見合わないと思ったりしたら、やめることができる。日本の場合、一度やめると再就職が難しいのでやめにくいという問題はあるものの、それは正社員の解雇規制などで労働市場が硬直化し、人を雇いにくいからだ。つまり、資本主義が悪いのではなく、資本主義が不完全なところに原因がある。いずれにせよ、辞表を出しても、イカゲームと違い、銃を持った兵士から追いかけられる心配はない。
消費者に恩恵
もう1つの相違点は、さらに重要だ。イカゲームがゼロサムゲームであるのに対し、資本主義はそうではない。
ゼロサムとは、合計するとゼロになることを意味する。言い換えれば、一方の利益が他方の損失になることだ。ゼロサムゲームとは、そのような性質のゲームを指す。
イカゲームでは、天井に吊り下げられた巨大な豚の貯金箱に注がれる賞金の総額は、あらかじめ決まっている。それを参加者で奪い合う。誰かがお金を得れば、他の誰かが失う。まさにゼロサムゲームだ。
一方、資本主義はゼロサムではない。たとえば、近代資本主義が発展した産業革命以来の200年で、人々の暮らしは急速に豊かになった。200年前、世界人口の80%以上が極度の貧困の中で暮らしていた。今日、その比率は9%未満だ。とりわけグローバル資本主義が拡大した1980年代以降、貧困削減のペースは大幅に加速している。
資本主義によって、個人によるばらつきはあったにしても、全体としてみれば経済的に得をしたといっていい。このように参加者の利得の合計がプラスになるゲームのことを、プラスサムゲームという。資本主義はプラスサムゲームだ。
人は資本主義というゲームについて考えるとき、企業という参加者に目を奪われやすい。しかし、参加者には消費者もいることを忘れてはならない。企業間の競争によって、「持たざる者」である消費者も、品質が高く、価格の安い製品・サービスという富を手に入れる。
マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏、アマゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス氏らの巨万の富は、資本主義が生み出す格差の象徴として非難されやすい。けれども起業家たちの富は、消費者に提供した製品・サービスの価値と引き換えに得たものだ。
言い換えれば、消費者は全体としてみれば、便利なパソコンソフトや電子商取引という形で、富豪たちに匹敵するかそれ以上の富を手にしている。売り手と買い手の双方が得をする、これも資本主義のプラスサムゲームだ。
人々の協力関係
このようにイカゲームは逆説的に、資本主義の本質を明らかにする。それは自由なプラスサムゲームだ。一方で、資本主義のキモを正面から語ってもいる。それは人間同士の協力だ。
たとえば、ゲーム大会には団体戦があり、同じチームの参加者たちは勝ち抜くために互いに協力する。5人6脚で進む競技では、歩調をそろえるのはもちろん、めんこやコマ回しといった5種類のゲームをクリアするため、それぞれ得意とするメンバーが任される(実際にはそれほど得意でなく、苦戦してヒヤヒヤさせられる場合もあるが……)。シーズン2のクライマックスでは、それまで対立していたゲーム続行派と終了派が協力し、真の敵であるゲーム運営組織との対決に向かう。
資本主義社会にとっても協力は欠かせない。人々が得意分野に特化し、分業・協力することで、経済の効率を高め、豊かさを築くことができる。
もちろん、それは国内経済に限らず、国際経済でも同様だ。経済に国境は関係ない。国境を越えた人々の協力関係が強くなればなるほど、世界経済は繁栄する。
保護主義にノーを
ところが昨年来、人々のグローバルな協力関係にヒビを入れかねない政治の動きが目立つ。
日本製鉄のUSスチール買収中止命令 バイデン大統領発表https://t.co/GFePJuS9uk
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) January 3, 2025
米国のバイデン大統領は日本製鉄によるUSスチールの買収計画を阻止すると表明した。「タリフマン(関税男)」を自称する同国のトランプ次期大統領は中国に60%、それ以外の国にも10〜20%の関税をかけると公言している。
海外投資や国際貿易は、国境を越えた商取引という協力関係だ。政府が国内産業や労働者の保護を口実に妨害すれば、保護される側が得をし、消費者が犠牲になるゼロサムゲームに陥る。
政治が押しつける保護主義というゼロサムゲームにノーを突きつけ、自由な資本主義のプラスサムゲームを守れるか。これがイカゲームから読み取れる、2025年世界経済のカギだろう。