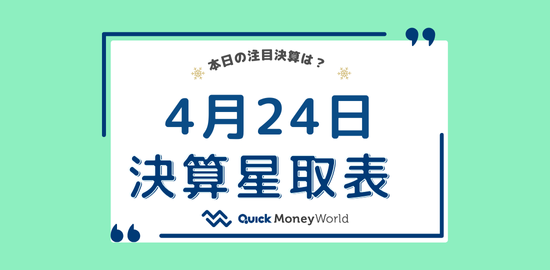【QUICK解説委員長 木村貴】突然ですが、ダイヤモンドの値段はなぜ、水よりも高いのでしょうか。水は人間の生存にとって欠かすことができません。それに対しダイヤはそれほど必要ではありません。それなのに、ダイヤは水よりもはるかに高価です。

いったい、どうしてなのでしょう。今回は、この「謎」について考えてみましょう。
価値は2種類?
人間の生存にとって不可欠の水が、それほど必要でないダイヤに比べて安価であるという「謎」は、水とダイヤモンドのパラドックス(逆説)と呼ばれます。このパラドックスが注目された歴史は古く、少なくとも、近代経済学の父といわれる、18世紀イギリスのアダム・スミスにさかのぼります。
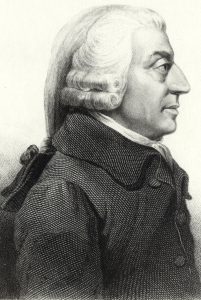
アダム・スミス(Wikimedia Commons)
スミスは有名な著作『国富論』の中で、このパラドックスに次のように言及しています。
「水ほど有用なものはないが、それで何かを購入できること――それと交換に入手できるものがあること――は、ほとんどない。これに反して、ダイヤモンドは使用価値などほとんどもたないが、それと交換に、きわめて多量の他財を入手できることが少なくないのである」(高哲男訳)
スミスは、このパラドックスをどのように説明したのでしょうか。いま引用した文章の直前で、スミスは、価値という言葉には2つの異なった意味があると主張しています。
1つは、あるものの「効用」を指す場合です。効用とは、個人が財(商品)やサービスを消費することによって得ることができる満足のことです。この意味での価値を、スミスは「使用価値」と呼びます。もう1つは、あるもので他の財を購入する力のことです。この意味での価値を、スミスは「交換価値」と呼びます。
ものの価値には、使用価値と交換価値という2種類の価値があるというわけです。そしてスミスによれば、使用価値と交換価値は互いに食い違うことがよくあるといいます。また引用しましょう。
「最大の使用価値をもつものが、交換価値をほとんど、あるいはまったくもたない、ということも少なくない。逆に、最大の交換価値をもつものであっても、使用価値をほとんど、あるいはまったくもたないことが少なくない」
この後スミスは、水とダイヤのたとえを持ち出します。これまでの説明に当てはめれば、水の使用価値は大きいけれども、交換価値はほとんどない。これに対し、ダイヤの使用価値はほとんどないけれども、交換価値は大きい――となるでしょう。
さて、あなたはこの説明に納得できたでしょうか。
わずかな1単位
スミスの説明には問題があります。それは、水の使用価値はダイヤよりも大きいというとき、世の中に存在する「すべての水」と「すべてのダイヤ」を比べてしまっている点です。
もしある日、宇宙人が地球を征服し、あなたに向かって「この星のすべての水か、すべてのダイヤかの、どちらかだけ残してやる。どちらを選ぶ?」と問い詰めたら、どう答えますか。ダイヤに未練はあるかもしれませんが、生き延びるために、やはり水を選ぶことでしょう。この場面においては、水はダイヤより価値があるといって間違いではありません。
けれども普通は、こんな途方もない選択を迫られることはありません。たとえば、1リットルの水と1粒のダイヤというように、全体からみたらわずかな量どうしを比べて、自分にとって価値が高いと思うほうを選ぶものです。
これは、1リットルの水に価値がないといっているわけではありません。1リットルの水は、飲んだり、顔を洗ったり、料理を作ったりするのに役に立ちます。つまり「効用」があります。その意味で価値があります。
しかし、それを他の商品、たとえば1粒のダイヤと比べ、どちらかを選ばなければならない場合には、自分にとって、どちらの価値がより大きいかという判断をしなければなりません。
そのとき、「水は人間の生存に欠かせないが、ダイヤはそうではない。だから水のほうが価値が大きい。だから水を選ぶ」と考えるのは間違いですし、実際、そんな風に考える人はいないでしょう。
なぜかといえば、繰り返しになりますが、人が日常生活で複数のものから1つを選ぶとき、それぞれのもの全体の効用ではなく、1粒、1杯、1本、1箱といった、全体からみればわずかな「1単位」あたりの効用を比較するからです。
この1単位あたりの効用を、経済学では「限界効用」といいます。「限界」という言葉がわかりにくいですね。英語では「Marginal(マージナル)」で、「わずかな」という意味です。限界効用とは、あるもの全体から得られる効用ではなく、あるものの供給をわずかに1単位増やしたときに得られる効用だと覚えましょう。
価値判断は現場で起きる!
限界効用について、理解できたでしょうか。「ダイヤは水よりなぜ高い?」という疑問を解くためには、ダイヤ全体と水全体の効用を比べてはいけません。ダイヤと水、それぞれの限界効用を比べるのです。
そうすれば、アダム・スミスのように使用価値、交換価値という2種類の価値を、苦しまぎれにひねり出す必要はありません。日常生活ではほとんどの人にとって、ダイヤ1粒から得られる限界効用(満足感)のほうが、水1リットルから得られる限界効用(満足感)よりも大きいから、ダイヤを求める人が多くなり、その結果、交換する価値、つまり価格が高くなるのです。
もちろん、つねにそうだとは限りません。特殊な条件の下では変わります。たとえば、あなたが何日も砂漠をさまよい、のどが乾いて今にも死にそうになったとき、目の前にペットボトルを手にした魔神が現れ、「お前の指にはめたダイヤの指輪をくれるなら、この水をやろう」と取引を持ちかけられたなら、たとえ大切な指輪でも、命には代えられないとして、手放すことでしょう。
人間が日常生活で価値判断をするとき、たとえば水とダイヤの価値を比べるとき、人類にとって水とダイヤのどちらがより重要かを決定するわけではありません。そういう頭でっかちな議論のためではなく、目の前の選択をするために判断するにすぎません。
「事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ」。映画版『踊る大捜査線』で叫ばれるこの有名なセリフは、経済学で扱う価値判断に通じるものがあります。経済学は、物質の絶対的価値について延々と戦わされる哲学的な議論に関心はありません。日常生活という現場で、絶え間なく分かれ道に立たされ、選択を繰り返す、生きる人間の価値判断に注目するのです。
ぜいたくは敵だ?
ダイヤモンドは飲んだり食べたりすることこそできませんが、美しいジュエリーとして使うことができます。それなのに、なぜアダム・スミスは、ダイヤに使用価値はほとんどないと強調したのでしょうか。その背景には、ある宗教思想の影響があったとの見方があります。それはカルヴァン主義です。

カルヴァン(Wikimedia Commons)
カルヴァン主義とは、ヨーロッパ各地に影響を及ぼしたキリスト教プロテスタントの神学者カルヴァンの思想です。勤労を重んじ蓄財を容認する一方で、禁欲を重視し、娯楽や賭け事を禁止しました。
アダム・スミス自身の信仰がどのようなものだったかについては議論がありますが、少なくとも洗礼を受けたプロテスタントであり、出身地のスコットランドはカルヴァン主義が盛んな土地でした。スミスの周辺には熱心なカルヴァン主義者がいました。
その影響とみられる、禁欲を重んじ、娯楽やぜいたくを非難する口ぶりが、『国富論』には目立ちます。
たとえば、経済学者マレー・ロスバードが指摘するように、「音楽と踊りはほとんどすべての未開な国民の娯楽」だと決めつけていますし、「女性のぜいたくは(略)つねに子を産む力を弱め、しばしばそれを完全に消滅させてしまう」とも書いています。
また、ぜいたく品の輸送に通常よりも高い通行料をかけることで、「金持ちの不精や虚栄心が、貧乏な人々を救う」と述べています。さらに「貴金属の食器は、虚栄心と見栄から増加する」し、同じ理由から「金や銀の彫像、絵画やその他すべてのぜいたく品や珍奇な物」も増えると書いています。
ダイヤに使用価値はほとんどないという主張は、こうした気難しい禁欲主義の延長線上にあると考えるのが自然でしょう。
ダイヤをさげすむようなスミスの主張に、今でも多くの人が納得してしまうのは、心の中に、スミスと同じような、金持ちに対する反感や嫉妬があるからかもしれません。
けれども、「ぜいたくは敵だ」という日本の戦時中の標語を思い出すまでもなく、そのようなあまり生産的でない感情は、寛容な社会や魅力ある文化、経済の繁栄にとって、決してプラスにはならないでしょう。