【QUICK解説委員長 木村貴】人生は選択の連続です。誰もが日々、大小さまざまな選択に直面し、限られた条件の下で、自分に最大限有利になるように、選択肢のどれかを選び取っています。その仕組みはどうなっているのでしょうか。経済学で考えてみましょう。
目的の優先順位
人間は誰しも、より幸せになろうとして、あるいは少なくとも、より不幸せでなくなろうとして、行動します。そして、その目的を果たすための手段として、最も役立つ物を手に入れようとします。
しかし、それらの物はタダで無限に手に入るわけではありません。空気や日光などを除けば、世の中の物はすべて希少、つまり有限だからです。そのため、何らかの代償(コスト)と引き換えに手に入れなければなりません。
また通常、目的は一つではなく、複数あるでしょう。このため、それらの優先順位を考える必要があります。例を使って説明しましょう。

ある小さな村に、パン屋の太郎という人がいたとします。この村にはお金がなく、太郎は欲しい物やサービスを手に入れるために、パンをお金代わりに使います。
ある日、太郎はパンを5個焼きました。パンはすべて同じ種類、同じ大きさ、同じ品質だとします。太郎は5個のパンの使い道を考えます。
最初のパンは、最も急を要する目的のために使います。働いてすいたお腹を満たすため、自分で食べることにしました。
次のパンは、2番目に急を要する目的のために使います。新鮮なトマトを1個手に入れて食べることです。さいわい、トマト農家と相談がまとまり、パン1個と交換してもらうことができました。
3番目のパンは、その次に急ぐ目的のために使います。1杯のコーヒーをいれてもらって、ゆったりと飲むことです。村のはずれにあるカフェを訪ね、パン1個でコーヒーをいれてもらうことができました。
4番目のパンは、かなり優先順位が下がりましたが、その次に急ぐ目的のために使います。新しいシャツを手に入れることです。洋品店に行き、パンと引き換えに1枚買うことができました。
最後の5個目のパンは、今の太郎にとって、最も急がない目的に使います。野鳥にエサとしてあげることです。パンをちぎってまくと、鳥たちがうれしそうに寄ってきました。
ここまでで、太郎の考える、目的の優先順位とパンの割り当てがわかりました。ここから、さらに深く考えてみましょう。
限界効用の法則とは
太郎の5個のパンはどれも、同じ種類、同じ大きさ、同じ品質だったことを思い出してください。つまり、コストとして払ったパンはすべて同じものです。けれども、それによって得た満足感、経済学の用語でいうと、効用の大きさは、それぞれ違います。
太郎のパンの使い道
| パ ン | 目 的 | 満足感(効用) |
| 1個目 | 自分で食べる | 大 |
| 2個目 | トマトと交換 | ⇩ |
| 3個目 | コーヒーと交換 | ⇩ |
| 4個目 | シャツと交換 | ⇩ |
| 5個目 | 鳥にやる | 小 |
1番大きな効用は、最初のパンから得ました。すいたお腹が満たされたという効用です。2番目に大きな効用は、2番目のパンからです。トマトと交換し、食べることができました。3番目に大きな効用は3番目のパンからで、コーヒーを飲んでくつろげました。4番目に大きな効用は4番目のパンからで、シャツを手に入れました。そして1番小さな効用は5番目のパンからで、野鳥にエサをやることができました。
パンが1個増えるごとに、新たな効用を得ています。このように、ある物の供給を1単位増やしたときに得られる効用を、前回のコラムで説明したように、「限界効用」といいます。
そして太郎の例でわかるように、ある物の供給が1単位増えるたびに得られる新たな効用(限界効用)の大きさは、順を追って、しだいに小さくなります。優先順位が低いのですから、当然です。これを「限界効用逓減の法則」と呼びます。「逓減」とは見慣れない言葉ですが、「しだいに減る」という意味です。
逆に、ある物の供給を1単位ずつ減らせば、そのたびに、最も優先順位の低い目的から得られる限界効用は大きくなっていきます。
たとえば、太郎が4個しかパンを焼けなかったら、5番目の目的である鳥のエサやりはできなくなります。残った選択肢のうち、4番目のシャツの優先順位が1番低くなります。シャツから得られる効用は、鳥から得られる効用よりも大きいことを思い出してください。パンの供給が減ることで、最後に満たす目的から得られる限界効用が大きくなります。
まとめると、経済学者マレー・ロスバードが述べるように、ある商品の供給が増えればその限界効用は小さくなり、供給が減れば限界効用は大きくなります。このように、限界効用は小さくなるだけではなく、大きくもなるので、「限界効用逓減の法則」ではなく、単に「限界効用の法則」と呼ぶほうが適切かもしれません。
ご存じのように、ある商品やサービスの供給が増えると、需要に変化がなければ、価格は安くなります。これを「需要供給の法則」といいます。
教科書ではそれ以上、突っ込んで説明しませんが、供給が増えると価格が下がる背景には、限界効用の法則があります。供給が増えると、限界効用、つまり新たに得られる満足感が小さくなるため、安くないと買わなくなくなるのです。
ビールのたとえの誤り
ここで、注意点をいくつか補足しておきましょう。
まず、目的の優先順位は状況によって変化する可能性があります。パン屋の太郎の場合、シャツよりトマトやコーヒーの優先順位が高くなっていましたが、古いシャツが破れて着られなくなってしまったら、シャツの優先順位は高くなるでしょう。
次に、それぞれの目的を果たすことで得られる効用は、どちらが大きいかという順序を言うことはできますが、どれだけ大きいかを数字で示すことはできません。
太郎に向かって「トマトから得られる満足は、コーヒーの何倍か?」と尋ねても、答えることはできないでしょう。太郎だけでなく、誰でもそうです。ステーキよりもお寿司が好きだとは言えても、その差が何パーセント、何倍かを言うことはできません。互いに足したり引いたりすることもできません。
最後に、ネット上の解説などでは、限界効用逓減の法則について、ビールを使ったたとえ話をよく目にします。暑い外で1日中働いた後に飲む1杯目のビールの満足度は非常に高いけれども、2杯目、3杯目、と追加するうちに、だんだんとその満足度は減っていく、というものです。

感覚に訴える説明なので、多くの人が納得しやすいかもしれません。けれども、感覚には個人差があります。1杯目はのどを潤すだけだが、2杯目、3杯目のほうがじっくり味わえるから満足感が大きい、というビール通の人だっているでしょう。これでは、とても「法則」などという大それた呼び方はできません。
それに対し、今回説明した限界効用の法則には、決して個人差や例外はありません。誰であっても、優先順位のランキングが高いものから低いものになるにつれて、新たに得られる満足感(限界効用)は小さくなっていきます。これが、あやふやな感覚や心理ではなく、厳格な論理に裏付けられた、限界効用逓減の本当の意味です。
厳格な論理を重視する「オーストリア学派」の経済学者ミーゼスは、限界効用の法則を証明するために、心理学的推論や議論に訴える必要はない、と強調しています(『ヒューマン・アクション』)。
また、ビールのたとえ話ではよく、しだいに減っていく限界効用を足し合わせ、満足度の総量を計算しようとします。けれども、さきほど述べたように、効用を足し合わせることはできません。1杯目の満足感に比べ、2杯目、3杯目の満足感がどれくらい小さいか、数字で示せる人はいません。そうであるなら、それらを足し合わせることもできません。もちろん、他人と比べることもできません。
ですから、「満足度の総量を大きくしよう!」と考え、あれこれ手を出しても、うまくいかないでしょう。それよりは、自分のさまざまな目的の優先順位を、感覚ではなく理性に基づいて明確にし、その心のランキングを指針として、目の前の選択肢のうち、自分を幸せにしてくれると思うものを1つずつていねいに選んでいく。そのほうが、結果として満足度の大きい人生を送れるはずです。








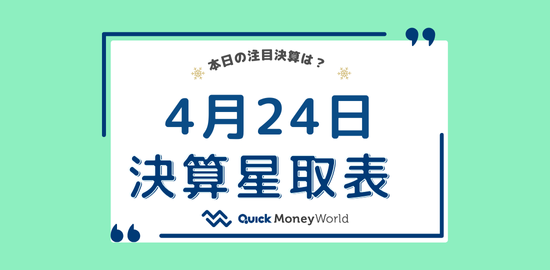










結論の部分ー目的の優先順位を、感覚ではなく理性に基づいて明確にしー人生全般に適合するかどうか。結婚相手を理性に基づいて決めることは多いにありうることと思いますが、恋愛対象を感覚でなく理性に基づいて選択しましたと相手に言ったら相手はどうでるか? 経済学は実り多いい知見を与えてくれますが、その地平の限界は認識しておかないとと思うのですが。