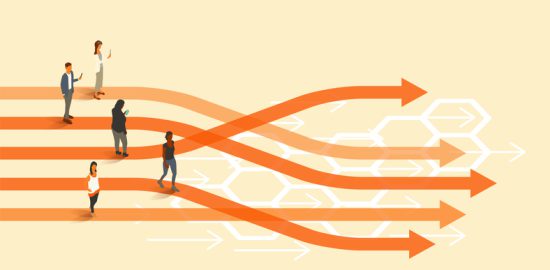米連邦準備理事会(FRB)が金融政策の「限界」に挑む一歩をさらに進めた。景気浮揚のためにゼロ金利政策を長く続ける金融政策の新指針を発表。FRBの政策実現力の高さに信頼を置く、米債券市場では長期金利が上昇(価格は下落)するとともに、償還までの期間が長い債券の利回りがより上昇する「ベアスティープ」が進んだ。
■サプライズ演出
FRBは27日、市場関係者にとって「サプライズ」となる臨時の米連邦公開市場委員会(FOMC)を開き、金融政策の新たな指針を決めた。同時にパウエル議長は米カンザスシティー連銀が開催する国際経済シンポジウム(ジャクソンホール会議)の講演に臨んだ。
新指針の最も重要なポイントは「平均物価目標への政策シフト」(JPモルガンのマイケル・フェローリ氏)だ。政策金利の判断の目安としてきた物価上昇率について「平均して穏やかに2%を上回る水準まで上昇することを許容する」と明記した。一定期間の物価上昇率が2%を上回ることを容認する。つまり物価が2%に到達しても、すぐに金融引き締めに転換しない姿勢を強めた。現時点のFOMCメンバーの見通しに基づけば、ゼロ金利政策は少なくとも23~24年まで続きそうだ。市場ではさらに25年前半まで続くとの見方もある。
■デフレの恐怖が突き動かす
パウエル議長は講演で「インフレ率の低下は極めて深刻なリスクだ」と語り、期待インフレ率の低下を放置する危険性を訴えた。期待インフレ率が低下すると、現実に物価上昇率が下がり、さらに期待インフレ率が低下する。金利が低い状況のなか、期待インフレ率が下がれば、名目金利から期待インフレ率を差し引いた実質金利の上昇が起き、資産価格の下落など経済に悪影響を与える。デフレ化による経済の縮小均衡を経験した日本を反面教師にしているのはほぼ間違いない。
物価上昇のため、個人消費を支える雇用の回復を「広範かつ包括的な目標」(パウエル議長)としたのが次の重要ポイントだ。現実の雇用状況の完全雇用からの下ぶれ分、「shortfall」(不足)を埋めることを重視して、金融政策の方針を決める。これまでは、「deviations」(ずれ)という文言を使い、完全雇用から上下両方のぶれに対応する姿勢を示していた。「雇用の下ぶれへの対応を重視する、非対称的な政策へのシフト」(ゴールドマン・サックスのヤン・ハチウス氏)。下ぶれがなくなるまで、長期の緩和姿勢を続ける。一方、雇用が回復し、(インフレを加速させない失業率である)自然失業率を現実の失業率が下回っても、過去のように拙速な金融引き締めは行わない。
■フィリップス曲線の否定
債券市場は新指針による将来の景気回復と物価上昇に期待を高めた。27日のニューヨーク債券市場で米長期金利の指標である10年物国債利回りは前日比0.06%高い0.75%に上昇。2カ月半ぶりの水準だ。この日は10年以上の期間の長い債券利回りが、短い期間に比べ大きく上昇。2年と10年の利回り格差は0.59%と3カ月ぶりの大きさ。5年と30年は1.20%と前日の1.13%から拡大した。8月に入り、FRBによる金融緩和姿勢の強化期待もあってベアスティープが進んでいたが、この日のFRBの新指針を受け、その動きは一段と広がった。
※27日は短い年限より長い年限の国債利回りが上昇する「ベアスティープ」が進んだ
FRBは失業率が下がると物価上昇率が上がるというフィリップス・カーブ(フィリップス曲線)を完全に否定した。物価上昇を前提とした20世紀後半の経済学では存在感があったフィリップス曲線は、世界経済のグローバル化などを背景に21世紀に入り、存在感は大きく低下した。かねてフィリップス曲線の希薄化を指摘していたパウエル議長はこの日の講演でも「大幅なインフレを招かずに、完全雇用を達成できる」と述べた。過度なインフレが起きた時は利上げをためらわないとしながらも「インフレが長期間続くことはないだろう」とも語った。物価上昇率の管理は可能と強調し、金融緩和の長期化に布石を打った。
一連のFRBの動きは、景気の押し上げに金融緩和の効果は限られるとする「金融政策の非対称性」に対する挑戦にもなる。新型コロナウイルスの流行による経済危機への対応に、過去にみない金融政策のフル活用で限界に挑んだ先はどこに行き着くのか。市場では金融緩和の副作用に対する警戒も根強くある。エバコアISIのデニス・デバッシャー氏は7月以降、金融情報端末で「bubble」(バブル)の検索回数が急激に増えていることを気に掛けていた。(NQNニューヨーク 張間 正義)
<金融用語>
フィリップス曲線とは
失業率をグラフの横軸に、賃金上昇率を縦軸にとって関係を描くと、賃金が上がる(下がる)ほど失業率が下がる(上がる)右肩下がりの曲線が描けることを、1950年代に英経済学者が提唱。その名前を冠した曲線。 縦軸の賃金上昇率に代えて物価上昇率(インフレ率)を取り、横軸の失業率の関係をグラフにすると同様の右肩下がりの曲線になる。中央銀行が景気動向(失業率)を考慮しながら、金融政策でインフレ率をコントロールする際の判断材料として参考にするが、デフレ下でも失業率が増大したり、インフレ化での不況(失業率の増大)というスタグフレーションの場合もあり、右肩下がりのフィリップス曲線では説明がつかない経済事象も起こっている。