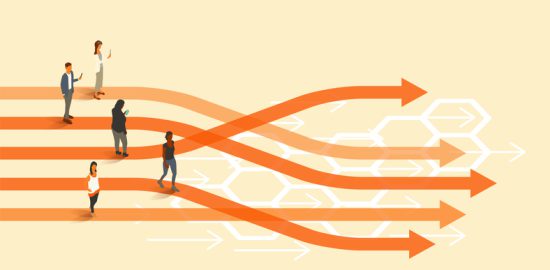【日経QUICKニュース(NQN) 松下隆介】外国為替市場を分析するアナリストの間で、2021年の円相場のじり高を見込む声が増えている。米連邦準備理事会(FRB)の金融緩和策などドル売りの材料に加え、購買力平価でみた円の割安さなど日本独自の円買い要因もあるためだ。運用リスクをとる動きから足元では上昇に一服感が出ているものの、先高観を背景に当面は底堅い展開が続きそうだ。
■1ドル=100円予想
英スタンダードチャータード銀行は21年4~6月期に1ドル=100円ちょうどまで円が上昇した後、年末まで横ばいで推移すると見込む。米ゴールドマン・サックスも向こう12カ月で100円まで上げると予想。シンガポールのユナイテッド・オーバーシーズ銀行(UOB)は21年末にかけて102円までの上昇を想定している。マレーシアのメイバンクも21年末は101円予想だ。

主因はFRBの量的金融緩和策だ。11月13日時点のFRBのバランスシートは2月末と比べ7割強膨らみ、12月の追加緩和観測もある。一方、2割強の拡大にとどまる日銀は当面、政策の現状維持が見込まれる。りそな銀行の武富龍太氏は「FRBが引き締めに向かうのは実体経済の回復を確認してからだろう。ドル売りトレンドは続き、100円を超える円高水準の定着もあり得る」と語る。
米バンク・オブ・アメリカが米大統領選後の11月6~11日に実施した11月の「FX・金利センチメント調査」によると、前回10月と比べ米財政出動の規模を「2兆~2兆5000億ドル」とする回答は大きく減り、「5000億~1兆ドル」の割合が大きく増えた。米金融緩和策に加え、米国の「ねじれ議会」で巨額の財政出動への思惑も後退している。米長期金利の上昇一服がドルを売って円を買う動きを誘いやすい。
円強気派の間では、円の割安さを指摘する声も多い。カナダのBCAリサーチが今週に入りアップデートした購買力平価(PPP)モデルで分析したところ、ドルが13%ほど過大評価され、円は15%ほど安く取引されている、との結果だった。観光需要の減少や通信料金の引き下げなどで「物価上昇率でほかの先進国に後れをとる」といい、100円を目標とした円買い・ドル売りを中核のポートフォリオと位置付けている。
市場では「『ドルを売るなら何を買うのか』という判断のもと、出遅れ感がある円が選ばれるストーリーを描いている」(スタンチャートの江沢福紘氏)との声もあった。米ゴールドマン・サックスは、景気敏感株が多い日本株市場への資金流入を背景とした円買いも円上昇の理由に挙げている。
■105円まで下落?
一方、円の弱気派の論拠として挙げられるのが、運用リスクをとる「リスクオン」の強まりだ。21年末にかけて109円までの円安・ドル高進行を見込む米ウェルズ・ファーゴは、株式相場と金利の世界的な上昇が「低リスク通貨」とされる円への需要を後退させるとみる。ただ、リスクオンが円を大きく押し下げない可能性にも言及する。「円は過去数カ月、歴史的に信頼できる『低リスク通貨』としての特性を示さなかった」ためだという。
夏場以降、米国株が幾度も大幅に調整したにもかかわらず、その間の円相場はおおむね小幅な値動きにとどまった。BCAリサーチは国内勢による積極的な米国債買いを理由に挙げる。米国債やドル資産への資金シフトが、リスク回避時の円買い圧力を弱めたようだ。米モルガン・スタンレーはこうした需要を背景に、年前半までの円高基調から一転し、年後半には105円まで下落すると見込む。
ファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)と需給という2つの要因が入り乱れ、外為相場の先を見通すことは容易でない。ただ、じゃぶじゃぶのドルが市場にあふれ続けるとの見立ては、多くのアナリストが一致する。「ドル安」に焦点があたる中、少なくとも「110円を突破して円安・ドル高が進む」という展開を読む向きは、ほとんどない。