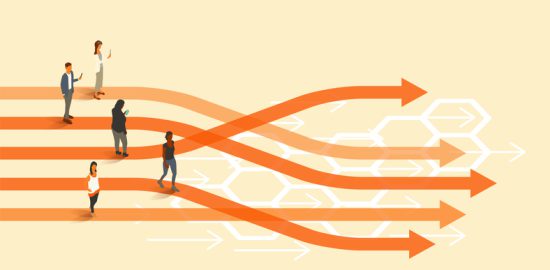【NQNニューヨーク 古江敦子】12月15日のニューヨーク外国為替市場でドルは主要通貨に対して下落し、円に対しては1ドル=103円後半の円高・ドル安で推移した。新型コロナウイルスのワクチン普及などでリスク選好のドル売りが続く。米連邦準備理事会(FRB)が15~16日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で購入国債の年限延長を決めれば、ドルは一段安となる可能性がある。
■「購入国債の年限長期化」決まるのか
FOMCの焦点は量的金融緩和のフォワード・ガイダンスの変更だ。現在の毎月800億ドルの米国債、400億ドルの住宅ローン担保証券(MBS)の購入に関し、声明で「向こう数カ月」続けるとしてきたが、「雇用の最大化と2%超のインフレ目標の達成が展望できるまで続ける」などと結果重視の文言に移行するとみられる。量的緩和の拡充策として注目される「購入国債の年限長期化」を明示するかどうかが注目される。
「現時点で購入国債の年限延長は相場にわずかしか織り込まれていない」(TD証券のマゼン・イッサ氏)と指摘される。経済支援として即効性があるのは金融政策より財政政策とされるうえに、バイデン新政権の発足やワクチン普及による景気見通しへの影響を考慮するために、今回は見送るとの予想が多い。スコシア・キャピタルのショーン・オズボーン氏は「購入国債の年限延長が決まらなければ、想定通りとの安心感からドルは買われる。逆に決まれば、ドル売りが進む」と読む。
一方、スタンダードチャータード銀行のスティーブン・イングランダー氏は「保有国債の年限長期化を決めるだろう」と語る。米国のコロナ感染拡大は深刻化しており、米景気回復の勢いが向こう数カ月で鈍る可能性は高まっている。「追加経済政策が年内に決まっても、失業者数の増加傾向などから景気下振れリスクに早期に対処するだろう」という。
購入国債の年限延長が見送られても、来年の早い時期には決まるとの声は多い。オックスフォード・エコノミクスによると、FRBは今年の新規国債発行分の54%を購入しており、来年も800億ドルペースを維持すれば45%を購入することになる。比率が減る分、より長い年限の国債を購入して緩和効果を維持するという。同社のキャシー・ボスジャンティック氏は「FRBの保有国債の償還年限の平均は7.4年。前回の年限拡張で膨らんだ2011年後半の平均(10.5年)に比べ短く、年限延長に積極的になれる」と指摘した。
■「ドルが買われても、一時的なものだろう」
ニューヨーク連銀による11月のプライマリー・ディーラー調査によると、FRBは2022年上期まで現在の資産購入規模を維持するとの予想が多い。長期的なゼロ金利政策と量的金融緩和を受けて期待インフレが上昇すれば、実質金利をさらに押し下げ、ドル安に拍車がかかりそうだ。
「16日のFOMC結果発表後にドルが買われても、一時的なものだろう」(バノックバーン・グローバル・フォレックスのマーク・チャンドラー氏)と指摘される。FRBのハト派姿勢は続き、長期的なドル安基調は崩れそうにない。
<金融用語>
フォワード・ガイダンスとは
中央銀行(金融政策当局)が将来の金融政策の方針を前もって表明すること。 金利がゼロ近辺まで下がり、伝統的な金融政策である政策金利のコントロールでは対処できないほどの金融危機や景気後退に直面した際などに、中央銀行が行う非伝統的金融政策のひとつ。 声明等を通じて政策金利の据え置き期間や政策変更の条件などを明言し、市場参加者の予想や期待に働きかけることで、金融政策効果の浸透を目指す。 1990年代にゼロ金利政策の下、日本銀行が行った「時間軸政策」が先駆けとなり、米連邦準備理事会(FRB)や英イングランド銀行など、各国の中央銀行で採用されている。