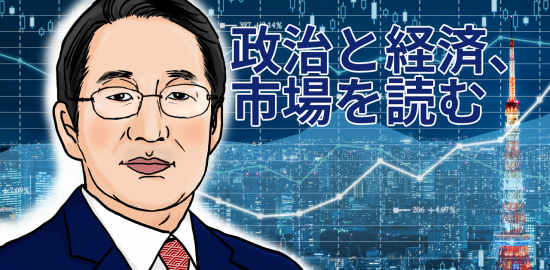【QUICK解説委員長 木村貴】個人の間で金(ゴールド)を購入する動きが広がっている。物価高や円安への懸念が深まる中で、財産の目減りを避けるため、金の価値保存機能が見直された形だ。読者の中にもすでに金を購入した人や、購入を検討している人がいるかもしれない。
実際に世界の歴史上、金は経済恐慌や急激なインフレなど経済危機に陥った際、財産を守る手段として重宝されてきた。しかし、ここで注意しなければならないことがある。政府は危機を口実に、国民が大切に保有する金の没収に踏み切るかもしれない。
それは今からおよそ90年前、実際に起こった。舞台は独裁者が支配する、どこかの小さな国ではない。自由と民主主義を標榜する大国、米国だ。
過激な大統領令
1933年4月5日、当時のフランクリン・ルーズベルト大統領は、大統領令6102号を発した。大統領令とは、米大統領が議会の承認を得ず、連邦政府や軍に対して独断で出すことができる行政命令のことだ。最近ではトランプ大統領が、暗号資産(仮想通貨)を米政府が戦略的に備蓄するための大統領令に署名したことで、話題となった。

ルーズベルト(Wikipedia)
ルーズベルトが発した大統領令の中身は、トランプ大統領よりもはるかに過激で、米国の伝統的なお金のあり方を根本から否定するものだった。米国民に金の所有を禁じたのだ。
具体的には、ジュエリー用、工業用、対外支払い用を除き、金貨、金塊、金証券の私的な所有を禁止した。金証券とは、米財務省が発行した、金との引き換えを保証した兌換証券で、1900年以降、お金として流通していた。
政府はこれらを1トロイオンス20.67ドルの公定価格で強制的に没収した。拒否した場合、1万ドルの罰金か最長10年間の投獄、あるいはその両方の罰が科された。
没収といってもドルと交換だからいいではないか、と思うかもしれない。しかし、そもそも強制であることが問題だし、しかも金や金証券を差し出した代わりにもらえるドルは、金の裏付けがなく、政府によって勝手に価値を引き下げられる恐れがあった。
事実、すぐにそうなった。ルーズベルト政権は翌1934年、金の公定価格を35ドルに引き上げた。逆にいえば、ドルの価値はそれだけ引き下げられたことになる。当時まだドルを金と交換できた外国の中央銀行は、同じ金額のドルで、前より41%少ない量の金しかもらえない計算だ。
金貨などの保有が禁止されたことで、米国内では、金を正式なお金とする金本位制が事実上廃止された。ルーズベルト政権は当時、これはあくまで一時的な措置だと強調したが、結局、金本位制は復活しないまま、現在に至っている。
誤りだったデフレ脱却策
ルーズベルト政権による金の没収は、アメリカ大恐慌から抜け出すための「ニューディール政策」の一環だった。1929年のニューヨーク株暴落をきっかけに始まった大恐慌は、ルーズベルト政権が発足した1933年当時、銀行倒産が相次ぎ、失業率が25%に達するなど最悪の状況にあった。しかし、政府の考えた解決策は間違っていた。
当時、多くの財界人や農家、ブレーントラストと呼ばれるルーズベルト大統領の側近らは、大恐慌を引き起こしたのは物価の下落だと信じていた。だから大恐慌から脱出するには、物価を上げればいいと考えた。今の言葉でいえば、デフレ脱却だ。
そのために、ニューディール政策の柱として、全国産業復興法(NIRA)を制定し、政府の統制のもとで企業に生産や価格の規制をさせたり、農業調整法(AAA)を定め、農民に補償金を払って生産制限をさせ、農産物価格の引き上げをはかったりした。
けれども、個々の商品ではなく、物価全体を押し上げるためには、お金の量を大幅に増やす必要がある。それには金本位制が邪魔になった。金本位制の下では、政府・中央銀行が自由にお金の量を増やせないからだ。そこでルーズベルト大統領は金本位制の廃止を強行したのだ。
これだけ大がかりな政策を動員したにもかかわらず、米国は結局、大恐慌から抜け出すことができなかった。そもそも、物価下落が恐慌を起こしたという最初の診断が間違っていたからだ。米ミーゼス研究所のトーマス・ディロレンゾ所長が指摘するように、因果関係は逆で、恐慌の結果、物価が下落したにすぎない。
恐怖心をあおる
それにしても、当時の米国民はなぜ、大切にしてきた金を、大した抵抗もせず、政府から言われるがままに差し出してしまったのだろう。その背後には、ルーズベルト政権による「非常事態」の演出があった。
ルーズベルト大統領が1933年3月4日に行った就任演説は、「我々が恐怖すべきことはただ1つ、恐怖そのものなのである」という有名な言葉で知られる。続けてルーズベルトは「名状しがたく理不尽で不当な恐怖は、撤退を前進へと転換させるために必要な努力を麻痺させてしまう」と強調した。
ところが演説の残りの部分では、むしろ国民の恐怖心をあおっている。そこで繰り返されるのは、経済危機は戦争に匹敵する非常事態だという考えだ。
さきほど引用した「撤退」「前進」という表現がすでに、戦争用語である。ルーズベルトは、経済危機の原因は「金融業者の悪辣な行為」だとし、金融業者を社会の敵と認定する。これも交戦国の人々を敵として憎むよう仕向ける、戦争を連想させる話の運びだ。また、雇用回復への取り組みは「戦時の非常事態への対処と同様」だと明言した。
さらにルーズベルトは演説の後半で、経済危機への対応を次のように、露骨に戦争にたとえた。
「前進するには、訓練された忠実な軍隊として、共通の規律のために犠牲をいとわず行動せねばならない」
「共通の問題にひたむきに規律をもって挑む国民という、偉大な軍隊の指導者としての地位を、私は躊躇せず受け容れる」
「私は、危機に対処するための唯一残された手段――我が国が外敵に侵略された際に私に与えられるであろう力と同等の、広汎な行政権――を議会に要求する」
最後のくだりでは、盛大な拍手がわき起こったという。巧みな演説に酔い、拍手喝采した人々は、大統領という最高権力者に戦時と同様の強大な権限を与えたら、自分たちの身に何が降りかかってくるか気づかなかった。やがて彼らは金を奪われた。
米エコノミスト、ロバート・ヒッグス氏は、経済危機や戦争が政府権力の拡大に利用される傾向を分析した本で、こう指摘する。
「ルーズベルト政権と議会は、当初から非常事態と戦時のたとえを利用することで、広範囲にわたる政治的行為に対して通常なら立ちはだかる壁を打ち破った」
米国ではすでに、大恐慌が始まった前任のフーバー大統領の任期中から、ジャーナリスト、政治家、社会運動家らが声高に、経済恐慌は非常事態だと叫んでいた。こうした世論をルーズベルト大統領は巧みに利用したといえる。
日本でもあった財産没収
日本政府は終戦直後、一定額を超える財産(現預金、株式などの金融資産および宅地、家屋などの不動産)を対象に「財産税」を課し、富裕層の資産をほぼすべて没収した。戦争で悪化した財政を立て直すためだった。金貨などの貴金属は不動産に比べて隠しやすく、没収を免れたものもあったとみられる。
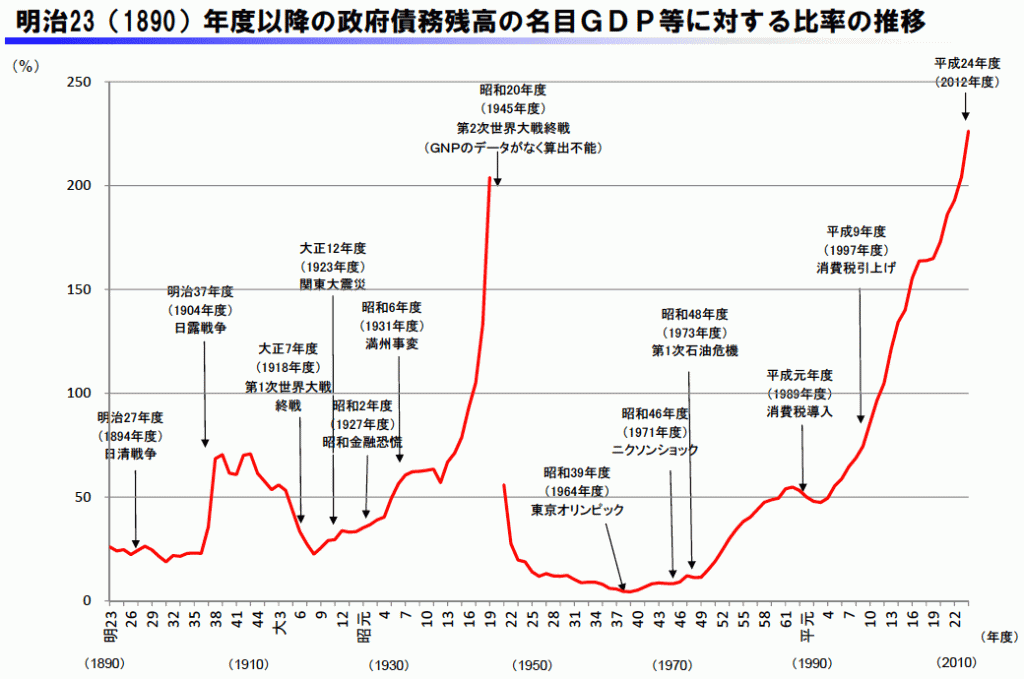
小黒一正氏記事より引用(RIETI)
現在、日本の政府債務は国内総生産(GDP)の2倍を超し、財政は太平洋戦争末期並みに悪化している。万が一、破綻の危機に直面したなら、政府は非常事態を口実に、金など市民の財産を奪う超法規的措置に踏み切らない保証はない。そうした究極のリスクを、頭の片隅に入れておく必要があるかもしれない。