
【QUICK Money World 荒木 朋】日本経済のデフレ脱却や企業の姿勢の変化を期待して、国内株式相場が大きく上昇しています。ダイナミックな相場展開が続くなか、相場全体の変動が自分自身が保有する銘柄の値動きにどう影響するのか、気になる方は多いのではないでしょうか。個別銘柄が市場全体の動きに対してどの程度敏感に反応するかを示すリスク指標として「ベータ(β)値」という数値があります。本記事ではβ値とは何かという基本的なことから、株式投資での活用の仕方やメリットなどについて詳しく解説していきます。
■β値とは? 市場全体と比べた個別銘柄の感応度を示す指標
β値とは、株式市場全体と個別銘柄の相関関係を示す指標で、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)などの株価指数の動きに対して個別銘柄がどれくらい連動したかを示すものです。β値は個別銘柄の投資を判断する際に使えるリスク指標で、その値動きからリスク・リターンを測ることができます。
β値を活用することで、市場全体の値動きが大きくなる局面での相場変動(ボラティリティー)の大きい銘柄や小さい銘柄を判断することができます。そのため、株式相場の状況に応じてより多くの利益を獲得することができる銘柄を発掘する上で、β値の把握は1つの重要なヒントになり得るのです。
■β値の見方は? β値が高い=値動き(リスク)が大きい
β値の見方を解説します。β値は「個別銘柄のリターン÷市場全体(株価指数)のリターン」で表します。β値は1を基準としており、個別銘柄と株価指数の値動きによって数値が変動します。
例えば、ある銘柄が株価指数と同じ値動きをした場合、β値は1となります。これは株価指数が1%上昇(下落)した場合、その個別銘柄の株価も1%上昇(下落)することを意味します。一方、β値が1.5の銘柄の場合、株価指数が上下に1%動くとその銘柄の株価は上下1.5%動くということです。β値が0.5の場合は株価指数上下1%の動きに対してその銘柄の株価は上下0.5%の動きになります。
β値が高いということはその銘柄の値動きが大きいことを示すため、相場変動に対するリスクが高くなることを意味します。逆にβ値が低い銘柄は値動きが緩やかであるため、価格変動リスクは小さいということを表しているのです。
■β値から見えるもの・傾向とは?
β値は個別銘柄の価格変動リスクを測るのにとても参考になる指標といえます。β値の見方でも示した通り、β値が1の銘柄は市場全体(株価指数)と同程度のリスク、2の銘柄は株価指数と比べて2倍のリスク、0.5の場合は対株価指数で半分程度のリスクであることを意味します。
そのため、個別銘柄のβ値を見ればリスク・リターンの判断材料として役に立ちます。β値が高いほどハイリスク・ハイリターン、低いほどローリスク・ローリターンとなります。大きな利益を狙う場合はβ値が高い銘柄に投資し、手堅い利益を狙う場合はβ値の低い銘柄を選択すればよいというわけです。
β値は個別銘柄によって大きな違いがあるため、同じセクター内でも一律とはなりませんが、一般的には電機や鉄鋼、金融など景気敏感株とされる業種はβ値が高くなる傾向があり、食品や通信、医薬品などディフェンシブ株とされる業種はβ値が低くなる傾向にあるとされています。
また、同業種の中でも業界の上位に位置する企業(銘柄)はβ値が低く、中堅・下位の企業(銘柄)はβ値が高くなる傾向があるようです。
■日経平均採用銘柄のβ値は? 電気機器など高く、食料品などが低い
東京証券取引所に上場している企業の多くはβ値が0~1.5程度の範囲内に収まっているとされています。
QUICKの金融情報端末「Qr1」を利用して、2023年3月下旬時点の日経平均株価採用銘柄のβ値(対日経平均、期間6カ月)を調べたところ、β値が高いランキング上位5位にはミネベアミツミや東京エレクトロン、エムスリー、SMC、キーエンスが入りました。業種別では「電気機器」が多くを占め、次に「機械」が続きました。
一方、β値が低いランキング上位5位には高島屋、ニチレイ、明治HD、日本ハム、日清製粉Gが入りました。業種別では「食料品」「陸運」「電気・ガス」が上位に顔を並べました。
先ほども説明した通り、電機などの景気敏感株はβ値が相対的に高く、食品などのディフェンシブ株はβ値が相対的に低いことが分かります。
QUICK Money Worldの中には、会員登録しなければ読めない記事がいくつかあります。ご興味がある方は無料会員登録をしてみてはいかがでしょうか。無料会員になることで、会員限定記事の閲覧や会員限定イベントの参加、お気に入り銘柄登録、クリップ機能、ユーザーフォロー、いいね・コメントなどのサービスが利用可能になります。会員登録については、メールアドレスの登録だけでなく、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。⇒無料会員について詳しく
■β値を投資に活用する方法、そのメリットとは?
β値を株式投資にどのように活用すればいいでしょうか。これまでの説明で分かる通り、β値の高い銘柄はリスクが大きいものの、その分、大きなリターンを得られる可能性が高い銘柄といえます。例えばβ値が1.5の銘柄は株価指数が10%上昇するとその銘柄の株価は15%上昇する可能性があるということです。上昇相場の局面でβ値の高い銘柄を選んで投資すれば、市場平均以上の大きなリターンが期待できるでしょう。もちろん、相場の下落局面でもリスクが高くなりますが、その際は信用取引を利用した空売りにより収益を獲得することが可能になります。
β値を利用した投資戦略では分散投資におけるリスク低減にも活用できます。仮に買いポジションのみで構成する投資手法(ロングオンリー)の場合でも、β値が高い銘柄と低い銘柄を保有することで株価下落のリスクを低減する1つの手段になり得ます。ポートフォリオに景気敏感株とディフェンシブ株の両方を保有するのが一例です。相場の先行き不透明感が強い局面ではβ値の低いディフェンシブ株を多めに保有すれば、相場下落リスクの低減につながります。
リスク許容度を意識して投資する際もβ値は活用できます。リスクを取ってでも大きいリターンを狙いたい場合はβ値の高い銘柄に多く投資し、反対にリスクをなるべく取らずに手堅く利益を狙いたい場合はβ値の低い銘柄を多く組み入れるといいでしょう。
■β値活用における注意点を整理!
最後にβ値を投資に活用する際に注意すべき点を整理しておきましょう。
β値は市場全体(株価指数)に対する個別銘柄のリスクとリターンの大きさを示した指標です。β値が高い銘柄はリターンが大きい半面、その分リスクも大きくなります。つまり、相場の下落局面では株価指数の下落以上に株価が大きく下げるリスクがあるというわけです。β値が高いと相場下落時の影響も大きいだけに、損切りの水準をあらかじめ決めておくなどリスク管理をしっかりしておくことが必要です。
β値のみで投資判断しないことも重要です。株式投資の世界ではβ値以外に、予想株価収益率(PER)や株価純資産倍率(PBR)、配当性向などといった多くの投資指標が存在します。β値はあくまでも投資指標の1つと捉え、他の投資指標と組み合わせて銘柄選択の手段として利用することが望ましいといえます。損切りも含めた自身の売買ルールをしっかりと決めて、機動的に対応することも重要です。
なお、β値は過去のデータに基づいて株価指数と個別銘柄の相関関係を数値化したものです。決して将来どう動くかを予測するものではないことを理解しておきましょう。企業の業績動向や市場全体の状況によってはβ値が大きく変動する可能性もあります。現時点のβ値が将来にわたって同様のリスク・リターンとして期待できる数値ではないことに留意しておいてください。
■まとめ
β値とは、株価指数の動きに対して個別銘柄がどれくらい連動したかを表したもので、個別銘柄のリスクとリターンの大きさを示した指標です。β値が1より大きい場合は市場全体に比べて値動きが大きく、相場変動に対するリスクが高くなることを意味します。皆さんそれぞれにとって望ましいリスク・リターンのバランスを踏まえ、銘柄選択の際の1つの投資指標としてβ値を活用してみてはいかがでしょうか。





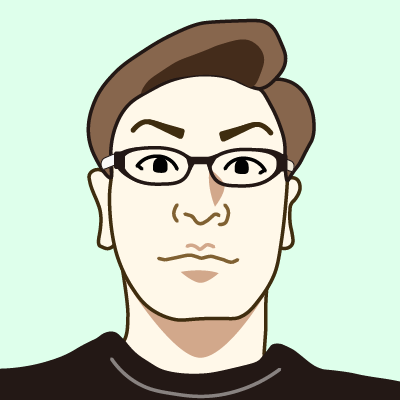








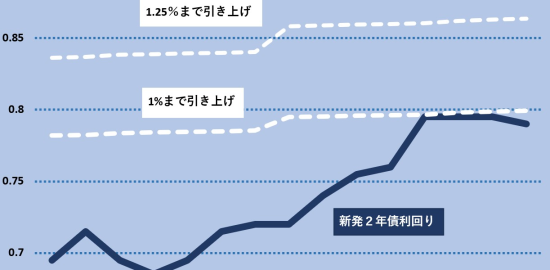


.png)








