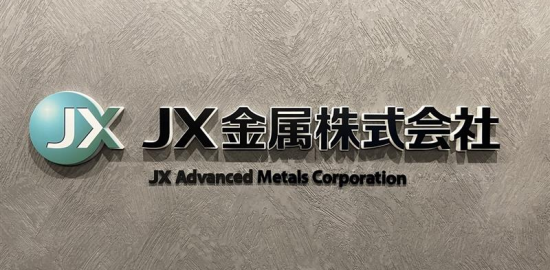【QUICK解説委員長 木村貴】お金は前回説明したように、商品から生まれる。だからお金として使う以外に、商品として使うことができる。まもなく新札が登場する日本円をはじめ、現代のお金はお金以外に使い道がない。これはお金本来のあり方に反している。また、お金は市場で自由な競争を通じて生まれるものだから、政府・中央銀行が製造を独占することもお金本来のあり方にそぐわない。
優れたお金を選ぶ市場競争
歴史上、さまざまな地域で多くの種類の商品がお金として役立ってきた。穀物、巨石、宝石、家畜、貝殻、タバコなどだ。いろいろな商品が人々に日々利用され、より優れたお金が選ばれていった。お金の市場競争だ。お米などの穀物はある程度日持ちはするものの、やがて腐ってしまう。大きな石は丈夫だが運びにくいし、小分けしにくい。家畜は自分で歩いてくれるが、個体によって大きさや品質が異なる。ダイヤモンドは一見、お金にふさわしいようだが、均質でない。大きな一つのダイヤのほうが、合計の重さが同じいくつかの小さなダイヤよりも価値がある。取引の手段としては使いにくい。

こうして最後に残ったのが、金や銀の貴金属だ。金や銀はお金にふさわしいいくつかの性質をすべて備えていた。日持ちする、小分けしやすい、均質である、運びやすい、取引しやすい大きさと重さ——などだ。
金は当初、金塊や砂金、装飾具などの形でお金として利用されていた。米経済学者エドウィン・ケンメラー氏の著書によれば、古代メキシコやアフリカなどでは、金は透明な羽軸に詰められ、取引に使われた。古代中国では小さなサイコロ状で流通していた。紀元前数百年頃、金は小アジア(アナトリア半島)や欧州の大部分で交換手段として使われた。銀については、「目には目を、歯には歯を」で知られる古代メソポタミアのハンムラビ法典に、お金としての最も古い使用の記録がある。
金や銀がお金に向いていても、金属としてそのままの状態では使いにくい。商店に訪れたお客が支払いのために金や銀の塊を持ち込み、それを店主がいちいち本物かどうか検査しなければならないとしたら、不便で仕方ないだろう。
この問題を解決するには、金や銀の塊を、大きさや純度が同一のコイン(硬貨)に鋳造すればいい。金貨や銀貨だ。それは政府・中央銀行によって鋳造される場合もあるだろう。ただし注意が必要だが、金貨や銀貨がお金として通用するのは、政府・中央銀行という公的な権威が製造し、その刻印が押されるからではない。特定の量と品質の金や銀が含まれることで、人々が安心して受け入れるからだ。
コインを鋳造する以外に、金や銀をお金として使いやすくする方法はもう一つある。一定量の金や銀と交換できる代用コインを発行することだ。代用コインであっても、お金として立派に通用するためには、見分けがつきやすく、偽造されにくいものでなければならない。
現代でたとえれば、カジノが発行するプラスチック製のチップを思い浮かべればいいだろう。米ラスベガスのカジノが発行するチップは、見分けがつきやすく、信頼できる見映えで、外部の者がたやすく複製できないものでなければならない。チップはカジノの中ではただちに換金できるから、お金と同等の値打ちをもつ。
こうして金と銀はお金として洗練され、進化していった。
民間造幣所の活躍
お金はもともと政府当局の介入なしに生まれたものだから、コインの製造も政府部門ではなく、民間部門で行うことができる。むしろ歴史上、最上質のコインや代用コインの一部は、民間の造幣所で製造された。
18世紀の英国で、政府の王立造幣局は日々の経済活動に十分な量のコインを製造することができなかった。そのせいで、人々は不便を強いられた。事業の雇い主は従業員に賃金を払うのに、「波状払い」をしなければならないことがあった。たとえば、従業員の3分の1に賃金としてコインを支給し、彼らがそれを町で使ったら、雇い主はそのコインを買い集め、次の3分の1の従業員に支払う、という苦肉の策だ。
政府製のコインがあまりにも不足したため、明らかな偽造コインであっても使われた。「悪いお金でも、お金がまったくないよりましだったからだ」とオーストリア学派のエコノミスト、ロバート・マーフィー氏は説明する。
政府の無能が招いた不便きわまる状況の中、「必要は発明の母」のことわざどおり、民間の貨幣製造業が生まれ、活躍する。有名なのは1788年、実業家マシュー・ボールトンが設立したソーホー造幣所だ。ボールトンは、発明家ジェームズ・ワットと組んで蒸気機関を商品化したことで知られる。ソーホー造幣所でも蒸気力を利用し、精巧なコインを生産した。今も残るソーホー製の美しいコインは、民間造幣所のみごとな職人技を示している。
「金のなる木」を信じた愚
金や銀がお金にふさわしい理由はもう一つある。政府・中央銀行がいつでも勝手に発行できる現代のお金と違い、採掘・精製しなければならないため、短期で大幅に量を増やすことができない点だ。そのことを知らない人形ピノッキオは、だまされてひどい目に会う。19世紀イタリアの作家カルロ・コッローディがつくった物語『ピノッキオの冒険』の中での出来事だ。
ピノッキオは大切な金貨を持ち帰る途中、悪いキツネとネコから、金貨を「奇跡の原っぱ」に埋めて水をやると金貨のどっさりなった木がたちまち生えると言われ、大喜び。金貨がとれたらお礼をあげると言うと、キツネとネコは殊勝ぶって、こう答える。「私たちは、そんなつまらない儲けのために、こんなアドバイスをしてるんじゃありません。ほかの人たちを、お金持ちにしてさしあげようと考えているだけです」(大岡玲訳)
今でも投資詐欺に使われそうなせりふだ。しかしピノッキオは信じて金貨を埋め、キツネとネコは掘り起こして逃げ去る。とまどうピノッキオをオウムがこう笑う。「お金を原っぱにまけば、豆かカボチャみたいにたくさん収穫できると思うなんて、きみは塩気の抜けたよほどのぼんやり者だよ」
もしもピノッキオが信じたように、誰もが「金のなる木」で金貨をあっという間に大量に増やせたら、金貨の値打ちは紙切れ同然に下がり、財産として持つ意味がなくなってしまうだろう。それを理解しないピノッキオは、オウムがいうように愚かだった。
けれども、現代人の多くにピノッキオを笑う資格はないだろう。「金のなる木」の投資詐欺には引っかからなくても、中央銀行がまるでおとぎ話の「打ち出の小槌」を振るようにお金の量を増やし続ければ、幸せになると信じた人が多いのだから。それがインチキだったことは、最近の物価高や急激な円安で、誰の目にも明らかになってきた。
誰かが勝手に発行量を短期間で大幅に増やせることは、優れたお金の条件に反する。金と銀がかつて人々に最善のお金として選ばれ、今もインフレ対策の有力な手段となっている事実は、現代の通貨制度がその根本に抱える深刻な問題を浮き彫りにする。