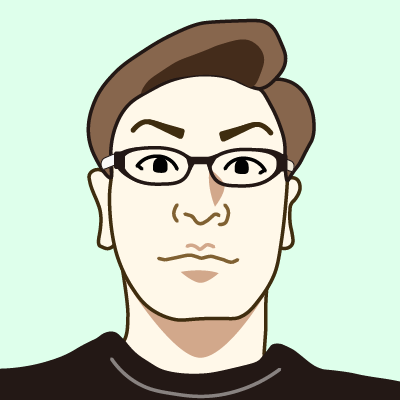【QUICK Money World 荒木 朋】全世界が注目する2024年の一大イベントで11月5日に控える米大統領選挙まで1カ月を切りました。現職大統領のジョー・バイデン氏に代わり民主党の新たな大統領候補となった カマラ・ハリス現副大統領と、共和党候補で返り咲きを目指すドナルド・トランプ前大統領との争いは終盤戦に突入しています。
米大統領選の結果は国際政治の行方を左右するだけでなく、世界の金融・株式市場にも大きな影響を及ぼす可能性が高いため、世界の市場参加者が注目しています。大統領選に関する最新の世論調査ではハリス氏が有利とする調査もみられます。本記事では、ハリス氏が当選する「もしハリ」となった場合の世界の政治経済や株価に与える影響などについて詳しく解説していきます。
ハリス氏vsトランプ氏 2024年の大統領選のポイント
米大統領選は4年に一度行われる一大イベントですが、2024年の大統領選は過去の選挙と比べても異例な点がいくつかあり、選挙戦の動向に世界の注目が集まっています。
当初は現職の民主党候補ジョー・バイデン氏と共和党候補トランプ氏との間で選挙戦がスタートしました。しかし、6月下旬に行われた2人によるテレビ討論会ではバイデン氏が精彩を欠き、不安視されていた高齢問題が改めて台頭。オバマ元大統領など民主党重鎮らが相次いでバイデン氏の選挙戦継続への懸念を表明したことを受け、バイデン氏は7月に選挙戦からの撤退を表明しました。
バイデン氏に代わり、民主党の後継候補として指名されたのがハリス氏です。ハリス氏はインド系の母とジャマイカ系の父の間に生まれ、2021年に黒人、女性、アジア系として初めて米副大統領に就きました。今回、米国史上初の女性大統領を目指します。
女性候補としては2016年に民主党のヒラリー・クリントン氏が選挙戦に挑みましたが、戦前の有利予想に反してトランプ氏に敗北した過去があります。女性の地位向上を阻む見えない障壁を指す「ガラスの天井」を今回こそ打ち破ることができるのか、ハリス氏の選挙戦はこうした観点からも注目を集めています。
共和党候補のトランプ氏は、2017年に第45代米大統領になった後、2期目の再選を目指した2020年の選挙戦でバイデン氏に敗北しました。今回、米大統領選史上2人目となる大統領返り咲きを目指します。トランプ氏は複数の刑事裁判を抱える中で選挙レースに挑んでいます。刑事裁判の判決は大統領選後になるとみられますが、大統領経験者の起訴は米国の建国以来初めてで、大統領選と裁判を同時進行で行う異例の選挙戦となっています。
米大統領選では、それぞれの候補者の資質や人気はもちろん、経済政策や外交政策に対する国民の評価が勝敗のカギを握ります。最大の注目点は選挙のたびに勝者が入れ替わる「スイングステート(揺れる州)」と呼ばれる激戦州での勝敗の行方です。
米国は50の州で構成されていますが、多くは民主党の支持基盤が盤石な州と共和党の支持基盤が盤石な州が分かれており、これらの州ではどちらの候補が勝利するか選挙前にほぼ確定しています。一方、激戦州は6~7つあると言われており、その中でも主に中西部に位置しラストベルト(さびついた工業地帯)と呼ばれるミシガン、ウィスコンシン、ペンシルベニアの3州は選挙結果に大きな影響を及ぼすとされています。
こうした状況を踏まえ、選挙戦の戦略上、大きなポイントの1つになるのが「ランニングメート(伴走者)」と呼ばれる副大統領候補の存在です。ランニングメートは大統領候補とともに選挙戦を戦い抜く重要な役割を担います。大統領候補の弱点を補える人物が選ばれることが多く、副大統領の立ち位置や発言は浮動票やスイングステートの得票獲得にも影響を与えます。
民主党の副大統領候補には中西部ミネソタ州のティム・ウォルズ知事が指名されました。一方の共和党は中西部オハイオ州出身のJ・D・バンス上院議員を指名しました。いずれの候補者も勝敗を左右する中西部やラストベルトの各州の中間層や労働者票を取り込み、地盤を固める狙いがあるとされています。両候補による討論会は10月1日に開催され、激論が交わされました。
そもそも米大統領選はなぜ重要なのか?
そもそも米大統領選はなぜ重要なイベントになるのでしょうか。理由の1つとして、米大統領選の結果を受けて、今後4年間の米国の政治や経済政策の方向性が決まる点が挙げられます。米国の外交政策や経済政策のかじ取りはその後の米経済の動向を左右します。それが米株や米金利の変動要因となり、その影響が世界の金融・株式市場にも波及するという経路をたどるのです。日本もその影響を大きく受けます。
米国のマーケット動向は世界の金融市場にも波及する可能性が高く、そのため世界の投資家は大統領選の結果とその後の経済政策などの行方を注視しています。仮に現在の民主党政権から共和党政権に代わることになれば、海外紛争などに関する外交政策も変化する可能性があります。米国から軍事支援を受ける紛争当事者にとっては今後の方向性を左右しかねません。地政学リスクも金融・株式市場の大きな変動要因の1つになります。
2024年の米大統領選によって米国の政治がどう変わり、どのような経済政策がとられるのかは今後のマーケットを見極めるうえで非常に重要なポイントになります。
トランプ氏は2017年に大統領に就任した際、法人税率の引き下げなど「トランプ減税」とされる抜本的な税制改革のほか、大規模なインフラ投資や「米国第一主義(アメリカ・ファースト)」の旗印のもとで追加関税の実施など保護主義的な通商政策を打ち出しました。
今回、減税策については期限の撤廃で恒久的な制度にすると主張するほか、接客業に従事する人々が受け取るチップを非課税にしたり、社会保障の給付金への課税を廃止したりして、さらなる減税策を推し進めると表明しています。
産業面では、バイデン政権の気候変動対策の巻き戻しを掲げて、石油や天然ガスなど化石燃料生産に対する規制の撤廃や電気自動車(EV)優遇制度の廃止なども訴えています。製造拠点と雇用の国内回帰に向け、海外から米国内に生産拠点を戻す企業向けの税制優遇のほか、規制緩和の恩恵が受けられる「特区」を設ける構想なども明らかにしています。
一方、ハリス氏は「オポチュニティ―・エコノミー(機会の経済)」の実現を掲げて、とりわけ中間層の底上げを図る経済政策を推進すると訴えています。生活費抑制、起業家支援、次世代産業促進の3つを主要政策に据え、物価高に苦しむ中間層の生活負担の軽減を最優先課題にすると宣言。中間層向けの所得減税のほか、住宅購入支援や子育て世帯の税額控除、食品価格の引き下げなどに取り組み、1億人以上の国民の減税実現を目指すとしています。
産業面では、起業家に対する税額控除の拡大や中小企業向けの低利・無利子融資の拡大を掲げるほか、バイオ、AI(人工知能)、量子コンピューティング、ブロックチェーン、クリーンエネルギーなどを重点的な投資分野とし、次世代産業拠点づくりを進めるための新たな税優遇制度である「アメリカ・フォワード税制」を新設すると明らかにしました。中間層への支援を手厚くする半面、大企業には適正な税負担を求めるとして、法人税率を現在の21%から28%に引き上げると宣言しました。
法人税率は前回のトランプ政権下で35%から21%に引き下げられていました。現在のバイデン政権はこれを28%に戻すことを目標に掲げていましたが実現しておらず、ハリス氏はこの方針を引き継いだ格好です。
金融政策については、トランプ氏は米連邦準備理事会(FRB)の政策決定に「関与すべき」との見解を表明する一方、ハリス氏は「決して干渉しない」などと明言したと伝わっています。
ハリス、トランプ両候補の政策には異なる点も多いだけに、どちらの候補が大統領になるかによって金利や為替、株価の方向性にも大きな影響を及ぼし得ることは避けられない状況といえます。
|
<関連記事> |
この他にも、QUICK Money Worldは金融市場の関係者が読んでいるニュースが充実。マーケット情報はもちろん、金融政策、経済情報を幅広く掲載しています。会員登録して、プロが見ているニュースをあなたも!メールアドレスの登録だけでなく、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。人気記事を紹介するメールマガジンや会員限定オンラインセミナーなど、無料会員の特典について詳しくはこちら ⇒ 無料で受けられる会員限定特典とは
ハリス氏が当選すると株価はどうなる?
米大統領選は終盤戦を迎えていますが、各種世論調査などを受けて、金融・株式市場では米政治の行方や米経済政策の先行きを少しずつ織り込んで取引されていくことが想定されます。米国では主要メディアが米大統領選の特集を組んでいるほか、大統領選挙に関する世論調査などを公表するウェブサイトも数多くあり、米政治専門サイト「リアル・クリア・ポリティクス」や、政治経済などの世論調査の分析を行う「538(ファイブサーティエイト)」などがよく取りあげられます。
リアル・クリア・ポリティクスによれば、バイデン氏が撤退し新たにハリス氏が候補となって以降、ハリス氏の支持が急速に盛り返し、8月にはハリス氏の支持がトランプ氏の支持を上回りました。その後、初の直接対決となった9月のテレビ討論会を経てハリス氏への評価が続き、現時点ではハリス氏がトランプ氏をリードする状況が続いています。
仮にハリス氏が新大統領になった場合、株価はどのように動くのでしょうか。
まず、米大統領選挙と米国株の関係をみると、民主党か共和党のどちらの候補者が勝利するかにかかわらず、選挙前年に米国株は上昇する割合が高く、選挙年は前年に比べてパフォーマンスはさえないものの上昇が続く傾向にあるというアノマリー(経験則)が見て取れます。
1970年代以降のダウ工業株30種平均の年間騰落率をみてみると、大統領選挙年にあたる1972年から2020年までの計13回のダウ平均の年間騰落状況は上昇した年が10回、下落した年は3回で、平均騰落率はプラス5.9%でした。2024年は9月末時点で10%以上上昇しています。選挙結果を見極めたいとして様子見姿勢も強まるものの、選挙後の経済対策などへの期待も高まりやすいことが株価上昇につながる要因とみられます。
バイデン政権は、脱炭素など「環境」重視の政策などを掲げて、クリーンエネルギー政策や大規模なインフラ刷新など「新しい産業政策」を推し進めました。ハリス氏もバイオ、AI、クリーンエネルギーなど次世代分野を中心に税優遇などの政策を進める方針で、バイデン政権と同じく、脱炭素に関連する電気自動車(EV)や太陽光発電といった環境関連企業、インフラ整備関連企業、新しい産業政策に伴う最先端半導体などのハイテク企業などへの業績期待が相場全体を下支えする可能性がありそうです。米金融政策が利下げ方向に転換したことも追い風で、利下げで米金利が低下すればグロース株と呼ばれる成長株の押し上げも期待できそうです。
先行きの株価を占ううえでもう1つ注目されるのは、ハリス氏が家計負担の軽減策を進める一方で法人税率の引き上げを主張している点です。複数の金融機関の調査によると、ハリス氏が公約として掲げる法人税率を21%から28%に引き上げた場合、個人消費の上振れが期待される半面、企業の設備投資抑制などのマイナス面が影響し、米企業の利益が1割近く押し下げられるとの試算もあります。株価の最大の決定要因である企業業績の下振れリスクが意識されれば、株式相場全体の重荷になる可能性があります。
最新の世論調査ではハリス氏優勢とのデータが出ていますが、予断は禁物です。前述の通り、2016年の米大統領選では民主党のクリントン候補が優勢との事前予想に反して共和党のトランプ候補が大勝利を収めました。トランプ氏が当選に近づくなか、世界で最初に大統領選の結果を織り込んで取引されたのは東京市場でしたが、トランプ氏の保護主義的な通商政策や強硬的な外交政策などの警戒要因に目が向かった結果、当時の日経平均株価は919円安という大幅安で終えました。
しかし、その後はトランプ氏が掲げていた法人減税やインフラ投資、規制緩和などの景気刺激策へのプラス面に目が向かい、大幅安となった翌日の日経平均株価は一転して1000円を超える大幅高となりました。その後も米株高と歩調を合わせるように日経平均株価は上値を追う展開となりました。
民主党、共和党それぞれどちらの候補が勝っても、長期的には「選挙は買い」という経験則はあるものの、選挙前後の株式相場は短期的に変動の大きい展開になりやすい点は肝に銘じておくべきです。2016年の大統領選後のように市場の解釈次第で相場の動きは一変する可能性があります。個人の皆さんにとっては、一大イベント後の拙速な投資判断は避けて、相場の方向性がある程度出たところで投資行動を起こすようにするといいでしょう。
米国や欧州では現在、長らく続いた利上げ局面から一転して利下げ局面に移行してきました。利下げは金利低下を促し、株価にはプラスとされるのが一般的な見方です。ただ、利下げを継続しなければならないほど景気が悪いという見方が浮上すると、株価には下押し圧力として意識される可能性もあります。
今のところ、米景気は大きく悪化せず軟着陸する可能性が高いとの意見が多く聞かれますが、大統領選後の新政権の経済対策などを見極めることも大切です。長期的な視点を持ちつつ、焦らず投資することを心がけるといいでしょう。
もしもハリス氏が大統領になったら?「もしハリ」関連銘柄
米大統領選で民主党候補のハリス氏が勝利する「もしハリ」となった場合、日本ではどのような銘柄が恩恵を受けるとみられているのでしょうか。前述の通り、米国では脱炭素に関連する電気自動車(EV)や太陽光発電といった環境関連企業、インフラ整備関連企業、新しい産業政策に伴う最先端半導体などのハイテク企業などへの恩恵が大きくなるとみられ、日本でも同じような業種・セクターが物色される可能性が高そうです。
ハリス氏は住宅支援策に言及しており、米国事業の比率が高い住宅メーカー株はその恩恵を受ける可能性があります。関連銘柄としては、米国事業が利益柱となっている住友林業(1911)、2024年に入り米住宅大手を買収しシェア拡大を狙う積水ハウス(1928)などが挙げられます。また、住宅用の塩化ビニル樹脂などに強みを持つ信越化学工業(4063)なども関連銘柄の1つです。
生活コストの削減方針を示したことで、米国事業を積極展開する食品メーカーにも追い風になる可能性があります。北米しょうゆ事業が拡大するキッコーマン(2801)、北米の即席めんシェア上位の東洋水産(2875)、日清食品グループホールディングス(2897)などが主な関連銘柄です。
たこ焼き「築地銀だこ」を展開するホットランド(3196)は3月、大谷翔平選手が大活躍するロサンゼルス・ドジャースのホーム球場である「ドジャー・スタジアム」内に「築地銀だこ」をオープンすると発表。5月にはドジャースと複数年のスポンサーシップ契約を締結したと発表しました。大谷選手の活躍も追い風に知名度向上に伴う業績寄与への期待も高まるかもしれません。
環境関連も注目銘柄の1つです。例えば、太陽電池の製造装置などを手掛けるエヌ・ピー・シー(NPC、6255)。NPCは米太陽光パネルメーカーであるファースト・ソーラーが主要取引先となっています。ハリス氏とトランプ氏による9月10日のテレビ討論会を受けた世論調査でハリス氏優勢との結果を受け、ファースト・ソーラー株は翌日の取引で15%の大幅高となりました。これを受けてその後の東京市場でNPC株もつれ高し、一時15%高となりました。
| <関連ページ> |
まとめ
世界が注目する4年に一度の一大イベントである米大統領選が間近に迫っています。女性初の大統領を目指すカマラ・ハリス現副大統領と、米大統領選挙史上2人目の返り咲きを狙うドナルド・トランプ前大統領の戦いは佳境を迎えています。9月10日に行われたテレビ討論会ではハリス氏優勢との見方が多く、世論調査ではハリス氏がトランプ氏を現状上回っています。ただ、勝負の行方は蓋をあけるまで分かりません。
米大統領選の結果は米国の政治の行方を左右するだけでなく、世界1位の経済大国である米国の経済政策の向こう4年間の方向性が決まる重要なイベントです。ハリス、トランプ両氏の掲げる経済政策は世界の経済や金融・株式市場にも影響を及ぼすため、世界の市場参加者が結果に注目しています。日本の政治経済や株価の動向にも多大な影響を与えます。先行きの投資スタンスを適正に判断するためにも、米大統領選の行方と相場全体や関連銘柄への影響などについて、今のうちに頭の体操をしておくといいでしょう。
「QUICK Money World」の有料会員になると、プロのマーケット予想や企業分析など全ての記事が読み放題となるほか、企業の開示情報やプレスリリースをメールで受け取れます。提供情報をもとにマーケット予想や企業分析まで行いたい方にピッタリです。マーケット予想から企業分析まで最大限活用したい方は、有料会員登録をご検討ください。メールアドレスの登録だけでなく、Googleアカウント・Apple ID等でも登録できます。詳しくはこちら ⇒ 有料会員限定特典とは