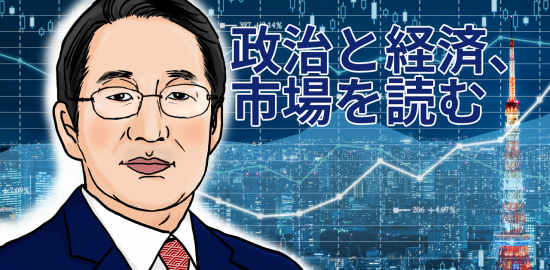狩猟民族の心構えがなければディーリングには勝てない――。市場のベテランに相場との向き合い方を聞く「ベテランに聞く」の第2回はグローバルマーケット・アドバイザーの小池正一郎氏。外国為替市場の生き字引で円が変動相場制に移る以前から市場に関わってきた小池氏は、日本人が好むレンジ前提で相場の流れに逆らう取引の「待ちの姿勢」を批判する。そのままでは欧米投機筋などの執拗な順張りには到底太刀打ちできないという。【聞き手は日経QUICKニュース(NQN)編集委員=今晶】

小池正一郎(こいけ・しょういちろう)氏
1969年に長銀入行後、外国為替畑を主に歩き、2度のニューヨーク支店経験をもつ。長銀証券を経てスイスUBS銀行外国為替本部の在日代表に就いた後、米シティバンク・プライベートバンクに移籍。2006~15年に国際金融情報コンサルティング会社のプリンシパリス・日本代表を務め、現在にいたる
■徹頭徹尾アグレッシブなスタイル
高収益を目指すにあたって必要な心構えはいくつかあるが、その1つが「市場は狩猟民族が仕切る」との認識だ。著名投資家ジョージ・ソロス氏にせよ、ジム・ロジャーズ氏にせよ、そのトレードスタイルは徹頭徹尾アグレッシブだった。狙った獲物をどこまでも追いかけるように、相場の流れに乗る順張りを突き詰めてくる。
苦い経験がある。日本長期信用銀行(現新生銀行)のニューヨーク拠点でトレーダーをしていたときだ。ドルが対円で上げ始めた局面で、なじみの外国銀行ディーラーからレートを出すよう求められた。ドルの売りと買い双方のレートを示すと彼は買ってくる。しばらくするとまた彼から再びレートを出せと言われ「さらに買われると困るからややドル高にしよう」とレートを提示するとちゅうちょせずに買う。その後間を置かずに再び彼から呼ばれ、かなりドル高の水準を示したにもかかわらずたたみかけて買ってくる。
海外勢のこうした買いによってドルは上昇する一方だったが、売り手に回ったこちらは含み損でノックアウト寸前。「狩猟民族はこういうものか」と心底怖くなった。
足元では狭い範囲で売り買いを繰り返す機械取引の「HFT」が増えてきたものの、欧米勢の基本的なマインドは変わっていないはずだ。ここ数年だと2016年の英国による欧州連合(EU)離脱決定やトランプ相場などで一度動きが出ると、狩猟民族の強みをいかんなく発揮する。軽い気持ちで逆張りをすると大けがしかねない。
■高いところにお金が流れる
相場予想をする際にまず押さえておきたいのは「高いところにお金が流れる」との原則だ。高い低いの判断基準は安全性と成長性、利殖性の3つ。安全性には市場規模の大きさや取引の自由度をあらわす「流動性」の概念を含む。
有事の際に円買いが進むのは、日本が国として安全だからではなく、円の流動性が高いためだと理解すべきだろう。利殖性は一般市民の目線で、名目金利から物価上昇率を差し引いた「実質金利」の高低が深くかかわってくる。
この原則を18年の相場に適用すると、米ドルと米国株が有望とみている。市場では米利上げが米景気を冷やすとの懸念がくすぶっているものの、米経済指標は今のところ堅調で、景気の腰は相当に強いのではないか。米株式相場の上昇局面はまだ続くと思う。
次に相場は生き物であり、勢いの強弱について常に意識しなければならない。例えば幼、青、壮、老の4段階に分け、現在どのレベルにいて基調転換の可能性がどの程度高いかを考えていく。市場は群集心理に左右されるので、参加者が何を注視しているのか、いち早く情報を得る努力も必要だ。
■地球儀を眺める気持ちで視野を広げよ
「地球儀の上に立って世界を眺めろ」。いつだったか、米バンカース・トラスト(現ドイツ銀行)の名物ディーラーがこんなアドバイスをくれた。外為市場の中心はユーロの対ドル取引やドルの対円取引で、日本人に限らず円、ドル、ユーロの主要3通貨ばかり見てしまいがちだ。だが他にも収益源はいっぱいある。
2回目のニューヨーク赴任後、のちにソロス・ファンドのアドバイザーを務め、ソロス氏による1992年の英ポンド売りの舞台裏をよく知るリチャード・メドレー氏(故人)と親しくなった。メドレー氏がごく限られた人数向けに開いたパーティーで、デビッド・マルフォード氏(元米財務次官)などの「通貨マフィア」(通貨当局の事務方の幹部)に近づけた。ヘッジファンド業界のことも深く知り、視野が急速に広がった。メドレー氏がその後、調査会社を立ち上げ、市場に影響を与えたのは周知の通りだ。
インターネット全盛の現代は情報があふれていて、玉石の見極めはかなり難しい。既に通貨マフィアの時代ではなく、政府や中央銀行、民間金融機関はコンプライアンス(法令順守)の制約がきつく、昔のように独自に質の高い情報を得られることはなくなった。ただ、人でもメディアでもいいので、信頼できる情報源を1つでも作っておきたい。
個人的なおすすめは英エコノミスト誌だ。記事は長くて小難しいが、表紙などの風刺画に政治や経済、市場の本質がうまく表現されている。それを見るだけでも参考になる。
(随時掲載)