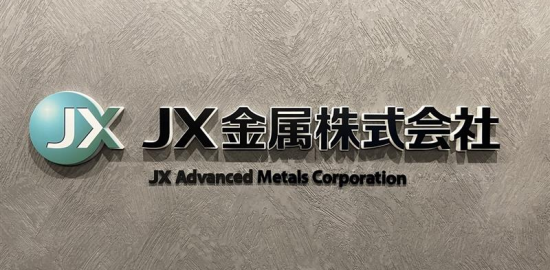ドルペックがバブル助長、リーマン危機も同根
三和銀行(現三菱UFJ銀行)外国為替部門の大物ディーラーで鳴らし、剣道の達人でもある今井雅人氏は現役時代、研ぎ澄まされた勘で相場の転換点を察知し、アジア金融危機をもたらした新興国の過剰なドル調達や対米ドルの固定相場制(ドルペッグ)といった背景を見逃さず利益を出した。「おいしい話は永遠に続かない」。誰もが分かっているはずなのに、もうけたいとはやる心が先に立ってバブルを生んでしまう――。今井氏は「利益追求が市場参加者の目的である限り、危機は繰り返す」と断言する。

今井雅人氏
いまい・まさと 1985年に三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行。89年から5年間米国のシカゴ支店で勤務し、通貨先物市場を通じて外国為替市場との関わりを深めた。三和銀と東海銀の合併で生まれたUFJ銀行のチーフディーラーを経て2004年に退職し、金融情報会社グローバルインフォ(現DZHフィナンシャルサービス)を設立。マットキャピタルマネジメント代表兼経済アナリストとしてい積極的に情報配信を続ける。09年から衆院議員を務め、現在4期目
◆腑に落ちない値動きが虫の知らせ
成功体験を1つを挙げるとすれば、アジア通貨危機やロングターム・キャピタル・マネジメント(LTCM)破綻などを受けて市場が混乱した1997~98年だ。98年の秋にはあっという間に20円近く円高・ドル安が進むなどかなり荒っぽく動いた。実は円高が加速する直前までずっとドルを買い持ちにしていたのだが、ふと居心地の悪さを覚えて円買い・ドル売り戦略に変えた。とたんに円は上昇し、1ドル=115円を大幅に超えたところで利益を確定できた。
なぜ持ち高をひっくり返そうと思ったか。タイミングについては虫の知らせとしかいいようがないが、予兆は感じていた。水準自体は1ドル=140円台で安定していたにもかかわらず値動きがかなりおかしかったのだ。
例えば1ドル=140円20銭で厚い円買い・ドル売り注文が控えているのにそれよりも円安の140円50銭で取引が成立した後、次の出会い値が再び140円20銭になるといった具合だ。外為取引は短い期間で資金交換を終えるため、無担保でお金を貸し借りする市場に比べると与信管理は緩い。それでも決済リスクなどを考慮し、経営基盤が弱そうな銀行とは取引しない。売りと買いのレートの逆転現象は特定の金融機関を巡る不安が水面下で広がっている状況を示唆しているのではないか。そう解釈した。
修羅場をくぐったディーラーには市場の空気をかぎ分ける力が備わっている。仲介業者(ブローカー)の声と電子トレーディングシステム(EBS)の取引画面が伝える生の注文状況や、次々と成立していく取引などの一次情報から投資家やディーラーが何を考えているのか、何が起こっているのかを判断していく。メディアやインターネットで流れる相場動向は二次情報でしかなく、重要度は低い。
1997~98年に話を戻す。当時のアジアはほとんどが成長途上の純債務国。金利の低い米ドルで資金を調達し、自国を含めた金利の高い国で運用して利息収入を稼ぐ「キャリー取引」に傾いていた。ドルペッグ制の下で、アジア通貨の対ドル相場は動きが鈍いとの前提にたつ危うい戦略だった。ひとたび投資家が運用資金を引き揚げると取り付け騒ぎのような状態に陥る。
タイから始まったマネー収縮は瞬く間に広がり、タイが変動相場制に移ると他の国も固定相場を維持できず、98年には多くがペッグ制を廃していった。傷を負った世界の金融機関や投資家は体力低下に苦しむ。それを察知した他の市場参加者は与信枠を絞り、EBSなどが示す値段の不可解さにあらわれる。
◆2007年まだ危機感薄かった日米欧の金融当局
2008年にリーマン・ショックが起きたときはアジア危機とそっくりだと思った。07年の「パリバショック」から小康状態を挟み、本格的な金融危機にいたる2段階の構えは、タイバーツの暴落からアジア全体の危機に波及したころと似ていた。原油高で潤った中東などのオイルマネーがドルペッグ制をテコにドル建ての資産に流れ、低所得者向け融資(サブプライムローン)証券市場の過熱をもたらしたのもアジア危機前のキャリーブームを連想させる。
07年の冬に榊原英資元財務官(現インド経済研究所理事長)とニューヨークに出張した。前半は当時のガイトナー・ニューヨーク連銀総裁やサマーズ元財務長官など当局関係者や学者を中心に回った。日本の財務官だった篠原尚之氏(現東大教授)が後に振り返っている通り、日米欧ともに金融・通貨当局の危機感はまだ乏しく、市場の混乱を楽観的に捉えている印象を受けた。
半面、出張後半に訪れたゴールドマン・サックスやメリルリンチなどの投資銀行の幹部、ジョージ・ソロス氏といった著名投資家を回ると様子が違う。「金融機関の資金調達が難しくなっている」「何となくおかしなムードだ」との声が相次いだ。榊原氏とは「市場の混乱は止まりそうにない」との意見で一致した。
米政府の最大のミスはリーマン・ブラザーズをさっさと見限ったことだ。1つの銀行が倒れると市場は「次はどこか」と疑心暗鬼になり、短期金融市場を中心に取引が凍りつく。信用不安の怖さはアジア危機で身にしみていたはずだが、教訓を生かせなかった。数カ月前にベアー・スターンズを処理して安心したのだろうか。もしリーマンも救っていたら激震は食い止められたかもしれない。
◆何事も永遠には続かない
危機はたいてい、みなが「大丈夫だろう」と慢心した後に起こる。言い換えれば誰もが「危ない」と警戒しているときには何も起こらない。昨年末から19年初めにかけて株式相場が急落すると、「19年の後半は危ない」との予想が増えたが、2月にかけて株高が再開した。本当の危機の芽は心理的な要素が濃く、目には見えにくい。
アジア危機やリーマン・ショック時は日米欧や新興国の間でだいぶ金利差が開いていたので、キャリーによるバブルの可能性を主にチェックしておけばよかった。だが足元では主要国の金融緩和と金融機関の規制強化によって金利格差を背景にしたカネの流れは細っている。傾斜は株式など他の資産できつくなっていると考えられるが、PER(株価収益率)の点などから判断すると株式相場がとんでもなく割高とまではいえないのが実情だ。ではリスクの芽はどこに潜んでいるのか。
個人的に気になるのが中国の不動産市場だ。深センなどの新興地域に向かうと不動産価格の異常さに驚く。日本円で500万円だった土地がわずか数年で2億円に達するぐらいの上げ幅を普通に記録している。この部門が崩れると怖い。ただ中国では不動産も株も手掛けるといった総合投資家が少なく、株の相場には不動産ほどの熱は感じられない。このままいくとしばらくは中国が大崩れすることはないだろう。
2018年初めにかけての仮想通貨ブームも既に去り、金融・資本市場への影響も薄れた。一時は国境をまたいでの通貨機能に期待が増えていたが、主権国家における通貨発行権は極めて重要なものだ。もし侵害されれれば政府・中央銀行はただちに規制するだろう。しかも仮想通貨は存在そのものに決定的な矛盾を抱えている。決済手段としての通貨は価格安定が不可欠なのに、投機資金で市場を活性化させるには変動がないといけない。
おそらく危機は、我々がいま把握していない場所から発生するのだろう。改めて肝に銘じておきたいのは、何事も永遠には続かないということだ。
=聞き手は日経QUICKニュース(NQN)菊池亜矢
=随時掲載