外国為替市場で世界的に円相場の膠着が続いている。マイクロ秒単位で売り買いを繰り返す高頻度取引「HFT」やHFT並みの高速売買をする個人の外為証拠金(FX)投資家の存在感が相変わらず大きく、もともと動きが小さかった東京市場に限らず欧米の取引時間帯でも「たかが1円動けば大相場」となっている。オプション市場では「ストラドル」や「ストラングル」と呼ばれる相場の波乱を前提とする取引の影が薄れている。
電子ブローキングシステム(EBS)のデータから3~4月の円の日米欧市場を通した日通し値幅をみると、米金融政策と世界景気の先行き不透明感が強まった3月20日と22日の1円10銭台が目立つ程度。4月に入ってからは1日と11日の70銭台が今のところ最も大きい。円が1ドル=111~113円台で停滞していた昨年10~12月と似た状況だが、今月は値幅が50銭に届かなかった日が12日までの10営業日で6営業日もある。

オプション市場では円の上値の重さが意識され、円高の為替差損リスクを回避(ヘッジ)する目的の取引が細って予想変動率(IV)の低位安定をもたらしている。IVの1カ月物は前週後半に4.7~4.8%台と、過去最低を付けた2014年夏以来の低さになった。大相場を前提とするオプション戦略に適した環境にはない。

ストラドルの買い手は権利行使価格が同じプット(売る権利)とコール(買う権利)を同額購入し、ストラングルは権利行使価格をやや離してプットとコールを求める。いずれも相場がどちらかに振れさえすれば利益を積みあげられるため、直物でも積極的に持ち高を傾けて収益の最大化を狙う。だが、その戦略が一昨年あたりからなかなかうまくいかなくなってきた。
「ストラングルやストラドルはむしろ、波乱なしを前提に売る参加者が増えている」(外国証券のオプションディーラー)という。15日の東京市場で円相場は一時1ドル=112円09銭近辺と前週末のニューヨーク市場で付けた3月以来の安値水準に並んだが、下落ペースは依然として緩やかだ。オプションの売りは行使されたときのリスクが極めて高いものの、背に腹は代えられない――。そんな空気が広がっている。
【日経QUICKニュース(NQN ) 今 晶】
※日経QUICKニュース(NQN)が配信した注目記事を一部再編集しました。QUICKの情報端末ではすべてのNQN記事をリアルタイムでご覧いただけます。




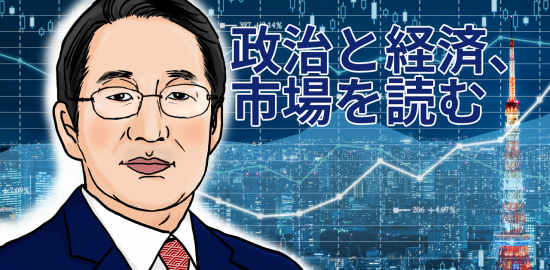






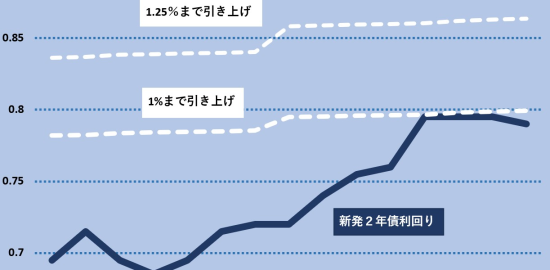


.png)








